すべてのカテゴリ
新着有料ブログ
89 件中 1 -
60 件表示

語呂合わせでゴロゴロする時間を作りませんか?
『勉強をする際、こんなお悩みはございませんか?』・どうやって勉強したらいいのかわからない。・資格勉強をしたいが、若いころみたいに記憶に定着しない。・暗記が苦手で、すぐに忘れてしまう。 私も勉強が苦手で、中学受験の時に1時間も勉強することができませんでした。 成績も悪く、家庭教師にも社会科目等の暗記ができておらず、勉強が間に合わないのではないかと危惧された経験があります。 そんな困っていた時に両親と勉強していて、ダジャレを考えるのが好きであったこともあり、ゴロを作って一緒に覚えようということで暗記をしました。 その結果、勉強が楽しく感じ、一日8~10時間勉強することで無事に第一志望へ合格することができました。 (中高時代は勉強をさぼっていたため、第一志望にはいけなかったのがネックです笑) その後も大学時代の勉強、国家公務員、国税専門官、国立大学法人の筆記試験の勉強についても上記ゴロにより記憶を長期定着化させることで無事最終合格まですることができました。 語呂は古典や生物、日本史等大学受験で使用するものはいくつかありますが、なかなか資格試験やマニアックな科目、当日のテスト範囲に応じたゴロが揃っていないため、知人等からも作成をしてほしいという話を聞き、いくつか作成し、共有した経験があります。 その際、同じような悩みを持つ方の支援を少しでもできればと存じ、以下のサービスを利用できればと考えております。上記サービス概要は以下の通りです。①購入者にて暗記したい項目(参考書の画像等)を6〜10頁お送りいただきます。
②当方にて語呂合わせを30個作成します。例1:日本史
語呂:なにさ?三千
0

長所で〇〇力は要注意。
面接の中で良く聞かれる定番の「長所」。
更に類似した質問で、
・あなたを採用するメリットは?
・あなたのセールスポイントは?
この質問に対してよく〇〇力があります。といわれます。
例えば
・調整力 ・忍耐力 ・向上力 ・傾聴力
・コミュニケーション力 ・分析力
特に最近はご時世的にか「調整力」を最もよく聞くように
感じます。
いつも面接でこの〇〇力って言われると、この力ってどの
くらいあるの??前の人も同じ事をいってたけどあなたと
どちらが凄いの?って疑問が沸いてきます。
また、例えば調整力をとっても、それって役職や立場的に皆が
調整するのでは?その職場だからできるのでは?
と新たな疑問も沸いてきます。
では、何をアピールすれば良いのか?オススメは他人に実際に
〇〇という変化を与えるようなことやモットーとなるものです。
例えば
他人に与える変化
・場を明るくするムードメーカー
・面倒見がよいお世話好き など
モット―
・凡事徹底(当たり前のことを徹底すること)
・前向きな考え方 など
を聞くと、内定後の働いているイメージが分かりやすくなります。
では、
〇〇力と伝えたら不合格なのか?いえいえ、もちろん合格する人も
沢山います。じゃあその違いはというと先の調整力をもう一度、例
に挙げると
①調整力があります。
私は現職場(学校)で意見が分かれ収拾がつかなくなる事態が起き
ました。そこで私は多くの意見がある中、皆の意見をよくききその場を
調整してきました。よって、この調整力を活かし〇〇で貢献していける
と考えています。
②調整力があります。
私は日ごろ職場(学校)では誰よりも先に
0

指導者の選択方法 ~経験者かつ有識者を狙い撃つ方法とは~
1.はじめに先日、コラムを一つ書かせていただきました。それについてのお問い合わせや感想などを想像以上に多くいただき、沢山の方に目にしていただけたことを嬉しく思っております。そして、お問い合わせの内容として多かったのは「具体的に、どのような指導者にお願いをしたら良いのか」というものでした。前回のコラムにも記載のとおり、繁忙期については私のキャパシティの関係でどうしても新規のご支援をお受けできないことが多く、本当に心苦しい思いです。やむを得ずに私が直接ご支援ができなかった方々に対して、少しでもお役に立てるのであればと思い、今回は指導者の選定方法などについて簡潔に記載をいたします。2.三つの魔法の質問について本題に入ります。最初に、結論に近い部分から申し上げます。「款項目節(カンコウモクセツ)の詳しい意味を知りたいです」
「〇〇(受験官庁、自治体名)の予算の流用範囲を知りたいです」
「〇〇(受験官庁、自治体名)は枠配分ですか」
上記、三点の質問に対して即座に明確な回答ができない指導者の場合、依頼者様が望むような結果に導くことができる可能性は低いでしょう。これらの問いについては、「公務員試験対策について最低限の知見がある指導者」の場合、100%、適切に回答が可能です。あくまで「公務員試験対策について最低限の知見がある指導者」ということであって、これが回答できるという段階でやっとスタートラインに乗っているだけではありますが、一定の安心材料になります。
当該質問については、ネット上で色々と検索をすれば、それぞれある程度の断片的かつ不確かな情報であればすぐに出てきます。しかし、十分な知見のな
0

公務員試験対策とは ~「人口減少への対応」の捉え方で、受験者の力量は丸裸になる~
1.はじめにこれまで長年に渡り、公務員試験対策のご支援を行ってまいりました。その中で「公務員試験対策の手法(考え方)がそもそも全く分からない」という段階からのお問い合わせを数多くいただきました。これら、私が正式にご支援対応を行う場合は、終始、手取り足取り並走し、最終試験の合格まで導くことが可能なのですが、どうしても当方のキャパシティの関係でご支援をお受けできないことがございます。
皆さまご存じのとおり、一般的な公務員試験のスケジュールとしては、年度当初に国家公務員採用試験(総合職、専門職、一般職)が続き、それと並行して地方公務員採用試験(特別枠、先行枠、特別区、A日程など)が行われます。そして、国家公務員採用試験が一気に落ち着く初夏以降は、一部の国家公務採用試験における経験者枠などを除き、ほぼ全てが地方公務員採用試験となり、B日程、C日程、追加募集、というような形で一年を終えます。
私のご支援実績の割合は、年間を通せば、国家公務員採用試験3割、地方公務員採用試験7割、位に収まるのですが、どうしても年初にまず国家公務員採用試験対策のご依頼が集中するため、地方公務員採用試験として一番早い時期に行われる特別枠等について、ご相談を受けた段階で既に手一杯となっており、お断りせざるを得ないケースが多発してしまいます。
自らの信念として、私が並走させていただくご依頼者様に対して、本気で「全員を最終合格に導く」という強い思いを持ってお仕事をしておりますので、お一人お一人に十分なお時間を割くことができないと判断した場合、その時点で新規受付を休止しております。依頼者様にとって最適なご支援を十分に提
0

面接はネガティブ質問への対応が信頼獲得の鍵
フリー面接トレーナーのnoriさんです。
面接初心者🔰のための面接対策コーナー、略して【めんたいこ】
悩んでいる人も、これから考える人のためにも、今みなさんが向き合っていくことについて書きますよ。
面接では受験者にアピールしてもらうための、「頑張ったこと」などのポジティブな質問は当然ながら用意されていますが、受験者にとって答えにくいネガティブ質問も問われます。
答えにくいことだからこそ、しっかり考えて対応しましょう✨今日の【めんたいこ36】ネガティブ質問ネガティブ質問とは、例えば失敗談、挫折経験をはじめ、退職理由なども該当します。
どれもそうですが、一概にネガティブ質問というわけではないと思います。つまり、人によって捉え方が異なりますので、ある人にとっては大したことがない質問です。
ですが、これらの質問を聞いて不安を感じる方は要注意です。
また、今は不安を感じない人でも、話の内容を深掘りしていくと、うまく話せない人も少なくありません!
そのため、事前にネガティブ質問にどのように対応すべきか考えておきましょう。
なぜネガティブ質問をされるのか?
主に学生さんであれば、ポジティブ質問な質問に対しては、必ず準備されていると思います。
それは、多くの方が多少なりと「盛った」形で話してしまいがちです。
残念ですが、こうしたポジティブ質問だけでは、受験者の本質的な人となりは見えません。
ネガティブ質問は答えにくい一方で、面接官側からすると、その方の困難な状況に陥った時の行動を見ることができます。
仕事とは、楽しい側面がある一方で、つまらないことや、不本意なこと、大変なこと、辛い事など、決し
0
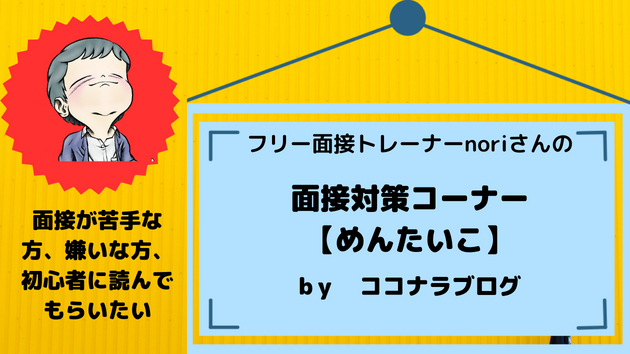
面接官の教科書から学ぶ面接官の視点
フリー面接トレーナーのnoriさんです。
面接初心者🔰のための面接対策コーナー、略して【めんたいこ】
悩んでいる人も、これから考える人のためにも、今みなさんが向き合っていくことについて書きますよ。
今回は面接官の視点に立ったお話です。いつもは、面接を受ける側に立った話が中心ですが、面接官の視点で見た「面接」を考えます。
まずは、書籍を紹介します。
『採用面接100の法則』
株式会社人財研究所 代表取締役社長
曽和利光 著こちらから引用させていただきながら、面接官の視点に立つことで、何を期待されているのかを知り、そこから面接対策に繋げていきましょう。
著者について
著者である曽和氏は、リクルート出身で、採用の世界では第一人者の人事コンサルタントです。学生向けにも著書もありますので、今後紹介していきますね。
今回、曾和氏の著書を引用させていただくのは、採用担当者にとって認知度が高く、曾和氏の考えが参照されていると考えても差し支えないと考えるからです。
面接官の視点
同書から引用させていただくのは66Pの「人となりを見るための四つの観点」です。
こちらから、自分たちがどのような視点で見られているか考えましょう。
一つ目 「一人でコツコツやってきたもの、自己完結したこと(独学の楽器演奏や資格受験)」よりも「チームでやったこと」です。二つ目 「成功したこと」よりは「ピンチの時の経験」です。三つ目 「好きなもの」ではなく、「嫌いなものや苦手なものに取り組んだこと」です。四つ目 「短期間の事柄」よりも「長期間にわたる事柄を聞く」ことです。採用面接100の法則 66P~67P 曽和利光 著
0

一度でも働いたら仕事経験を語れ
面接初心者🔰のための面接対策コーナー、略して【めんたいこ】
悩んでいる人も、これから考える人のためにも、今みなさんが向き合っていくことについて書きますよ☆
今回は、「新卒でどこかに入社するも1~3年目程度で転職する際の面接」について話したいと思います。今日の【めんたいこ29】入社間もない転職者が面接で問われること一度はどこかの会社に入るものの、何かの挫折や思っていた仕事と違った。ということで早期退職・早期転職を希望する方は少なくありません。
いち社会人の先輩としては残念に思う時もありますが、自分自身の人生に決断をしたわけですから、それは応援したいと思います。
そういった方々が、次の転職先を受ける際に陥る面接の落とし穴を整理しておきましょう。
早期転職者の面接落とし穴
これもよく相談を受けるのですが、「ガクチカが無いんです」
「ガクチカはこれでいいですかね?」
「ガクチカまだ使えますかね」おや?💦
「ちょっと待ってください。
君らは既に就職したんですよね??第一に考えることはそこじゃないですよ。」
という流れが私と彼らの間で定番化しつつあります😵
何が伝えたいかと言いますと、まず早期転職者が考えるべきは、その仕事の退職理由と仕事の経験です。
確かに、ガクチカのように、頑張ったことは問われますが、どちらかと言えば、仕事の経験値です。
早期転職者が問われるポイントは・転職理由(退職理由)
・仕事の経験値(何をしてきたか)これらの点についての対策が必要です。
今回はその中でも、仕事の経験値について触れておきます。
短期間での仕事の経験
「少ない期間だから何もないんです。」
と嘆かれる
0

私のガクチカは中学時代に遡ります!?
面接初心者🔰のための面接対策コーナー、略して【めんたいこ】
悩んでいる人も、これから考える人のためにも、今みなさんが向き合っていくことについて書きますよ☆
今日は、ガクチカのネタについて。
みなさんの「頑張った」はいつのころ?
今の頑張りも認めてほしい!
今回はそんなテーマです😊今日の【めんたいこ27】 語れる事が無いと感じる人いつものガクチカがテーマですが、視点を変えて聞いてみます。
「みなさんの学生時代に力を入れたことは?」
といういつもの問いに対して、少なからず抵抗を示す人がいます💦
これは、個々に事情は異なりますが、①学生時代(大学生なら大学入学後から現在)で何かしら活動はあるものの、どの活動にも自信が持てない人
②過去(大学生なら大学入学前まで)の出来事の印象が強すぎて、現在の活動が霞(かす)んで見える人
③本当に何もやってない人以上の3パターンで考えました。
今回取り挙げたいのは、パターン②です。
ちなみに、①と③は共通点があり、「何もやってない」という思い込みや自分に厳しい人が多いように感じます。また、③についても、視点や考え方を変えれば、話せることが見つかることも多々あります。
①と③については、改めて別の機会で話したいと思います。では、②の「過去(大学生なら大学入学前まで)の出来事の印象が強すぎて、現在の活動が霞んで見える人」について考えていいきましょう!
過去の栄光はガクチカで使えるか?
こういったケースはよくあります。
結論から言えば、面接の文脈にもよりますが、やはり現在軸の話が求められています。
ただ、決してダメではないので、うまく過去の栄光も使いこなせ
0

常識を捨てよう!面接はフリースタイル
フリー面接トレーナーのnoriさんです😊
面接初心者🔰のための面接対策コーナー、略して【めんたいこ】
悩んでいる人も、これから考える人のためにも、今みなさんが向き合っていくことについて書きますよ☆今回は面接の常識!?について。
果たして面接に、「これが正解」的な常識はあるの❓
一緒に考えましょう❗今日の【めんたいこ】 面接はこれまでの常識は通用しないこれからの面接対策のなかで、誰かに、「面接ではこの言い方が正解だ!」って指示を受けることがあるかもしれません。
厳密に言えば、面接は答えがない。
これまでの受験やテストとは異次元の世界です💦「異次元」と極端な話をしましたが、例えば、受験では、前日に頭に入れた数学の公式や日本史の年号の語呂合わせも面接室では役に立ちません。
(というより問われません😵💦)
なので、正解・不正解という概念そのものがありません。
例え、自分では「これ、間違ったかも💦」という発言であっても、
案外共感してもらえたり。その逆もまた然り🤭
私は、そういう意味も込めて「面接はフリースタイル」だと考えています。
面接はフリースタイル
私のところに来てくれる、主に学生さん達からこんな声を時々聞きます。M.Uさん 短所についての相談(法人営業希望)
「私の短所は、計画をたてることが苦手で、行き当たりばったりになることだと自覚しているんですが、○○先生から、その短所は面接官の受けが悪いから、『少々心配性』と言った方がいい!」
みなさんはどう思いますか?
M.Uさんにとっては、「心配性」というのは真反対の人物像です。自分の性格とは異なるけど、これで受かるなら・・・
と思いま
0

はじめに「緊張してる?」って聞かれた時のスマートな対応
フリー面接トレーナーのnoriさんです😊
面接初心者🔰のための面接対策コーナー、略して【めんたいこ】
悩んでいる人も、これから考える人のためにも、今みなさんが向き合っていくことについて書きますよ☆
今回は簡単なテーマ&簡単な質問への対応方法について👆
では一緒に頑張りましょう👍今日の【めんたいこ】面接アイスブレイク面接が開始されるとすぐに、
「今日は暑いですが、体調は大丈夫ですか?」
「遠方から来られたんですね。道には迷わなかったですか?」
「緊張されているみたいですね。大丈夫ですか?」
のように問われることが多くあります。
学生さんの相談に乗っていると、
「先生、こういう時なんて答えたら正解ですか?」
なんて質問を受けることもたびたびあります🤔
じゃあ正解は?
ここは正解はありませんよ💦
普段の生活の中でもありそうな質問です。
「今日は暑いですが、体調は大丈夫ですか?」と問われたら、
「はい!この日のためにばっちり体調管理してきました!」
と元気な声が聞きたいのです😊
こうした面接開始早々の質問の流れをアイスブレイクと呼びます。
では、面接アイスブレイクをスマートに対応しましょう。アイスブレイクの目的
面接アイスブレイクには、正解はありませんが、質問の目的はあります。
そもそもアイスブレイクとは、氷を解かす🥶凍り付いた緊張を解すです。
つまり面接時で、応募者の緊張を解して、リラックスした状態で面接に臨んでいただくための、いわば、面接官の配慮です😲💡🌟
面接は相互コミュニケーションが大原則
面接官側がわざわざ緊張を解そうと聞いてくれた質問にも関わらず、間違った理解をしている学生
0

公務員試験チャレンジで陥りやすい罠
フリー面接トレーナーのnoriさんです✨
面接対策コーナー、略して【めんたいこ】始まるよ♪先日岡山のとある大学で、公務員試験希望者を対象にセミナーをさせていただきました😃
「公務員試験にチャレンジする前に知っておいてほしいこと」と題した講義でした。
今回はそんな講義内容のポイントを共有したいと思います。今日の【めんたいこ】心構え、計画をテーマにしたお話です。
タイトルに書いたように公務員試験を始めてチャレンジする方には、「罠」が待ち受けています。
私は常々思いますよ。
公務員試験を受ける方は、本当にチャレンジャーだと。
そんなチャレンジャーなみなさんが、がんばった結果、罠にハマって苦しむ姿を何人も見ています。
大学3年生、高校2年生であれば、まだまだこれからです!まずは要点だけでもおさえておいてください😊
大学のキャリアサポートセンターからご相談いただいた内容
この講義を受けるにあたり、大学側からこんな課題をもらいました。①目的意識を持とう
②仕事をもっと知ろう③人物試験を疎かにしないで④就職活動を全体的に見渡してみようこれは、同大学様だけに限ったことではなく、
多くの学生さんに共通することです💦
学生から見た大人たちは、
確かに余計なお世話が多いかもしれませんし、
同じようなことを言っていると思いますが、やっぱり大事なことなんです😃
一つ一つ考えていきましょう①目的意識を持とう
まず最初に。
「なんで公務員になりたい?」
と考えたことありますか??
もし無いなら、ぜひ考えておきましょう!
この話をしたら、こんな感じで学生さんの声が聞こえます😀学生:これって志望動機?私:そう
0

面接で話し終えた後の「以上です。」って必要??
フリー面接トレーナーのnoriさんです。
面接は人生の岐路を迎えたときにやってくる、嫌な存在です。
そんな面接に自信を持って挑むための
面接対策コーナー、略して【めん・たい・こ】です!😃今日の【めんたいこ】話し方・伝え方
今日も話し方・伝え方をテーマにお話ししますね。
面接の時の話し方って、緊張しっぱなしですよね💦
長く説明してしまって、最後に「以上です。」
なんて話しの締めくくりになっていませんか??
緊張して、なんだか話が終わるたびに
「以上です。」を付け加えているような・・・。
そもそも、話の切れ目をわかりやすくするために、
「以上です。」は言ったほうがいいのでは?と疑問に思うかもしれませんね😊
ということで、
本日はコレいるの?「以上です。」
の付け所解説です🙌
面接はコミュニケーションの場
まず、話し終えた後の「以上です。」は必要かどうかについて。
私の結論としてはあっても良いと思います。
で・す・が
すべての話の終わりに必要ではありません😨
ここで面接の大原則をお伝えします。
面接はコミュニケーションの場です。
コミュニケーションは対話が必要です。
対話は片方だけの話では成り立ちません。
面接では、面接官が応募者のことを知るために、
質問を通して理解を深めていきます。
そういう意味で言えば、
面接は、応募者が話したいことを話す場ではなく、
面接官が聞きたいこと(知りたいこと)について話す
ことが必要です。
(もちろん相互理解の場でもあるので、応募者側が企業を理解する場でもあります。)コミュニケーションの場に「以上です。」は要らない目上の人と話す経験が無い若い方にとっ
0

面接中に「えー」って言ってしまうのはマイナス評価なのか?
こんにちは。フリー面接トレーナーのnoriさんです。
面接初心者🔰のための面接対策コーナー、略して【めんたいこ】
悩んでいる人も、これから考える人のためにも、今みなさんが向き合っていくことについて書きますよ。今日の【めんたいこ5】
話し方・伝え方
えーっと今回は、あのー、面接時の話し方について、えー、そのー、ってなるのが気になる人のための話です!
普段仕事でプレゼンをする人や学校でも発表の機会に、つい言ってしまうことありますよね。ほぼ無意識か、気づいていても直りにくいと思います。特に面接で言ってしまうことを気にされる人も多いようです💦
面接で「えー」を言わないようにするためには、あるいはどんな影響があるか一緒に考えてみましょう。
「えー」の原因
実際に研究したわけではないのですが、私の見解とネット情報をまとめてみると、こんなことが考えられます。
1.話す場の緊張感が高い
2.元々緊張しやすい
3.実は話す内容を決めていない
4.話しと話の「間」を繋ぐために無意識に発する
のようなことが考えられます。1と2は確かにあるでしょうね。面接の場は緊張感が溢れる空間ですから。
3と4も大きな原因だと思います。自信が無い話や即興で話す時は、考えながら話しますので、「えー」と言いながら考える時間を無意識に作り出している可能性はあるかと思います。
面接中の「えー」の影響
あくまで個人的な意見ですが、評価への影響は限りなく少ないと思います。
ホント??😲
ホントです!だって面接官は「えー」の数は数えないですよ。
例えば、仕事内容がプレゼンをするとかアナウンサーだとかすれば、話し方の上手さは見て
0

公務員を目指すための”志望軸”を作ろう
フリー面接トレーナーのnoriさんです。
面接初心者🔰のための面接対策コーナー、略して【めんたいこ】
悩んでいる人も、これから考える人のためにも、今みなさんが向き合っていくことについて書きますよ。
公務員を目指す方、「志望軸」ってありますか?
「安定」でしょうか。
もちろんそれは外せません!
ですが、面接ではそれだけじゃあ勝ち残れない💦
一緒に考えてみましょう!今日の【めんたいこ4】
目的意識、モチベーション
タイトルにあるように今回は公務員希望者を対象に書きますが、その他の就職希望者にも通じまています。
公務員を目指す人が一番最初に考えてほしいことについて書きたいと思います。
一番最初は、筆記試験に向けた対策方法?予備校に通うかどうか?
いいえ、違います。
では、公務員を目指す!!と志している方に質問です
何のために公務員を目指しますか???
「何?いきなり志望動機?」って思われた方ごめんなさいm(__)m
そう一番最初は志望動機です。
志望動機は面接前に考えたらいいんじゃない?
筆記試験が大変なのは十分わかっています。だって大変そうなのは毎年見ていますから💦
それでもあえて志望動機を考えようというのは、面接対策のためではありません!
「じゃあ何?」
それは自分のモチベーションのためです😃
長い公務員試験勉強の中で、一度は、挫折し欠けます。
「何のためにやってたっけ?」
「もう勉強やらんでもえかろー?」
何度このような嘆きを聞いたか💦
公務員になってやりたいことあるの?
何がしたい?って言われても難しいですよね。公安系や国家公務員なら、専門的な仕事なので、ある程度やりたいこ
0

オンライン企業説明会では顔を出すべき?
フリー面接トレーナーのnoriさんです。
面接初心者🔰のための面接対策コーナー、略して【めんたいこ】
悩んでいる人も、これから考える人のためにも、今みなさんが向き合っていくことについて書きますよ。今日の【めん・たい・こ】テーマ
オンライン就活のマナー
タイトルにあるように今回はオンライン企業説明会を舞台にした話をします。早速「面接対策」じゃない!?細かいことはご容赦ください(^^;
無理やりですが、この説明会を疎かにすると、後の面接にも響きますからね。
タイトルに「オンライン企業説明会では顔を出すべき?」とあるように、些細なことですが悩んでませんか?「みんな顔出ししてない。どうしよう??」と心細くなることもありますよね。そんなお悩みの対策を一緒に考えていきましょう!
オンライン就活のメリット
オンライン就活は、2020年の就活以降、一気に全国で主流になりました。説明会やインターンシップ、さらには選考会に至るまで。もはや、一度もオンラインを使わずに内定を得ることは難しいのでは?と思うくらい。
皆さんから見たオンライン就活は、やはり多くの就活生が有効と思っているみたいです。特に、移動時間を気にすることがなくなったため、県外の企業の説明会にも参加しやすいですし、心理的なハードルも低くなったので、気軽に参加できるメリットが大きいですよね^^
これは、採用担当者側から見た意見も同じで、「これまで会えなかった県外学生に会えるようになった」などと前向きにとらえているみたいです。
学生のみなさんは、既に授業でもオンライン授業に出席しているので、もう慣れていますよね。ただ、このオンラ
0

面接の上手な盛り方・下手な盛り方
こんにちは。フリー面接トレーナーのnoriさんです。
前回の「面接で長~い話は何でダメ?」に続き、面接対策コーナー、略して【めんたいこ】を書きますよ。今日の【めん・たい・こ】テーマ
面接中のコミュニケーション
テーマは前回と同じですが、着眼点を変えています。今回は「面接の上手な盛り方・下手な盛り方」について書きます。
面接では、自分をいつも以上に「良い人」としてアピールしたいものです。そのため、応募書類や面接の回答内容を意図的に「盛る」行為は当然のごとく行われています。もちろん嘘はダメですが、ある程度大袈裟に言うことは心情として頷けます(*-ω-)
では、上手に盛ることはできるのか?どのくらいならありなのか?ひとまず、私の考えを聞いてください。
上手な盛り方
結論ですが、嘘の盛り付けは、誰も得しません。詳しく言えば、「盛る」と言うのは、現状の自分に対して、今の自分とは異なる「何か」を付け加えた状態です。
例えるなら、ラーメンにリンゴがトッピングされる感じ。
結果的に不相応であり、自分に似合わない服を着るようなものですね。
なので、逆に言えば無理に盛らなくて良いと思います。ただ、それは、今の「素のまま」の状態じゃあないよ。
何が必要かと言えば、それはやっぱり自己分析なんよね。
これを例えるなら、自分に似合う服を探す感じ。ラーメンには、チャーシューをトッピングする感じ。
盛り方のコツ
何が言いたいかと言うと、自己分析することで、自分を正しく着飾るエピソードや言葉が見つかるってこと。例えば、
「私には継続力があります。飲食店でのアルバイトを3年間、まじめ
0

公務員が出来る副業、出来ない副業
私は、60歳で地方公務員を定年退職後にネット通販で起業しました。 在職中は、まさにインターネット黎明期、いわゆる「インターネット・ビッグバン」の時代で、ヤフーは手作業でホームページを検索サイトに掲載し、グーグルは会社すらまだ有りませんでした。 そんな中で、インターネット上に次々と新しいサービスやネットショップが出来るのを見て、自分もインターネットを使ったビジネスがしたいと本気で思いながらも、公務員なのでネットショップなんか開店したら即クビです。時代が激変するのを日々目撃しながら、どうする事も出来ませんでした。 1999年にMCP資格を取得した頃は、今度はITバブルが絶頂期。プログラマーの年収は1千万円、システム会社に支払う日当計算は「10万円/人日」という飛んでもない時代に突入。40代になっていた私も、公務員をやめて時代の最先端のITの仕事に転職したいと本気で思っていた矢先にITバブルが崩壊。その時は転職をしなくて助かったと思いました。高校時代の同窓生が起業したシステム会社は年商1億円まで行っていながら倒産。妻子を奥さんの実家に帰して一人で暮らしていると言っていました。 世の中のIT化がさらに進む中、私は二度と転職は考えず公務員を全うすると決めた訳ですが、60歳の定年を前にして、定年後も再任用(再雇用)で65歳まで働くか、それとも退職して起業するかを考えた時、65歳から起業しても何もできないと思い退職&起業の道を選びました。ユーチューバーではないですが「やりたい事で生きていく」道を選んだのです。 妻は反対はしなかったものの「出来れば働いて欲しい」と言われましたが、聞こ
0

雑な人には無理。完璧が求められる、公務員という仕事。
タイトルにこう書くと「ホンマかいな?」と突っ込まれそうですが、民間会社は利益追求のために目標を設定し、それをどれだけ達成出来るかが問われるのに対し、公務員という仕事は仕事の結果に80%は有りません。どんな仕事を任されても100%完了しなければクビか左遷ですが、公務員試験は大学受験よりも難関なので、合格した人はそのプレッシャーに負けずどんな仕事でもこなせるのです。 異動は3年から5年毎に有りますが、その度に全然違う仕事に変わります。異動するとまたゼロから新しい仕事を全部覚えます。法律に基づく仕事なので自由に考えてやれる部分は少なそうですが、同じ結果をいかに効率的に完了するかの工夫をしたければいくらでも出来るという創造的な部分も大いに有ります。頭脳労働が得意で、不真面目な人がいないのが公務員の職場です。(真面目過ぎるが故に、仕事で追い詰められて自殺したり、本物のうつ病(怠け病とは違う)になる人もいますが。) 話を地方上級公務員試験に絞って書くと、受験科目は法律や経済はもちろん、高校の全科目の基本問題程度、それに推理力や常識も問われるので、合格した人は公務を100%完了できる能力を備えた優秀な人材ばかりです。 よく勘違いされるのが、上級公務員は大学を出なければなれないと思われがちですが、高卒でも受験可能で、実際に高卒で上級試験に受かった人も同僚にいましたし、私は大卒ですが文学部卒で法律も経済も全部独学で勉強しました。逆に、法学部や経済学部を出ていても、公務員試験用の勉強をしていない人は絶対に合格出来ません。 役所に入ってから驚いたのは、職員のおそらく2~3割は民間企業の経験者だった
0

面接で長~く話すと何でダメなの?
フリー面接トレーナーのnoriさんです。
高校、大学受験に面接がある中高校生や就職試験で面接をする大学生や転職者。
面接は人生の岐路を迎えたときにやってくる、嫌な存在ですよね。そんな面接に自信を持って挑むための面接対策コーナー略して面・対・コ=【めん・たい・こ】です!
最後におまけとして話し方の事例も書きました。参考にしてください^^今日の【めんたいこ】面接中のコミュニケーション
「面接では質問に対して、間違えることなく答える!」のように考えている学生さんは多いですね。特に、高校生をはじめとした、まだ大人たちとの対話の経験が少ない方たちによくみられます。
「言いたいことを言って、自分の考えをわかってもらいたい」との思いもあるかもしれません。
面接指導を受けている方は、おそらく、どの先生(支援者)にも、「今の長いね。もっと簡潔に話そう」みたいに言われた経験があるのでは?
まず始めに伝えておくと、長いのがダメではないんです。
「えっ!?どっち?」と悩みますね(^-^;その辺りが柔軟性や会話力です。
長~い話を指摘される理由
皆さんは、「頑張ったこと」や「志望動機」を一生懸命話したつもりなのに、何でダメなの?っ思いますよね。
そうなんです。一生懸命なのは伝わるんです!だから、絶対にダメという訳ではないんです。
就職指導の先生が指摘する理由はいくつかあります。皆さんの話は十人十色なので、個々に理由は違うでしょうが、以下のようなことが考えられます。
1.話の要点がまとまってないない
2.全ての話をメモできない(記憶もできない)
3.面接時間は決まってる
4.会話(キャッチボール)がしにく
0

出品者ご挨拶
シムネックス合同会社代表の中曽根です。 当社は中国輸入、Amazon直販を主たる事業としていますが、その経験を活かし、これから起業したい人に起業ノウハウを伝授すべく、「ココナラ」に法人として登録しました。 今後、ココナラにおいてIT・DX支援諸事業を展開して行きます。 また元地方上級公務員として公務員試験受験コーチングや、早稲田大学卒業生として早大受験に絞った大学受験コーチングも予定しています。 具体的なサービス設定はこれからですが、どうぞご期待下さい。 (巻頭画像は代表の仕事環境です。商品販促のためのPV制作、楽曲制作も全て自前でやっています。この他に商品撮影のブースも有ります。)【最速で事業を軌道に乗せるために】 商売経験ゼロからの起業は「とても難しい」です。 多くの人が起業後2年以内に挫折する現実を知った上で、その最初の2年を「ワープ」して、いきなり事業を軌道に乗せるには、先ずは商売の何たるかを「座学」で学ぶことが最短かつ最安の方法です。 私がこれから伝授しようとしているのはまさにそれです。(つづく)★このブログが気に入ったら是非ともシェアをお願いします。★当ブログを一部(半分以下)引用する場合は、必ず、当ページURLと「引用元 SIMMNEXブログ」と記載して下さい。記載して頂ければ特段の連絡は不要です
★全文引用は引用ではなく無断複製となりますので禁止します。
★画像の転載はすべて禁止します。
0

【あつまれ看護職採用書類】〚項目だけ集めました〛履歴書・ES・面接カードからリアルに出題|試験対策|入職・転職
『来年受験だし、履歴書の項目を前もって知っておきたいな~』『もう試験まで時間がないけど、面接対策不安だわ・・』『試験対策商品をお試しで買ってみたい』このように感じている方にオススメする有料コンテンツです。今回は、いくつかの地方公共団体(地方自治体)や医療機関の履歴書・エントリーシート・面接カードなどに実際、記載されている項目をExcelで一覧にし、まとめました。その数、15項目以上!「志望動機」や「自己PR」などの一般的な項目だけではありません。購入しないと分からない、リアルな項目が一覧となっています。ぜひ、電子データ(PDF)を手に入れて、試験の不安を取り除きましょう。志望校が決まってから、願書・面接対策をするのでは十分な時間がとれません。実際の項目を確認し、入念に対策を練りましょう。早め早めの試験対策が、周りと差をつけることになります。合格へ近づく選択を、是非なさってください。なお、本商品は買い切り商品となります。
今後、記載項目に変更があった場合でも、
項目が増えることはあっても、減ることはありません。
追加料金は一切かかりませんので、ご安心ください。
購入後も引き続き、商品は閲覧可能となります。
0
1,000円

その志望動機では、公務員試験の面接官は納得しない~志望動機の5つのポイント~
公務員採用試験で、最も重要なのは面接試験と言っても良いでしょう。なぜなら、どんなに筆記試験の成績が良くても、面接試験を突破しなければ、最終合格することはできないからです。せっかく一生懸命に様々な科目の勉強をしてきたのに、その努力を一瞬で無にしてしまうのが、面接試験の怖さです。それほど、面接試験は重要なのです。しかし、残念ながら、その面接試験で最も重要と言っても良い志望動機を、きちんと説明できない受験生は意外に多いのです。志望動機が曖昧であれば、面接官は「実は、第一志望ではないのかもしれない」、「本気で受験していないな」と考えてしまいます。そうすると、合格することは難しくなってしまうでしょう。では、受験生の志望動機に、具体的にどのような問題点があるのか、説明していきましょう。
0
500円

消防士になるには・・・
消防士になるには、「公務員採用試験」に合格することが必須になります。試験と一言で表しても「東京消防庁」「横浜市消防局」「○○地域消防組合」などさまざまです。まず、”消防業務”は地方自治体がそれぞれに担っており、都道府県警察とは大きく異なります。東京消防庁も一部自治体(稲城市と島しょ部)を除き、23区や立川市、多摩市などは”消防業務を委託”しているのです。そして、日本全国どこで消防士を目指しても避けては通れないもの・・・それが、「消防吏員採用試験」となります。(吏員=公務員のこと)合格までの倍率も30倍を超えるところから、1倍のところまでバラバラです。公務員試験はほとんどの消防組織が試験区分ごとに”年1回”行なっています。「大卒区分(一類)」「短大区分(二類)」「高卒区分する(三類)」と東京消防庁のように実施する場合もありますが、多くの自治体では年1回でしょう。つまり、その年の1回で合格を逃すと「1年間の空白」が生まれるのです。それを避けるために多くの受験者は「併願」をします。試験日程が重ならない限り、できるだけ多く受験をしているのです。その中で本命に合格すればそこで消防士に、お試しだったところなら辞退して翌年に再受験などするのが一般的な流れです。公務員予備校の学生などは、警察や自衛隊、海上保安庁など手当たり次第に受験をします。これは本人というより合格実績を必要とする学校側の方針です。さて、もし不合格になり「1年間の受験浪人」が決まると・・・周囲の合格した友人たちが話す「消防学校の生活」などキラキラした話を聞くことになり、それがモチベーションになれば良いですが、1年という時間の長
0

実際にある公務員面接試験での失敗-面接官はこう見る
筆記試験は問題なくクリアできたのに、最後の面接試験で失敗して不合格になる…… そんな受験生は大勢います。人物重視の公務員試験では、筆記試験が良くでも、面接試験ができなければ、合格は困難です。面接が重視される理由は、下記ブログを参照してください。では、実際の面接で、受験生はどのような失敗をしてしまうのでしょうか。また、それに対して面接官はどのように考えるのか。これらについて、説明していきたいと思います。<ケース1>質問に対して、的確に答えられない面接官の質問に対して、的確に答えられない受験生は多いです。具体的には、話しが長くなってしまって要領を得ない、質問に関連することは述べるが結論がはっきりしない、考え込んで黙ってしまうなどです。こうした場合、面接官は「この人は、住民に対して説明できないのでは?」と考えてしまいます。そのような態度では、「早く答えを言ってよ」、「結局、結論は何なの?」と、住民は怒り出してしまうかもしれないからです。<ケース2>入退室の所作や言葉遣いがおかしい面接室に入室する時に、「失礼します」の一言がなく、無言で入ってくる受験生がいます。また、敬語が上手く使えず、面接官にタメ口になったり、自分に尊敬語を使ったりする人もいます。これもNGです。面接官としては、「そんなことは、面接に来る前に確認しておいてよ」という気持ちになります。これでは、公務員になったとしても、基本的な社会人マナーから教えなくてはならず、入庁後に余計な時間がかかってしまいます。<ケース3>人間関係を構築できない学生時代のアルバイト、サークル活動、ゼミ活動などの状況を聞く中で、自分の成果を強く主張
0

公務員試験では、なぜ面接が重視されるのか
最近の公務員試験では、面接が非常に重視されています。しかし、そのことを十分に理解していない受験生は、少なくありません。面接の重要性について、面接を実施する自治体の立場で考えてみましょう。そこには、「公務員に相応しくない人を採用してしまったら、大変だ!」という思いがあります。その理由の1つは、「公務員の生涯賃金は約2~3億円」と言われていることです。自治体にとって職員の採用は、大きな財政負担です。このため、公務員に相応しくない人を採用してしまったら、大きな損失になってしまいます。また、「職員数を増やすことができない」という事情もあります。住民の目もあり、公務員の数を増やすことはできません。このため、同じ職員1人を採用するにあたっても、より良い人を採用したいと思うのです。さらに、内定辞退を避けたいとの思いもあります。面接して良かったので、内定を出したにも関わらず、内定を辞退されることがあります。これは、ある意味では、面接官が見抜けなかったことが原因とも言えます。内定辞退があると、場合によっては、また採用試験を実施しなくてはいけなません。これは、二度手間です。そんなことがないように、面接でしっかり見極めたいのです。このような背景から、近年の公務員試験では、面接が非常に重要視されています。最近では、神奈川県茅ケ崎市や大阪府寝屋川市のように、従来の筆記試験を止めて、面接中心の試験にしている自治体も少なくありません。受験生としては、こうしたことを踏まえて、面接試験に臨むことが必要なのです。
0

良くない面接カードの具体例
皆さんは、面接カードの記入に苦労したことはありませんか。多くの方が、なかなか上手く書けずに悩んでいます。どうにかこうにか、書き上げてみても、面接官の目から見ると、「何が言いたいんだろう?」と首をかしげることも少なくないのです。そこで、良くない面接カードの記入例を、ご紹介したい思います。次のようなものが、典型的なダメな面接カードです。1 都道府県と基礎自治体の役割の違いを認識していない
市役所を志望しているにも関わらず、県庁が行う業務をやりたいと書いているなど。2 自治体が求める人物像などと合っていない
自治体が「様々な主体と連携・協働できる方を求めます」と言っているにも関わらず、それに関する言及がない。また、「協同」と文字を間違ってしまうなど。
3 一文が長過ぎて、意味が伝わらない
「難しい文章が良い文章」と勘違いしてしまい、やたら一文を長くしてしまう。このため、面接官は文章を一度読んだだけでは理解できない。
4 読点がない、文字が小さいなどで、読みにくい 読点(、)を付けるのは良くないと思い、単語を連ねる文章になってしまう。やはり、面接官は読みにくい。5 記入スペース(記入欄)に対して分量(文字数)が適切でない
小さな記入スペース(記入欄)にも関わらず、小さな文字でびっしり書いている。反対に、ある程度のスペースがあるのに、文字数が少ない。
6 同じ内容を何回も書いている
複数の質問項目に、同じ内容を書いている。このため、面接官には受験生の人物像がよくわからない。
このような面接カードでは、さすがに高得点を得ることは難しく、結果的に不合格になってしまうことがあるのです
0

分数と比を使いこなそう! ― その2
前の記事の続きとなります。前の記事はこちらです。2つの部門の売上を考えております。再度、問題を挙げておきましょう。コチラです。問題:
ある会社には、A、Bの2つの部門がそれぞれ販売業務を行なっている。2つの部門の売上げについて、先月に比べて今月は、Aは15%の増加、Bは4%の減少となった結果、今月の売り上げが260万円だった。このとき、今月の 部門A の売上金額はいくらか。前回は、中学校以来つづけてきた「文字式」の解き方を考えました。それも悪くはありませんが、どうしても分数がゴミゴミしがちで、ミスも出やすくなっております。それで、次の方法でやってみるのはどうでしょうか?次は、「比」と「分数」を使いこなして!
何事も、こだわりを捨てることは時に必要! 今までの常識を少し外して、自由をGETしましょう。
まずは、様子見と作戦から!ん~、今のところ、分数はなしですみました。コツは、「100とおく」こと。ストレスが減ります。その代わり、同じ値ではないことを示すため、「○の100」と「□の100」に分けておきます。では、続き・・・いかがですか??もしかしたら、こんな方法は考えたことはないかもしれませんが、ストレスは少なめです。ただし、いくらか「技」があります。1つは、割り算を排除してかけ算に徹することです。最後の「○の115」を求めるところでは「5/7で割る」のではなく、「5/7がいくつ入るか」を「かけ算」で考えています。「7をかけて分母を消す」&「23をかけて分子を115にする」ぜひ、このような技を持っておきましょう。もう一つは、出てしまった分数を許容することです。「①」が分かればいい
0

分数と比を使いこなそう! ― その1
割合の問題は、公務員試験に付き物です。「人数が35%増えた」とか「3割引きで売る」というような割合の問題を、どのように解いていますか?
真っ先に思いつくのは 文字式 かもしれません。「分からないものを文字式でおく」という中学校からの方法は、問題を解くのにとても効果的です。しかし、どんな方法にもメリットとデメリットがあるもので、文字式にも弱みもあります。それは、割合の問題で文字式を使うと、確実に分数がゴミゴミすることです。
ここで、公務員試験で役立つ2つの数学的アイディアをシェアしたいと思います。それは、「比」と「分数」です。これらを使いこなせると、余分な分数や筆算から解放されることがあります。例を挙げましょう。
問題:
ある会社には、A、Bの2つの部門がそれぞれ販売業務を行なっている。2つの部門の売上げについて、先月に比べて今月は、Aは15%の増加、Bは4%の減少となった結果、今月の売り上げが260万円だった。このとき、今月の 部門A の売上金額はいくらか。
まずは「何かを文字式におかなきゃ」と感じるかもしれません。
ぜひ解いてみてください!では、失敗を交えながら、一緒に解いて学んでみましょう。まずは、文字式で・・・先月の売上を「4%増」するので、経験的には、先月の売上をA円、B円とおいた方が解きやすいです!さて、行き詰まってしまいました。原因は何でしょうか?もちろん、このままゴリ押すこともできますが、でも!少し立ち止まって考えてみましょう。いま質問されているのは何でしょうか?それは、「今月の 部門A の売上」です。つまり、「B=・・・」にするよりも、「A=・・・」にした方が効
0

【勉強法】独学で公務員試験に合格した問題集の使い方すべて晒します
独学で公務員試験に合格した!しんたろすです('ω')ノ
今回は私が公務員試験に合格した際に実際に行った勉強法について、具体的なプロセスを辿りながら画像付で解説していきたいと思います。
✔公務員試験の受験を考えているor受験予定である✔独学における勉強法に悩んでいる✔実際に合格した勉強法を知りたい!!
という方は、ぜひ本記事をチェックしてみて下さいね。独学で公務員試験の勉強法に悩んでいる方はもちろんのこと、これから公務員を目指す方についても、気軽にお読みいただければと思います。本記事が皆様の公務員試験勉強法を構築するうえで参考になれば幸いです。ボリューム満点で公開していきます!それではいってみよう!!
私が使用した問題集はコレだ!!
私が公務員試験を受験するうえで使用した問題集は「スーパー過去問ゼミ(通称:スー過去)」です。正確に言うと、全てスー過去というわけではないですが、ほぼほぼスー過去とでも言いましょうか。
今回はこのスー過去を例に挙げ、どのようなプロセスで問題集を攻略していったのかを整理・解説していきますが、この手法はその他の問題集(LECの「過去問解きまくり」etc…)にも応用可能な使い方になりますので、問題集の使い方にお悩み中の方は是非参考にしていただきたいと思います('ω')【知識ゼロ】正文化による超高速化勉強法
公務員試験で定番?とも言われる手法「正文化」
解説見る⇒誤文を見え消し⇒余白に正しい文を書く
これについては賛否両論ありますが(問題集が汚くなる、答えが見えるので考える力が付かないetc...)、実際に私はこの「正文化」による手法で合格することができたのも
0
500円

公務員試験対策で「数的判断」が伸び悩む場合
公務員試験に向けた勉強 本当にお疲れさまです。今回の記事では、「数的判断」の点数が伸び悩む理由についての考察をシェアしたいと思います。今回取り上げたい課題は、「分かる」から「解ける」へのステップアップと解答スピードの感覚の欠如です。勉強の際にまず気になるのは、恐らく、 なぜ?どうして? どういう理論で?というところだと思います。しかし、それを理解して「だからか~」で終わってしまうと、「分かる」止まりになってしまいます。その後、「解ける」までのステップアップができていますか?「解ける」のレベルまで行くためには、同じ問題を2回、3回と解く必要があります。だからこそ、多くの問題集には「○月○日」と、取り組んだ日付を書く欄が設けられています。「お勉強」ではなく「仕事」として取り組みましょうもしも、点数や速度が伸び悩んでいるとしたら、小中高校、大学の「お勉強」のイメージで取り組んでしまい、それが邪魔になっている可能性があります。数的判断を「面倒くさいけど、仕事」と考えましょう。「自分で解けてなんぼ」の作業です。でも、計画があって、順番があって、作戦があるから、作業ではなく、仕事です。例えば、オムライスをつくる職人さん。どうやって卵を丸めるのか、手順をテレビで見て評論するなら、偉そうなお客さんで十分…。しかし、仕事人の意義は、それが「できるようになる」ところにあります。3分で解けた!5分でなら解けた!3分で解くってこんなスピード感か!こんなことを感じながら練習できていれば伸びると思います。問題集を山ほどこなす必要はありません。核となるような問題を繰り返し、時間内に終わらせる 仕事力を持つこ
0

オリンピックにちなんで 簡単そうで難しい推理問題
今回は、簡単そうで難しい推理問題をご紹介いたします!実際に公務員試験で出題された問題です。いつも思いますが、公務員試験の数的判断の問題を作っている人って、すごいですね…もちろん、条件をいくつ与えておくとか、型があることは分かるのですが…でも、解く方も真剣ですよ!意外と、「大学の工学部です」と理系を豪語する人でも すぐには解けない のが数的判断。しかし、「文系で数学は苦手です」という人が ひょいっと 解いてしまうのも数的判断。こう聞くと、理系科目の得意な人が不利のような気がしますが、本来はそうではないはずです。では力試し!ではさっそく、オリンピックにちなんだ この問題、いかがですか??【問題】A、B、Cの3か国がオリンピックで獲得したメダルについて、次のことが分かっているとき、1~5の中で、確実にいえるのはどれか。● 3か国が獲得したメダルの数の合計は、金メダルが3個、銀メダルが3個、銅メダルが4個だった。● 3か国が獲得したメダルの数は、A国が3個、B国が3個、C国が4個だった。● 銅メダルは、どの国も獲得した。● 銀メダルを獲得した国は、金メダルも獲得した。1 A国は、3種類のメダルを獲得した。2 A国が獲得した銀メダルの数は、1個であった。3 B国は、3種類のメダルを獲得した。4 B国が獲得した金メダルは1個だった。5 C国が獲得した銅メダルは1個だった。さて、ぜひ解いてみてください。いや~、意外と・・・ですよね。そう、表で、ここまでは書けるんです。ただ、その後、詰められそうで詰まらない・・・かぎの一つは、直感そうです、悪くはありません。C国の銅が「2個」で、あとは全部「1
0

公務員試験 数的判断の勉強方法
はじめまして。公務員試験講座で数的判断と自然科学の講師をしております shigumakaitack と申します。これからの時代、ネットを使った学習がますます大切になっていきそうですね。皆さまのお役に立てればと思い、情報を発信させていただいております。ぜひ一緒に学んでみませんか?私がご提供させていただいている講座では、音がなく、集中して見ることができる動画を中心に、「解ける感覚」を身につけることを目標にしております。公務員試験の数的判断について公務員試験では、短時間で流れに乗ることが大切です。つまり、~ということだったら、こっちのタイプになるはずといった、「推理」を繰り返していきます。その速さが解答時間の短縮につながります。思考力が大切なのは言うまでもありませんが、慣れが大切ともいえます。では、どうやって勉強するか??私の答えとしては、問題が解けている人の様子を眺めることその後で、同じことができるように練習していくこれが早道かな・・・と、思っています。よくある勉強方法と比べてみましょう。① 参考書で勉強する試しに、数的判断の参考書を見てみてください。参考書で勉強しようとすると、どうなりますか?場合によっては、長~~い文章の解説をまず読解する必要がある・・・確かに、長文解釈の練習にはなるかもしれませんが、 読解 → 理解にかなりの時間がかかってしまいます。「なんでかな?」と疑問が生じたら、かかる時間はさらに2倍、3倍に・・・労力もかかり、たいへん疲れてしまい、あきらめそうになったことはありませんか?② 授業を受ける、動画を見る方法論としては間違っていないと思います。ただ、数的判断だ
0

mol(モル)でお困りのあなたに、動く参考書を!
はじめまして。理系の講師をしている shigumakaitack と申します。世の中には、どうしても乗り越えがたい壁があるものです。化学の「mol(モル)」計算は、その一つです。大学受験、公務員試験、各種の資格試験で、「mol(モル)」計算をさせられることは珍しくありません。たいていの参考書は、分かった人向けかのように数式や計算を並べて「解説」としますが、意味が分からないということはありませんか?このページの目的をまとめました。次の動画をぜひご覧ください!皆さまのお役に立ちたいと思い、単発の授業をご用意いたしました。モルを理解してクリアするため、このブログに9つの動画を準備いたしました。合計でおよそ50分です。集中して学んでいただけるよう 音なし の動画 となっています。参考書を読むようにして一つずつ見ていってください。扱っている範囲は以下のとおりです。● mol(モル)の意味● 化学反応式の係数合わせ● 原子量と分子量● 気体の標準状態● 絶対温度● ボイル・シャルルの法則● 気体の状態方程式どうして mol が導入されたのか、いったい何を数えるのか、グラム(g)やリットル(L)とどういう関係があるのか、など、かゆいところにきっと手が届くと思います。この動画を見た後に問題集に目を移せば、分かるようになると思います。ご質問がありましたら、こちらまでぜひお寄せください。▼動画に関する質問は、上記サービスのメッセージにて承ります。では、ここからは 肝心の単発授業 合計で およそ50分です。
0
2,000円

地方公務員化学職【1】筆記試験対策の始め方
こんにちは。
ようやく涼しくなってきて、過ごしやすい季節になってきましたね。
新しく何かを始めよう!と思えるような気分になります。
来年度の化学職受験をする方は、この時期のこの気分でスタートを切れたら良いですね。
さて、今回は公務員試験対策としてまず取り掛かる「筆記」の対策の始め方について書いていきます。専門と教養の試験対策の流れと、実際に私が使用した問題集や対策本の一部を記載します。専門&教養対策は何からはじめる?
【専門試験】まず、専門試験については「大学で化学をどの程度専攻していたか」で流れが変わると思います。ここでは、私と同様に「大学で化学系学科の授業を一通り受けた」という方を想定して勉強の始め方を紹介します。この場合、基礎を一から勉強しないと問題に取り組めないわけではないので、
実務教育出版の「技術系 新スーパー過去問ゼミ 化学」から解き始めることをオススメします(以下新スー過去)。これは化学職受験者で最もポピュラーな対策本だと思います。
内容のレベルは国家一般職や地方上級試験(県庁、政令市)からの出題でちょうど良く、頻出問題を多く掲載しているので、ここから始めて間違いはないと思います。技術系 新スーパー過去問ゼミ 化学作者: 資格試験研究会
出版社/メーカー: 実務教育出版
発売日: 2020/09/02ただし、私は何も考えずに第一章の第一問目から解き始め、たまたま苦手な問題にぶつかったため、即諦めることになりました笑。皆さんは、ご自分の「得意または好きな分野」から解き始めましょう。もし、化学系の学生なんだけど「化学全般苦手、、」と思っても、この本の中には「こんなに
0

公務員試験対策(裏道メソッド)
公務員試験対策は進んでいますか?
受験が今年で何度目かという人もいるでしょうか。
「過去問を繰り返しても、なかなか受からない。」
「1次試験が通っても、2次試験でいつも落ちてしまう。」
「努力はしているのになぜ受からないのか。」
「周りの同級生や、年下の子がどんどん受かっていくのに、なんで自分
は・・・。」と。
心が疲弊していきますよね。
「何年か受験しているがなかなか受からない」という方は、もしかしたら、王道法では受験勉強がうまくいっていないのかもしれません。
また、初めて受験するとい方でも、「コツコツ過去問をやっていてもなんか不安だな」と思っている人もいるかもしれません。
私が市町村の公務員試験と県の教員採用試験に合格した際の勉強法の内、少し特殊だったかなという方法をお伝えしたいと思います。あくまで、王道な勉強をした上での+αになりますので、「楽して受かる」という内容ではありません。ただ、「このままの勉強法でいっても不安だな」という方は、この文章で少しでも勇気がもてたらなと思って書きました。
0
500円

公務員試験のノウハウ提供
本業で公務員試験のサポートをして早20年。そのノウハウを活かしてココナラでサービス提供して2年弱が経ち、100件以上のサービスの新規購入、リピート購入をいただきました。まずは感謝致します。ありがとうございます!しかし実際、サービスを提供する上でESや小論文をはじめとして文章をまとめる、言語化が苦手な人が多数いることを再認識しました。公務員の仕事だけではないですがビジネスでコミュニケーション能力は今後とても大事になります。自分はコミュニケーションが苦手だからデスクワークやオフィスワーク、さらに安定しているから公務員という選択だけでは厳しいと言えます。口頭で伝えるには確かに訓練が必要であり、すぐには上手くはなれないと思います。まずはESや小論文で文章や言語からうまくなってみませんか?まずはESや小論文のノウハウを少しずつではありますが提供(一部有料)していきたいと思います!
0

試験問題作成経験者からのアドバイス
公務員としての体験談を昨日まで書きてきましたが、
いかがだったでしょうか。
しんどそうだな、と思った方もあれば
早くやってみたい、と思った方もあったでしょう。
あなたはどう感じましたか?
ここまで読んでいただいたあなたは、
公務員試験や公務員として待っている世界について
ある程度理解していただいたので、
ブログのタイトルにある通り、
私が専門試験問題の作成を経験した立場から
公務員を目指すあなたのために、
試験合格の「コツ」をアドバイスします。
その前に、専門試験問題どうやって作成するのか、
簡単に解説しましょう。
問題作成を担当する関係課から分野別に1~2名選出され、
人事委員会から作成委員として任命(兼務)されます。
その後、週に1回程度打合せをしながら問題を作成していきます。
作成の注意点として
・過去5年間に出題された問題(類似も含む)はNG
・出題分野が偏らないように担当を決める
このルールに従って、担当毎に原案を作成し、
打合せ会で作成委員全員で議論しながら問題を精査し、
何度かそれを繰り返して問題が出来上がります。
通常業務もこなしながらの問題作成で、
図書館に行ったりして参考書や問題集を読んだりするので、
結構大変でしたよ。
あと、試験終了後に受験者の採点も行いました。
採点基準を問題作成時に決めるので、それに従って採点するわけですから、
出題側の意図するところを理解できれば得点できます。
試験不合格者から採点基準等を情報公開請求されることがあるので、
そうなった場合の説明を意識しながら、採点基準をつくります。
これもなかなか大変です。
ここまで読んで、
どうす
0

思い出に残る体験談(その2)
前回に引き続き、思い出に残る体験談を書いていくようにします。
西日本の空の玄関口、関西国際空港。
コロナ前までは、インバウンドのおかげで利用者は右肩上がり。
飛行機の発着回数が開港当時に想定していた回数を超えるかもしれない、これは大変だな、そんな話を関係者と話をしていました。
ところが2020年は利用者が激減、コロナの影響で仕方ないとはいえ、空港のロビーは閑古鳥がないていました。
JALやANAは国の基幹産業を支える会社なので、
赤字でも国が支援し、倒産することはありませんが、
人々の移動を支える交通関係の会社は、当面厳しい状態が続くと思います。
コロナに負けず、頑張って下さいね。
関西国際空港が開港したのは、私が公務員になる1年前の平成6年。
開港後、すぐに2期島建設の工事が始まり、
大阪と和歌山の県境にある岬町から埋め立て土砂をタンカーで運び、
2期島を埋め立てる工事が始まりました。
埋立工事は無事に終わり、タンカーに土砂を詰め込む搬出基地をどうするか、
関係者で様々な議論が行われました。
最終的には、大阪とは思えない美しい海を皆さんに知ってもらい、
そこで釣りを楽しんでもらおうとなり、
土砂搬出基地を「海釣り公園」としてリニューアルすることになりました。
ただ、交通不便地であるため、移動を車に頼るしかありませんでした。
海釣り公園に来てもらうためには駐車場が必要不可欠、
そこで国の補助がもらえるよう「道の駅」を海釣り公園に併設することで、
自治体の負担を減らそう、とのコンセプトに決まりました。
私は「道の駅」建設の担当者として、
平成19~20年の2年間、片道約2時間かけ
0

思い出に残る体験談(その1)
前回は市役所出向時の体験談について、
意思決定というテーマで記述しました。
意思決定に時間がかかるところが公務員のメリットであり、
デメリットでもあるという事をご理解いただけたかと思います。
今回は私の公務員生活の中で、
特に思い出深い体験談を書いていきます。
平成9年だったと思いますが、
大阪北部に位置する能勢町の清掃工場から多量のダイオキシンが発生し、
作業員の方がダイオキシンの被爆が原因で亡くなられ、
遺族の方が裁判を起こしました。
この頃は、米を刈り取った後の藁を野焼きすることが当たり前で、
焼却に対する環境意識が低い時代でした。
裁判陳述用に遺族の方が作成した原稿を読みましたが、
とても生々しい内容で、読みながら涙がこぼれました。
被害者の方は、ダイオキシンまみれのゴミの中で
ゴミを掻き出したり、炉を清掃したり等されていたので、
分かりやすくいえば放射能を浴びながら
長年仕事をされていたのと同じ状態だったのです。
鈍感な私でもこれはひどいなあ、
何とかしなければ、と使命感が湧いてきたことをよく覚えています。
この能勢町のダイオキシン被爆事件が発生してから、
国が対策に本腰を入れ、
ゴミを焼却する炉の基準を見直し、
有害物質を除去する「バグフィルター」の設置が義務付けられました。
バグフィルターを設置すると効果は抜群で、
焼却炉内のごみの燃焼技術にもよりますが、
従来発生していたダイオキシンを99%以上除去できることが判明、
どこの自治体も導入に前向きになりました。
補足すると、家庭で排出するゴミ(一般廃棄物と言います)の処理は
市町村の責務であると廃棄物処理法に定めら
0

公務員のメリデメ(その4)
前回、意思決定について書きましたが
基本的には、自治体の意思決定は民間に比べて遅いです。
でもそれがメリットであり、デメリットでもあるのです。
個人の考えによるのではなく、法律や条令に従って、
多くの職員で議論し政策を決めていく。
時間をかけた分、案が醸成されて、より良い政策ができあがる。
携わった者にしか得られない充実感です。
努力して結果が得られれば、誰でも嬉しいですよね、
特にその努力が大きければ大きいほど、得られる結果も大きい。
公務員の仕事でも一緒ですね。
あなたにも是非この気持ちを味わって欲しいと思います。
意思決定に時間がかかるのは、都道府県や政令指定都市に多いです。
扱う業務量が多く、職員数も多いため、
意思決定までに予想以上の時間がかかることが多々あります。
逆に人口規模の小さな市町村だと、
予算規模も小さく、職員数も少ないので、意外と意思決定が早い。
ただ、規模が小さいため、ワンマン体制になりやすく、
古い体質が変わらず、改革がなかなか進まない欠点があります。
私は都道府県(地方上級)職員でしたが、
人口規模約5万人の小さな市役所に出向する機会をもらいました。
市職員をサポートするスタッフ職で、
いくつかある懸案事項を、知恵を出しながら解決していく役割でした。
一番ビックリしたのが、内線電話で市長・副市長から呼び出される事。
知事から内線電話で呼び出される職員はごく限られた方だけで、
そんな経験がなかったため、最初は本当にビックリでした。
呼び出しの電話のトーンで、
今日は機嫌悪いなあ、まだましだなあとか分かるようになりました。
意思決定すべき案件があれば、
0

公務員のメリデメ(その3)
公務員のメリット・デメリット、3回目は
意思決定
というテーマで書いていきたいと思います。
意思決定って何?
大学生とか若い方ならこう思うかもしれません。
例えば標準的な4名家族(父・母・子供2名)ならば、
マイホームを購入するとか、受験する大学を決めるときなど
普通は家族で話し合いをしますよね。
家族で「意思決定」して物事を決めている例になります。
家庭のことならお父さんが決定権を持っているか、
いやお母さんが持っているよ、という家庭もあるでしょう。
公務員の仕事で、何かの政策や施策を決める際、
個人の思いだけでは決定できず、
上司の判断を仰いで決定していきます。
それが課長なのか、部長なのか、はたまた市長なのか、
それは内容によって変わります。
時々聞くことばですが、上司の「決裁」を取って意思決定していきます。
「事務分掌」という聞きなれないものが作成されており、
この内容ならば部長決裁、
1億円以上の支出に関わることは市長決裁・・・
というように規定で定められた立場の方が決裁し、業務を進めていきます。
本来だとトップである知事や市長が全てに関わっていくのが理想ですが、
それでは時間がかかりすぎるため、
権限を分散して、効率よく公務が執行できる体制が構築されています。
最初に配属されると、この案件は誰に決裁を取ればよいのか、
右も左もわからないのでそこから教えてもらわねばなりません。
でも1年くらいやっていくと、だんだん感覚がつかめてくるので、
そんなに心配はいりませんよ、大丈夫です。
ざっと書きましたが、一個人の判断で業務を進めるのではなく、
仕事内容に応じて決裁を取り、
0

公務員のメリデメ(その2)
公務員のメリット・デメリットとして、
人事異動
について書いていくようにします。
自治体の規模や職種にもよりますが、
新規採用されて配属された部署から3年~5年くらいで
別の部署に異動するのが通例です。
過去には、労働組合の幹部が組合活動しやすい部署に所属して、
全然異動しないという事がありましたが、
今はそのような事はほとんどないと思います。
人事異動があるおかげで、
話が合わない上司であっても我慢できますし、
辛い仕事でも何とか頑張れることができます。
それは、何年かすれば異動できることが分かっているからです。
最近では人事評価制度が変わり、
自分の能力や特技を活かせる部署への異動を希望することができたり、
家庭の事情で役職を外してもらうこともできたりします。
育児休暇等も取得できますし、
民間企業に比べれば恵まれた職場が公務員です。
私も息子(2人目の子供)が生まれた時は、育児休暇を取得し、
娘を幼稚園に送迎したり、弁当をつくったりなど
大変思い出深かったので、今でもその時のことをよく覚えています。
では、人事異動は公務員のメリットなのか、と言えば、
そうでなくデメリットの部分もあります。
異動するという事は、
職場も変わるし、仕事内容も変わり、上司や部下も変わります。
つまり、適応能力がないとやっていけません。
私の場合で言うと、
大阪市内に住んでいて、大阪市内の職場で働き、
環境やリサイクルに関する仕事に携わっていました。
ところが、辞令を受けて、
大阪市内に住んだまま、大阪南部の職場(和歌山との県境近く)で
働くようになり、工事発注や地元交渉を担当するようになりまし
0

公務員のメリデメ(その1)
前回までで、公務員になるために受験しなければならない3つの試験
・教養試験
・専門試験
・人物試験(面接)
について概要を書いてきました。
大体のイメージはつかめたでしょうか。
簡単ではないですね。
民間企業の試験もそれなりに大変ですが、
試験のボリュームと対策に必要な時間を考えると、
その大変さが理解できるのではないでしょうか。
そうは言っても、合格への道筋は示されているので、
コツコツ頑張るのみです。
私もサポートするので、
困った事などあれば、遠慮なく申し出て下さいね。
今回からは、あなたが試験に合格した後に待ち受ける公務員の世界について
メリット・デメリットを中心に書いていきます。
1回目なので、まずはメリットから。
よく言われる事ですが、
1番の大きなメリットは給料が安定して支給されること、でしょうか。
長年勤務していると当たり前の事なのですが、
コロナで職を失い、
生きるだけで大変な苦労をされている方の話を聞くと
毎月給料をもらえるのは当たり前ではない、と知らされます。
それと福利厚生関係も安定していますので、
医療保険や年金に関しても心配ないでしょう。
特に私の親の世代(20代の若い方なら祖父母の世代に該当するでしょう)であれば、役所勤めにステータスを感じる世代なので、公務員になることで、これまで育ててもらった恩返しができます。普段からお世話になっているなら、
恩返しするぞ、とモチベーションを高めて勉強するのもアリです。
私自身で言うと、自分の勤務地で「貢献」したかったので、
税金を使わせてもらう代わりに、しっかりサービス提供して恩返しする。
そのような気持ちを忘
0

在学中にやっておくべきこと(その2)
在学中にやっておくべき事、
当たり前のことなんですが、
本を読む
という事なんです。
意外かもしれませんが、間違いなくあなたの大きな財産になります。年収の高い方々がやっていることも「読書」なんですね。
少なくとも毎週1冊は読んでいるというデータがあります。
ネットやスマホをいじっている時間を少し削れば、
これは簡単にできることです。
仮にあなたが進路変更となり、公務員にならなかったとしても
全く損はありません。逆に「無形の財産」を築けますよ。
是非とも実践して欲しいと思います。
読書以外で何をしておけばいいかと言うと、
卒業してからあまり時間が経過していない先輩(卒業後5年以内が目安)の
職場体験談を聞いてみることをお勧めします。
これは民間企業でも同じことですね。聞いた方が絶対にいいです。
あなたの周囲にそのような先輩がいなければ、
ゼミに配属されてから同期や先輩、大学院生に聞いてみてもいいでしょう。
連絡先を教えてくれるかもしれませんし、
ZOOM等を使ったwebセミナー等を開催してくれる可能性もあります。
あなたが所属する学部・学科から公務員になっている先輩が多ければ、
公務員を目指すに相応しい学部・学科でしょうし、
専門試験の過去問や各種データも残っているはずです。
これが逆に少ないなら、進路を再考してみてもいいでしょう。
私の場合も、当時のゼミ生の3割くらいは公務員を目指していたので、
情報という点に関してはあまり苦労がなかったです。
地元の市役所や県庁に勤務している先輩方の話も聞くことができたので、
その点は非常に恵まれていたと思います。
またあなたの所属する学部・
0

在学中にやっておくべきこと(その1)
前回までで試験の内容を一通り説明しました。
3種類もあり、結構なボリュームですよね。
・教養試験
・専門試験
・人物試験(エントリーシート・面接)
試験を受験しようと考えている人で、一番多いのは大学生だと思います。
高校生や社会人の方もありますが、
公務員試験に向けて大学在学中に何をすべきか、少し書くようにします。
すでに本ブログにアップしている内容ですが、
「公務員としての基本を身につける(その1~4)」
を読み返していただけると有難いです。
<在学中にやっておくべきポイント>
・整理のスキルを身につける
・バランス感覚を身につける
・光を放つ存在になる
・執着から離れる
これができれば、間違いなく素晴らしい「人格者」になれます。
公務に携わる時に大きな財産になります。
ただ、実際はなかなか難しいでしょう。
私の個別相談を希望する方には、みっちり教えますよ!
アルバイトをしたり、クラブ活動や趣味に時間を使ったり等、
普段の勉強以外でも学生時代にやりたい事があるでしょう。
それも大いにやって欲しいし、
その時間を削ってまで勉強する必要はありません。
当面の目標として、
毎週1冊(月に4冊)以上本を読んで下さい!
ジャンルは何でもいいです。
あなたの関心のある本で構いません。
年収1,500万円(概ね月収100万円)以上稼いでいる方の多くが
月に4冊以上本を読んでいるというデータがあります。
年収1,500万円というのは、
市長・副市長の年収、あるいは政令指定都市の局長級職員の年収に
匹敵する額で、公務員トップの年収です。
キャリア官僚で事務次官クラスになると、もっと多いですけど
0

人物試験(面接)対策について
教養試験・専門試験の概要を見てきましたので、
次に人物試験(エントリーシート・面接)について見ていきましょう。
一点注意ですが、
人物試験は筆記試験の合格者のみに課せられる試験ですので、
残念ながら人物試験の経験をすることなく
公務員試験が終わってしまう方もいるかもしれません。
ですので、筆記試験の勉強に集中することが最も大切ですが、
かと言って人物試験もおろそかにできませんので、
筆記勉強を進めながら、こちらの準備も進めていくようにしましょう。
人物試験の目的ですが、
「ウチの自治体にふさわしい人物か」
を確認するためです。「ウチ」というのは、あなたが受験する自治体のことです。
筆記試験に合格しているので、基本的な学力があることは既に認められています。あとは、公務に携わった時に、その能力を十分に発揮し、納税者のために貢献できるか、
そこが確認する重要なポイントです。
自治体にもよりますが、
面接内容はマニュアル化されている場合が多いです。
中には模範解答も示されている事があります。
公務員には定期異動という制度があり、
自治体の規模等にもよりますが、
ある程度の年数が経過すると配属部署が変わることになります。
ゴミ収集や道路管理等の特殊な仕事は別にして、
10年以上同じ部署で働くというのは非常に稀なケースです。
ですので、面接担当官も人事異動で変わる場合が多く、
異動してきた職員でも理解できるようなマニュアルを作成しておくのです。
面接で得たい情報としては、
・あなたの人物像
・受験している自治体の主旨(政策目標や理念)を理解しているか
になります。端的にそつなく矛盾なく説明
0

オンライン講座の活用
前回は予備校に通うべきか、という話をしました。ポイントになるのは「勉強時間の確保」
予備校や専門学校に通えば、集中して勉強できる時間が確保できます。
しかし、新型コロナウィルスの影響があり、予備校に通うのも一苦労ですね。私には大学生の娘がいますが、ほとんどがオンライン授業。
何のために大学に通っているのか、よくわからないですよね。
折角、高額の費用を払って予備校に行こうと思っても、
新型コロナウィルスの感染が収束しないと無駄になる可能性があります。
私が勉強した頃はパソコンも普及しておらず、
予備校に通うか、独学で勉強するかの二択でしたが、
通信環境が整備された現代では
「オンライン講座」
で好きな場所・好きな時間に勉強できるようになりました。
独学で勉強するより費用はかかりますが、あなたの勉強のペースメーカーになってくれる事は間違いありません。
公務員試験のオンライン講座、ネット検索で探してみましたが、
スタディング(studying)の講座がいいなあと思いました。
スマホからでもアクセスできるので、移動時間等も有効に活用できます。無料で登録してみましたが、
無料動画や特典も充実しているので、あなたも一度登録してみて下さい。
得られるものはかなり多いです。「スタディング」はあくまで一例ですが、
他の会社でもよい内容のオンライン講座が色々とあります。
私のおすすめ勉強法は、オンライン講座の活用です。
費用対効果も高いですし、コロナ禍でも全く影響ありません。
自己管理能力が高く、モチベーションの持続もできるよ、
という方ならば「独学」で勉強してもいいです。
ただ、そういう方はなか
0

予備校(専門学校)に通うべきか
前回までで、試験対策の内容については概ね書き終わりました。
今回からはどのように勉強していけばよいか、
勉強方法(手段)について記載していこうと思います。
公務員を目指す方から、予備校(専門学校)に行った方がよいでしょうか。
とよく聞かれるのですが、
私自身は過去問を中心に「独学」で勉強しました。
大学には自宅から通っていましたので、
電車での移動時間を活用したり、
授業のスキマに図書館に行って勉強したり等、
ムダな時間を減らして時間を有効に活用することを心掛けました。
それでも合格できるわけですから、
予備校に行かなければ合格できない、というレベルの試験ではありません。
過去問の研究と実践が最重要であるので、
それをしっかりやっていけば、誰でも合格できるのが公務員試験です。
個人的な見解になりますが、
考えなければならないのは「勉強時間をいかに確保するか」です。
勉強時間を確保するための一つの方策が予備校や専門学校に行くことであり、
通信教育やオンライン講座を受講するのも同様です。
性格も違うし、置かれている環境も様々なので、
あなたに合った勉強法はこれです、とすぐに断言はできません。
そういい意味では、これまでの自分を振り返り、
あなたの人生の棚卸しをしてみるのがいいですね。
どこを受験するかを決める際にも、人生の棚卸しは必要ですし、より目標が明確になって、勉強にも頑張れるのではないでしょうか。
まとめますと、公務員試験は
予備校(専門学校)に行かねば合格できない試験ではありません。
家にいるとダラダラしてしまうので、
予備校に通うことでより勉強できて頑張れるという事であれ
0

専門試験対策&まとめ
前回の教養試験に引き続き、専門試験対策について書いていきます。
多くの方は「一般行政」で受験すると思いますが、
基本的な試験対策は教養試験と同じで、過去問の研究が最重要になります。
これが公務員試験の「王道」です。
過去問に始まり、過去問に終わると言っていいと思います。
出題される問題は、過去問の焼き直しが圧倒的に多いので、
過去問と解き方をセットで覚えるのが効果的です。
過去問の研究を十分行うことは、
公務員試験以外の場合でも過去問の研究が重要です。
まず過去問を手に取り、その研究からはじめていきましょう。
私、最初に申し上げましたが、
技術系(土木職)の公務員でしたので、
ハッキリ言って一般行政に関する専門試験対策の詳細は分かりません。
ですので、技術系の専門試験対策をどのようにすればよいか、
簡単にまとめていきましょう。
最初の段階で、自分の大学・学部・学科からどれくらいの人数が
公務員になっているのかを調べておく必要があります。
毎年ある程度の人数がいるのであれば、
配属される研究室(ゼミ)によく受験する役所の試験問題が残されています。
私は神戸市内の大学に通っていましたので、
兵庫県庁や神戸市役所の過去問が代々受け継がれていました。
試験問題は、大学の定期試験と同じような問題が多いので、
定期試験の勉強が公務員試験対策につながります。
やった事と言えば、それぐらいです。
・過去問を研究して何度も解く
・定期試験の勉強をしっかりする
おそらく、他の専門科目も一緒ではないでしょうか。
短期間ですぐに成果が出てくる科目は少ないですが、最低半年間は少なくてもいいので勉強時間を
0

教養試験の学習法
今回は、教養試験の勉強法について書いていくようにします。
公務員試験を受験しようと思ったら、
最初に書店で過去問の本を手に取るとか、
ネットで検索するのではないでしょうか。
私が受験した頃はネットが普及しておらず、
携帯電話が出始めた頃でしたので、
書店に行くしか情報を入手する方法がありませんでした。
専門試験については、私は理系でしたので、
過去問はゼミの先輩からもらいました。
一般行政(文系)ならば専門試験の問題も
書店やネットで入手(確認)できるはずです。
何と言っても、試験勉強を始めるになたり、
「過去問」を徹底的に研究していくことが最重要です。
これをしなければ、始まらないという事です。
過去問を十分研究した上で、科目特性に合わせた学習を行う。
これが公務員試験の「王道」です。
過去問に始まり、過去問に終わると言っていいと思います。
出題される問題は、過去問の焼き直しが圧倒的に多いので、
過去問と解き方をセットで覚えるのが効果的です。
過去問の研究を十分行うことは、
公務員試験以外の場合でも過去問の研究が重要ですね。
次に科目別の傾向を見ていきましょう。<知識系科目>
単純に勉強時間に応じて得点が伸びる科目なので、
過去問を分析して出そうなところだけを覚えるのが基本です。
知識系科目の配点は低いので、勉強時間にそれ程時間は取れません。
ロングランで勉強しても忘れるリスクがあるので、
一夜漬け学習のノリで、直前期にまとめて学習するのがよいと思います。
<理論系科目>
数的処理(数的推理、資料解釈)や英語が該当。
ただし、得点が伸びるまでに時間がかかるので、
正しい学習法
0

教養試験の突破戦略
出題範囲の広い教養試験をどう突破していくのか、
今回はそれについて書いていきます。
教養試験に高得点獲得は必要はありません。
何とかして「60%以上の得点」をかき集める、ということが大切です。
そのためには、
「選択」と「集中」
が重要になります。
最初に、得点が取れる科目を選びましょう。
配点や好きかどうか、伸びしろはまだあるか等も確認して下さいね。
現状で高得点が取れている科目があれば、
それについては伸びしろがあまりないので、要注意です。
過去の教養試験で出題されている分野を確認すると、偏りがあることが分かります。つまり、出題される分野はほぼ決まっているのです。これは、過去問を研究すればわかることで、全てを勉強する必要はありません。
なので、全ての分野を勉強してはダメで、
捨てる科目と分野を選ぶことが、勉強を進めていく上で重要になります。
教養試験で6割を取るために、
出題分野を以下の4つに分類してみましょう。
( )内に私の例を示しながら説明します。(1)高配点×得意(数的処理)
徹底的に伸ばす。
毎日短時間でいいので取り組んで数字のカンを養いましょう。
(2)高配点×不得意(現代文、英文、政治経済など)
いかに得点を伸ばすかがポイント。
不得意の意識を少しでも解消できるよう勉強に取り組みましょう。
(3)低配点×得意(物理、化学)
要領よく勉強して、もっと伸ばしていく。
ただ、伸びしろは少ないので、取りこぼしを防ぎましょう。
(4)低配点×不得意(古文、歴史、生物、地学など)
ほとんど勉強せずに諦める、点が取れればラッキーと考える。
いずれにせよ、過去問だけは、繰り
0

教養試験の傾向と分析
今回から「教養試験」について書いていくようにします。
教養試験は大きく2つに分類できます。
〇一般知能科目
・文章理解(現代文、英文、古文)
・数的処理(数的推理、判断推理、空間把握、資料解釈)
〇一般知識科目
・社会科学(政治経済、時事問題)
・自然科学(物理、化学、生物、地学)
・人文科学(地理、世界史、日本史)
数学は自然科学に入るのですが、
出題は数的処理に含まれるので数学単独の出題はほとんどありません。
思想や文学は人文科学に含まれますが、
ほとんど出題されませんので、出題分野から外しています。
次に教養試験の形式についてですが、基本は五肢択一式になります。
なので、分からない問題もカンで回答ができます。
必ず全ての問題を回答するようにしましょう。
私も分からない問題は、残り10分で鉛筆を転がして回答しましたよ(笑)
次に配点ですが、基本は各問題1点で、40~50問出題されます。
過去問の焼き直しが圧倒的に多いので、過去問の研究は必須です。
問題作成する時も、まず10年分くらいの過去問を研究しますので、
まず過去問を入手して解いてみましょう。
出題としては、数的処理が一番多く、全体の約1/3程度を占めるので、
ここを重点的に勉強しなければ合格は難しいです。
合格ラインはの目安は6割(60%)の得点になります。
出題範囲が広く、勉強量もそれなりに必要なので、
自分には合格は無理だ
と感じてしまう方も多いと推察します。
早いうちに判断するなら、それも賢明ですが、
折角公務員を目指そうと思ったのであれば、諦める前に
数的処理
の過去問を少し解いてみて下さい。
こりゃダメだ、
0

就職試験と思え
前回は公務員試験の概要について説明しました。
今回はそれぞれについて、もう少し詳しく見ていきましょう。
私が公務員試験を受験したのは平成6年、
関西国際空港や明石海峡大橋が完成し、インフラ整備が盛んな頃でした。
平成7年1月に阪神・淡路大震災が発生し、私の自宅も被害を受けました。
わずか20秒くらいの強い揺れで、あのような被害になるとは・・・
その2ヶ月後に地下鉄サリン事件が発生、
就職する直前の出来事だったので、今でもよく覚えています。
その頃の公務員試験は、こんな感じでした。
学科試験:重視
論文試験:無難にやればok
人物試験:無難にやればok
筆記試験による事務処理能力が「最重視」され、
論文や人物試験(面接)でどんな人間なのかを補足的に確認するだけでした。
では、現在はどのように変化したでしょうか。
学科試験:足切り的に活用
論文試験:重視
人物試験:最重視
学力重視から論理的思考力や人間性を重視するようになり、
大きく方向転換しています。
ここはしっかりと理解しておいて下さいね。
公務員試験の最終ゴールは「内定」の獲得ですので、
筆記試験で高得点を取ることが目的ではありませんよ。
次に、各々の試験の評価項目を見ていきましょう。
(筆記試験での評価項目)
・事務処理能力
・論理的思考力
・数字を扱う力
簡単に言えば、
基本的な頭の良さを審査するのが筆記試験です。
(人物試験での評価項目)
・仕事をする能力
・組織への適応能力
・コミュニケーション能力(協調性)
簡単に言えば、
筆記試験では測定できない要素の審査をするのが人物試験です。
時代の変化とともに、
公務員試験
0

公務員試験とは
前置きが長くなりましたが、
今回から本題である「公務員試験」について書いていきますね。
ご存じの方もおられると思いますが、
試験は大きく分けて2つあります。
(1) 筆記試験(一次試験)
・教養択一問題
一般知能科目(公務員試験特有の問題)と
一般知識科目(大学受験レベルの問題、基礎知識を問う)
・専門試験:行政専門、理系科目(土木、建築、環境など)
・論文試験:一般論文、専門論文
(2) 人物試験(二次試験) ※一次試験合格者のみ
・面接試験
・論文試験試験内容の詳細については、次回以降で説明します。
当然のことですが、
願書提出時には、受験資格や要件、欠格条項等を確認する必要があります。
新卒の場合は問題ありませんが、
社会人枠で受験する場合は「年齢制限」があるので、そこは要注意です。
あと大丈夫とは思いますが、
車のスピード違反や無免許運転等で検挙されていませんよね?
受験料は無料です。
ただ、必要経費は税金から支出しているので、
無料だからと言ってむやみやたらと受験するのではなく、
自分のやりたい事をよく考え、的を絞って勉強していきましょう。
試験日程については、受験したい自治体等のHPで確認して下さいね。
本命だけしか受験しないのはちょっと怖いので、
3つくらい受験するのが適当かと思います。
私の場合は、本命が地方上級の技術職でしたので、
ワンランク上の国家公務員1種とワンランク下の2種試験を受けました。
結果は2勝1敗で、自分が設定した目標通りの結果でした。
あなたも勉強開始する前に、受験先を決めましょう。今後のプロセスとしては、大きく分けて以下の5つになります
0

公務員としての基本を身につける(その4)
<これまでのポイント>
整理のスキルを身につける
バランス感覚を身につける
光を放つ存在になる
今日はこの3つに加えて、執着から離れることの大切さを説明したいと思います。
「執着」という言葉は、よい意味で使うこともあります。
・勝利への執着心を持つ
・成功するまで諦めない(成功に執着する)
これ以外にも、家族や友人が不慮の事故で他界し、
その責任を追及するため、裁判に持ち込んで有罪になるまで諦めない。
執着心がなければ、このような事はできません。
当事者のお気持ちを察すると、
亡くなった方の弔いをするために一所懸命頑張ることは理解できるのですが、
そうすることが本当に故人の弔いになるのでしょうか。
本当に故人の遺志を受け継ぐことになるのでしょうか。
大きな疑問です。
事故を起こした罪は、起こした本人が償わねばなりません。
今生で償いきれない分は、死んだ後(後生)に引き継がれます。
あなたが無理に頑張らなくても、
犯した罪の償いはその本人が背負っていかねばなりません。
お釈迦さまが説かれた仏教(経典)には、このように説かれています。
すみません、申し遅れましたが、
私の母方の実家が浄土真宗のお寺であったので、私は仏教とご縁が深いです。
時々、経典のエピソードも交えながらお伝えします。
本題に戻りますが、
執着から離れることと、公務員が携わる公務とどう関係があるのか。
納税者との対応をはじめ、公務員になると様々な仕事に従事するため、
慣れない頃は失敗を繰り返すと思います。
失敗は自分を成長させてくれる肥やし(原料)
と常に思わなければ、公務員としての責務は果たせません。
あー、失敗
0

公務員としての基本を身につける(その3)
整理のスキルを身につける
バランス感覚を身につける
この2つの重要性を理解してもらえたでしょうか。
今回は、光を放つ存在になろうという話をしたいと思います。
光を放つ?
ヘッドライトを頭につけて勉強するという事?
もちろんそんな意味ではありません。
あなたの個性(光)をアピール(放つ)しよう、という意味です。
現在は「個」の時代、多様性が重視されるようになりました。
ジェンダー差別、人権問題、夫婦別姓・・・
あなたも個性を強調してよいのです。
SNSの普及により、個人の個性を簡単にPRできるようになりました。
マナーは守らねばなりませんが、基本はSNSで自由にPRできます。公務に携わる公務員に個性なんて不要ではないか、と思うかもしれませんが、
様々な納税者に適切に対応していくのが公務員としての重要な仕事ですから、
対応の過程でよいところをドンドン吸収し、
あなたが魅力ある人間になることで、納税者に対する恩返しができます。
自分が得た知識や経験を還元していくことで、
納税者とWIN-WINの関係になります。
ちょっと書き過ぎた感がありますが、
様々な事を吸収しながら、あなたらしい光を放ちましょうという意味です。
それが公務員としての責務でもあるし、納税者への恩返しになります。無数の色の光があっていいです。例を挙げると、
・書類の整理が得意
・電話対応なら任せてね
・長い文章を書くのが苦にならない
・窓口対応が大好き
・道路管理のことなら何でも聞いてくれ
こんな感じでしょうか。
一色だけを放つのではなく、多数の色を放っても全く問題ありません。
整理のスキルとバランス感覚が身について
0

公務員としての基本を身につける(その2)
前回は整理のスキルを身につける事の大切さを訴えました。
今回は「バランス感覚」を身につける事の重要性を記述したいと思います。バランス感覚って何?
食事のバランス、体調のバランス、心のバランス・・・
バランスと言っても色々あります。
公務員となって公務に携わる上で重要になる「バランス感覚」とは?
公務員は税金で仕事をするため、色々な場面で納税者との対応があります。
・電話問い合わせ
・住民票や印鑑証明書等の交付
・窓口対応や民間業者との交渉など
高齢者の方から若い学生まで、相手は様々ですね。
スマホ知識の豊富な人もあれば、携帯電話しか使えない方もある。つまり、どのようなタイプの方を相手にして対応するかはわからないので、
相手に合わせて丁寧かつ親切な対応をしなければなりません。
相手のニーズに合わせた対応をするためにも、バランス感覚が重要です。
物事を客観的に見る力、と言ってもいいでしょうか。
相手の立場に立って物事を考える習慣をつけていく、という事ですね。
これは納税者だけではなく、
職員間や仕事上付き合いのある民間企業の方と接する時も同様です。
パソコンに不慣れな上司もいれば、同年代の方々もいる。
自分と気の合う仲間ならば、このような事を考える必要もありませんが、
公務を遂行する上でポイントになるのがこの対応力。
昔お世話になった上司から
「人間力をアップさせよう!」とよく言われた事を覚えています。
一つの考え方に凝り固まるのではなく、
時事問題を中心に幅広く知識を習得して、見識を深めていく。
なるほど、こんな考え方もあるんだな。
今まで誤解していたけど、こんな目的があったのか
0

公務員としての基本を身につける(その1)
公務の実務を長年経験した立場から、
勉強以外で何を準備しておけばよいか、具体的に書いていこうと思います。
勉強に関しては、以前の記事に書いた通り、半年間集中して取り組めば十分です。半年では不安だという方は、1年前から始めるのでも構いません。これを頭の片隅に置いておいて下さいね。
公務員を目指すあなたに是非とも身においてほしいこと、それはまず第一に
整理のスキル
です。今でこそ電子化が進んで書類の量が少なくなりましたが、
昭和の時代より以前は「紙」資料しかありません。
平成に入って初期の頃はワープロでした。
私が役所に入った頃は、富士通のoasysという機種を使って仕事をしていました。今では姿をみかけなくなりましたね。平成10年代に入ってからパソコンが普及しはじめ、
データの保存に共有フォルダを活用するようになりました。
生まれた頃からスマホを使っている若い世代の皆さんは驚きだと思いますが、パソコンが普及し始めてまだ20年、スマホで約10年しか経過していません。そのため、電子媒体資料と紙資料、うまく使い分けていかねばなりません。
仕事の効率を上げて、手際よく公務を進めていくためにも、
整理のスキルが大変重要になります。
よく使う資料はすぐに探せる場所に保存する、
あまり使わない紙資料は、机から少し離れた棚や地下倉庫に保管する。
机の周辺だけでなく、パソコンの中も整理しておく事が重要です。
こういった事を教えてくれる先輩は職場では少ないと思います。
仮に教えてくれる方がいても、身につけるためにはあなた自身の努力が必要です。
私は整理収納が比較的得意でしたので、さほど苦労はしませんで
0

経験者に相談してみよう
何をやるにも同じ志をもった「仲間」の存在は大切です。
孤独にコツコツと勉強を続けていくのが理想ではありますが、
高校受験や大学受験なら仲間を探すことは容易でしょうが、
公務員試験となると周囲に仲間を探すのは難しいのではないでしょうか。
だから、あなたもこのようなブログを検索して読んでいるのですよね。
私の経験談で言うと、
公務員試験を受験するか民間企業の面接を受けるか迷っていた時、
当時のゼミの担当教官から
「君は公務員が向いているから、これから勉強して公務員試験を受けなさい!」
というこの一言が公務員になるキッカケだったのです。
人生とは不思議なもの。
担当教官のこの一言に従ったおかげで、自分の人生の約半分を公務員として
働くことができたわけですから、担当教官には感謝しかありません。
公務員になりたいと思っているあなたは、もしかすると
公務に携わった経験者から見た場合、別の道に進んだ方がよいかもしれません。
・信頼して相談できる仲間がいる
・専門学校に通って勉強するので先生と相談する
・公務員として働いている先輩と相談できる
等であれば、私から何も言うことはありませんが、そうでない方も多いでしょう。
コロナに関する記事も書きましたが、
公的な病院で勤務している同僚と話をする機会があり、
このコロナ騒動がインフルエンザと同等のレベルに落ち着くには10年かかるそうです。
10年だって・・・
勿論、ワクチンや特効薬が完成し、私達の恐怖心がなくなる状態になるまでの時間が10年ということですが、長い道のりです。医療関係者だけでなく、公務に携わる人員がまだまだ足りないので、
多くの若者に
0

公務員試験勉強を始める前に
「公務員になって何がやりたいですか」
この質問にしっかり答えられるようになることが大切だと前回述べました。
これは民間企業に就職する場合でも同じですよね。
公務員対策の勉強は、当然それなりの努力が必要になりますが、
あなたが公務員になりたいと少しでも考えているなら、
勉強を始める前に官庁や自治体が主催する「説明会」に足を運びましょう。
可能ならば、
「インターンシップ制度」を活用して、あなたが希望する県庁や市役所で
実際に勤務してみるのが一番いいです。
就職したいところが明確になり、そこで実際に働く経験ができれば、
当然ですがモチベーションが上がり、勉強にも拍車がかかりますよね。
話をまとめると、
「公務員になって何がやりたいですか」
が明確になれば、次に
「どこで働きたいですか」(※国、県庁、市役所など)
を明確にすること。
願わくは、そこで働く体験をする。もしくは働いている方の声を聞く。
試験勉強は集中して半年間取り組めば大丈夫です。
試験に合格することだけを考えるのではなく、
公務員として「公共サービス」に長く従事できるような準備をしておくべきです。そうしないと、折角の勉強が無駄になってしまいます。元公務員の方が、動画をアップしておられました。首席で合格されたにも関わらず、わずか数年で退職されたそうです。
色んな事情があったにせよ、勿体ないですね。この能力を公共サービスとして還元して欲しかったと切に思います。
公務員としての経験を重ねて、係長や課長等の役職につくと、
住民の代表である議員からの「要望」に対する交渉(打合せ)、
首長である知事や市長に政策に関するレク(説明)
0
あなたも記事を書いてみませんか?
多くの人へ情報発信が簡単にできます。
ブログを投稿する
多くの人へ情報発信が簡単にできます。


.png)








.jpeg)





















