すべてのカテゴリ
新着有料ブログ
1,262 件中 1 -
60 件表示

その人の外側と内側のギャップ・3
勝つことだけを追い求める生き方人の世には本来「みじめさ」は存在していないということ。
平常心の人であればそのことは漠然とどこかで分かっています。
そういう人からすると他人を見下す修羅界の人を見て「なんで、こんなことするのかな?」と不思議に感じるのです。
ただ、修羅界の人が成功を収めたということに対しては一般的には、それ自体はすごいことですから他人が褒めたり、賞賛したりします。
そうするとその時だけは満足感が得られます。
でも「本当に自分がしたいこと」で成功したわけではないので虚しさは消えないのです。
・・・この修羅界の人は「本当に自分がしたいこと」は分かっているのでしょうか?
分かっていないからこんなことになってしまっているんです。
(※「本当に自分がしたいこと」=これは最終的には使命になっていきますがよく分からない場合はとりあえず目の前にあるこれだと思うものに向き合ってみましょう。)
こんなこと=勝つことだけを追い求める生き方です。
そして、次の目標を目指してまた戦いの日々に入っていきます。
でもその目標は他人から褒められ賞賛されることが第一の基準となっていますから自分不在の目標です。
そして、成功してもむなしい為同じことの繰り返しとなります。
人生が大分遠回りとなってしまいます。
つづく
0

過去に溶け込む、今
こんにちは。
いつも
ありがとうございます。
ふと
こんなことを思いました。
今という瞬間は
その瞬間瞬間に
過去に溶け込んでいく。
その瞬間は
二度と戻って来ない。
次から次へと
まったく切れ目なく
瞬間瞬間は押し寄せて来て
その瞬間瞬間は
容赦なく
過去の遠い方へと
押しやられていく。
服のチャック・ジッパー。
引き手を持って閉じてみる。
二手に分かれて
自由に開いてたものが
引き手のとこで合わさり
一本のラインになっていく。
開いてる部分
未来。
引き手の部分
今。
合わさった一本のライン
過去。
そして
チャックを引くのは
自分。
未来の方から
どんどんどんどん
チャックのレールが流れてくる。
開いた状態なので
いろんな可能性を含んでいる。
そこに向かって
引き手を引く自分。
引き手を通る
その瞬間が今。
今が
弾き手を握る自分の中を
通り過ぎる。
そして
自分の後ろに
あったこととしての事実が
一本の線として
長々と残っていく。
なんか
今を生きる
というようなことを考えてたら
こんなことを思っちゃいました。
今。
この瞬間。
時が
自分の体を通り抜けて
過去に溶け込み
流れていく。
そのほとんどが
忘れ去られてしまう。
でも
台風の経路みたいに
今までたどって来た軌跡は
確実に一本ある。
それが自分史。
自分史は
もうすでにあったことなので
変えることはできない。
だから
できるだけ
今今を
楽しい瞬間楽しい瞬間にできるよう
意識していく。
チャックの引き手を
楽しい方に楽しい方に引いていくよう
心がけていく。
人は
ほっとくと
時を
漫然と
過去の方に垂れ流しにし
0

人に依存しない
こんばんは。新年度になり、新しい環境を迎えた方、以前と同じ日常の方もいらっしゃることと思います。そのような中、孤独を感じたり、今の環境に満足できなかったり、同じ日の繰り返しで変化もなくつまらなかったりすることもあるかもしれません。孤独や変化がない時、今の生活に不安がある時は人に依存しやすい傾向にあります。必要以上にラインを送ったり、会話をしようとしたり。そして、ネガティブなことばかり言っていたり。それを人は重いと思うかもしれません。どんなに心を許した人でも、過度な依存は負担が大きくなります。依存された方も大きなストレスを抱える場合があります。自分が逆の立場だったら。。。どんな環境に置かれても、人に依存しないという生き方が大切になります。話を聴いてもらって心が楽になることも大切ですから、過度な依存にならないように、自分でコントロールしながら、程度を見極めて頼ってみると良いでしょう。1人でも楽しめる時間も作れると良いですね!また、楽しいことを一緒にできる仲間がいると良いですね。気持ちを楽にしていきましょう。まずは一人時間を過ごせるように整えていきましょう。
0

人に親切=自分に親切
こんにちは。
いつも
ありがとうございます。
人に親切は
自分にも親切。
電車で
座っていたイマノリ。
駅に着く。
人がドッと乗って来る。
と
イマノリの前に
スヤスヤと眠る赤ちゃんを抱いた
ママさんが。
すかさず
席をゆずる。
つり革につかまりながら
これまた
すかさず
ゆずった自分をホメる。
それからはもう
自分の気持ちが
うれしくてうれしくて。
電車を降りてからも。
家までの歩きも。
もう気分がいい。
人に親切にすることは
もちろん
相手の方も喜んでくれるだろうけど
何よりも
最終的に
自分が一番喜ぶね~。
人への親切は
結局
自分への親切でもある。
相手を思いやって
大切にする。
それは
自分を思いやって
大切にしてるのと同じこと。
だから
周りに
どんどん親切にしていこう。
自分を喜ばそうなんて
思う必要は
まったくない。
周りに親切にすれば
自動的に
自分にも親切になるから。
自分をやわらか~くして
視野を広げて
周りを見ていくことで
周りに親切にしていける。
やわらか~く
ひろ~く。
0

なぜFIREが注目されているのか?
Financial Independence, Retire Early(FIRE)が注目される理由は、現代の経済状況や働き方の変化に対する新しいアプローチを提供しているからです。従来のリタイアメントプランにとらわれず、個々の自立とライフスタイル設計を重視するFIREは、多くの人々に魅力的な選択肢となっています。
まず、経済的自立への渇望がFIREの普及を後押ししています。伝統的な仕事に依存せず、資産を効果的に活用することで、個々の自立が実現できるため、多くの人が経済的な自由を追求しています。また、働くことに対する価値観の変化も影響しており、長時間労働やストレスの多い職場環境に代わり、自己実現や生活の質を重視する傾向が強まっています。
さらに、インターネットやソーシャルメディアの普及により、情報が容易に入手できるようになったこともFIREの注目度を高めています。成功事例やベストプラクティスが共有され、FIREへの取り組みやその効果が広く知られるようになりました。これにより、FIREが達成可能な目標であることが証明され、多くの人々がその実現を目指すようになりました。
さらに、若年層の間でのFIREの人気は高まっています。若い世代は、長期的な資産形成やライフスタイル設計に興味を持ち、早期に経済的自立を達成することで、自己実現や新たな経験に時間を費やすことができる可能性を追求しています。
これらの要因から、FIREは単なるリタイアメントプランではなく、自己実現や経済的自立を追求する新しいライフスタイルの象徴として注目されています。
0

奇跡の「ぼたっ」
こんにちは。
いつも
ありがとうございます。
先日
映画を観に行きました。
有名な映画だったので
期待して観てたんですが
まったく心に響いて来なくて。
ちょっとガッカリしながら
街を歩く。
ほんとだったら
どこかカフェにでも寄って
映画を思い返しながら
本を読んだりして
芸術的文学的な時間を過ごそうと
思ってたのに。
このまま家に帰ろう。
いつもの道じゃつまらない。
別の道を歩く。
横断歩道。
赤。
から青に。
渡っていると
向こうの方で
自転車にまたがって
こっちを見てる人がいる。
だんだん近づく。
ニヤニヤしてこちらを見ている。
その人をよく見てみる。
二呼吸くらいの間。
があって
「○○さん?」
相変わらずニヤニヤしながら
うなずくその人。
14年くらい前
めちゃ過酷な撮影だった戦争映画に
一緒に出演した仲間だった。
おそらく
10年くらいぶりの再会。
そのまま
横断歩道のとこで
30分くらいだろう
途切れることなく立ち話。
遠回りになるけど
相手の家の方まで歩きながら話す。
連絡先を確認し合い
家が近いので
また会おうと。
また
一人で歩き始める。
スーパーに寄ろうと思ったけど
いったん家に帰ってからにしよう。
初めて歩く道。
この道を通ると
ここに出るんだ~。
だいぶ家に近づく。
歩く。
歩く。
右腕を前に出す。
その右腕の袖に
ぼたっ!
鳥の糞。
うわっ!!
と思うのとほぼ同時くらいに
今日のすべては
この鳥の糞に当たるためだったのか~
と
納得と感心に心が満たされる。
すべてが
少しでもズレていたら
鳥の糞には当たることはなかった。
期待外れの映画。
行かなかった
0

どんな場所でもできる仕事を作り出せれば、自分のライフスタイルに合った好きな場所に住むことができる!【アラフィフ心理カウンセラー「うさぴょん」のココナラ電話相談
現代のテクノロジーの進歩により、場所にとらわれない仕事がますます一般的になっています。インターネットやモバイルテクノロジーの普及により、人々は自分のライフスタイルに合った場所で仕事をすることが可能になりました。この新しい働き方の概念は、自由な生活を追求する多くの人々にとって魅力的な選択肢となっています。
どこでもできる仕事とは、場所に依存せずに行える仕事のことです。例えば、フリーランスのライターやデザイナー、オンライン教育講師、ウェブ開発者、バーチャルアシスタントなどが挙げられます。これらの職種は、特定の場所に縛られることなく、インターネット接続さえあればどこでも働くことができます。これにより、自分の好きな場所で生活する夢を追求することができるのです。
自分のライフスタイルに合った場所での生活は、さまざまなメリットがあります。まず第一に、生活環境や気候に合わせて場所を選ぶことができます。例えば、自然が豊かな地域でアウトドア活動を楽しみたい人は、山間部や海岸沿いの町に住むことができます。逆に、都会の喧騒を求める人は、大都市の中心部に近い場所を選ぶことができます。
また、移動の自由度も高まります。仕事が場所に縛られていないため、旅行や移住をより柔軟に行うことができます。長期的な海外滞在やデジタルノマドとして世界を旅することも可能です。さらに、家族や友人との時間を大切にしたい人は、故郷や好きな場所に近い場所で仕事をすることで、より豊かな人間関係を築くことができます。
ただし、どこでもできる仕事にはいくつかの課題もあります。自己管理能力や効果的なコミュニケーション能力が求められるため、
0

たくさんのハッピーとラッキーを引き寄せる(後編)
さて後編です。【前編】の最後に
波動が低いとマイクもスピーカーも1つずつ持っているかどうか。ある程度持っていても壊れていたりする。と書きました。
これ、イメージできますか?マイク1本だとみんなに声が届かないから周りに影響力はないし、存在感もない。スピーカー1つだと聞こえる音が少小さいし、何を言っているのかクリアに聞き取れないから大事なことを聞き逃してしまいがち。マイクもスピーカーもそこそこ持っているのに壊れていたら、自分が伝えたいことに雑音が混ざって違うニュアンスで伝わってしまったり、結構いいこと言っても届かない。
情報が聞こえてこない。肝心な部分が途切れてしまい、自分なりに解釈して失敗・・
想像するだけでもネガティブになっちゃいます。状況を変えていく近道は「自分が変わる」こと一番簡単な方法は「感謝する」こと。
些細なことにも感謝の気持ちを持つこと。
最強の言霊でもある「ありがとう」を多用。また相手より先に伝えてありがとうポイントを貯める。これね、結構効くんです。店員さんは「いらっしゃいませ」「ありがとうございました」と言ってくれます。もちろん心込めて言ってくださると思いますが、もっと心を込めてもらいたい。だから
こちらから先に「ありがとう」を伝えます。すると返してくれる「ありがとうございます」には心も愛も込められてきます。最強の「ありがとう」をたくさんもらうと、幸せオーラに包まれてきます。
次に「掃除」と「デトックス」です。
ごちゃごちゃした部屋や汚れた場所を見た時に、ネガティブ感情になりませんか。
完璧な掃除じゃなくていいんです。
自分なりに整えて「よくやった」と思えばOK
0

約束を破ること
こんにちは。
いつも
ありがとうございます。
約束を無断で破るって
実は
破った本人が
一番
心にダメージを負いますね。
先日
イマノリの
体験会に申し込まれた方。
当日
時間になっても
ZOOMに入って来られず
そのまま何の連絡もなく
キャンセルってな感じで。
もちろん
キャンセルされること自体は
しかたないことで。
イマノリのことがイヤだったのか
体験会に興味なくなったとか
あやしいとかね。
こちらにも
少なからず非はあると思うので。
ただ
何の連絡もなしだと
もちろん
こちらもガッカリしますし
なにより
ご本人が
自分で自分のことを
「ダメなやつ」って
思っちゃうでしょ。
まったく
何も感じない人も
いるかもしれませんが。
でも
大体の人が
何かしら
心に痛みを感じるはず。
「連絡せずブッチした自分」
「約束を守らない自分」
こういったコトバを
無意識のうちに
自分にかけてしまうでしょう。
「自分ダメダメだな~」
「自分どうしようもないな~」
こんなふうに
どんどん自分を責めてしまう。
もっと
自分のことを大切に扱って欲しいな~
って思っちゃいました。
相手もそうだけど
何と言っても
一番傷つくのは
本人。
それが
無断で約束を破ること
ですね。
ご自分のことを
あまり
悪く言ってなければいいんですけどね。
0

その状況を、今の自分を、遠くから見てみる
こんにちは。
いつも
ありがとうございます。
4月16日は
喜劇王チャールズ・チャップリンの
135回目の誕生日でした。
イマノリ
学生時代チャップリンの映画をたくさん観ました。
有名な映画はもちろん
初期の短編も。
今も家にありますが
ビデオを全10巻とか買って
集めてました。
人間の面白おかしさ。
人間のあたたかさ。
チャップリン映画からは
こういったものを感じます。
また
いくつか名言も残してますね。
そのうちの一つ。
『人生は
近くから見れば悲劇だが
遠くから見れば喜劇だ』
人生を俯瞰してみる。
人生を振り返ってみて下さい。
その時は
ものすごく大変な状況だった。
でも
時間が経って
遠くから見た今となっては
笑って話せる大事な思い出になっている。
こういったこと
あなたにも
あるんじゃないでしょうか?
自分を俯瞰してみる。
今の自分
まさに
悲劇の主人公。
その役に
どっぷりとハマって
周りが見えなくなる。
悲劇の自分を遠くから見てみる。
現状は大変ちゃー大変なんだけど
それでも
「なんとかなるでしょ」
ってな感じで
意外と前向きに捉えることができる。
今の物事
出来事状況を遠くから見てみる。
俯瞰してみる。
すると
取るに足らない
ちっぽけなことだと気づける。
自分を
遠くから見てみる。
俯瞰してみる。そこまで
悲劇的じゃないことがわかる。
人は
物事を
自分のことを
近くから見て
その不幸な部分を切り取って
そこだけ見てしまいがち。
もっと視野を広くして
客観的に見てみる。
そうすれば
悲劇の主人公から抜け出て
一人の観客として
冷静に見ることができるようになる。
0

人生最後の姿を描き、それを念頭に置いて今日を始めることが大切!【アラフィフ心理カウンセラー「うさぴょん」のココナラ電話相談
人生は一過性であり、誰にとってもいつかは最後が訪れます。その最後の瞬間に振り返るとき、私たちは自分の人生に何を求め、何を成し遂げたかを考えるでしょう。この視点から、人生の終わりを見据えた今日の意味について考えてみましょう。
最後の姿を描くとき、多くの人は幸福や満足感、愛する人たちとの豊かな時間を望むでしょう。しかし、そのためには今日の行動が重要です。人生の最後に後悔や未練を残さないためには、今日一日一日を大切に過ごすことが肝要です。
今日を人生の最後の姿に照らし合わせると、些細なことでも大きな意味を持つことに気づきます。例えば、愛する人とのひとときを大切にすることや、自分の夢や目標に向かって努力すること、他者への思いやりや感謝の気持ちを忘れないことなどが挙げられます。
また、人生の最後に求めるものは物質的な豊かさだけではありません。むしろ、心の豊かさや精神的な充実感が重要です。自己成長や他者への貢献、人間関係の深化など、内面からの充実感が人生に深い意味を与えます。
人生の終わりを見据えることは、今日の行動をより意識的にし、価値ある時間を過ごす助けになります。後悔や未練を残さない人生を送るためには、今日を大切に生きることが欠かせません。だからこそ、人生の最後の姿を描き、それを念頭に置いて今日を始めることが大切なのです。
0

あなたを待ってる人がいる
こんにちは。
いつも
ありがとうございます。
4月も半分が過ぎ
新しい職場とか
新しい環境に
少しずつ慣れてきたよ
っていう人も
いるんじゃないでしょうか。
4月の広告キャッチコピーに
こんなのがあるんです。
「入学式。
どこかに、
一生の友達が座っている。」
イマノリ
今月
飲みに行く予定の人がいます。
その人は
小学生からの友達なんです。
年に一回か二回くらいしか
会わないんですが
会えばすぐに
空気のように
いて当たり前という感じになります。
まさに
一生の友達。
小学
中学
高校
大学
それぞれの入学式。
入社式。
異動先の職場。
あるいは
何かのコミュニティとか。
この先
ずーーっと付き合っていくような人が
いるかもしれない。
友達だけじゃなく
結婚相手もいるかもしれない。
出会ったとしても
もう二度と会わない人がほとんどの中
数少ないけど
一生付き合っていく人がいる。
おもしろいですね~~
出会いって。
みんなみんな
誰かが
どこかで
あなたを待っている。
0

切りかえられる「自分」を作る
こんにちは。
いつも
ありがとうございます。
毎日を楽しく
人生を楽しくしていくために
どんな「自分」を作っていったらいいか?
それは
気持ちを切りかえられる「自分」
です!
人は
日々
そして
刻々と
気持ちが変わっていきますね。
自分の体が
元気な時
疲れた時だけでも
気持ちが変わってきます。
それに加わって
周りの人との関係や
出来事などにも
左右されてくる。
喜んでみたり
シュンとなってみたり
イライラしてみたり。
プラスの方に行ったり
マイナスな方に行ったり。
気持ちが揺れ動くのは
しかたない
というか
人間として当然のこと。
気持ちがあるから
人間ですもんね。
映画やドラマ
本を楽しめるのも
気持ちがあるから。
気持ちが揺れ動いてくれるから
楽しめる。
でも
普段の生活で
ず~~~っと
マイナスな方の気持ち
ネガティブな方の気持ちのままだと
そりゃ~
しんどいですよね。
つらいし
苦しくなっちゃう。
そんな時に登場するのが
気持ちを切りかえられる「自分」~。
自分で
自分の気持ちを切りかえていく。
まずは
今の自分に質問をして
気持ちを
マイナスからゼロに戻してあげる。
「落ち込んでてもしょうがないよね?」
「イライラするほどのことかね?」
「楽しくしたいでしょ?」
そしたら
ゼロからプラスの方にもって行く。
「次に向かって行こう」
「感謝できることはあるかな?」
「自分のできてるとこはどこだろう?」
「自分の良いとこはどこかな?」
こんなふうに
自分へコトバをかけていく。
自分が元気になるコトバ。
自分が楽しくなるコトバ。
自分が喜ぶコトバ。
こういったコトバをか
0

たくさんのハッピーとラッキーを引き寄せるには(前編)
気がつけば2024年の3分の1が終わろうとしていますね。時の流れが本当に早く感じますが、この4ヶ月を振り返ってもし
「あまりいいことなかった」
「特別なことはなくいつもと同じ」
と感じているなら、2024年残り3分の2は巻き返していきましょう!波動を知る
「波動」をWebで調べてみると
1 波のうねるような動き。
2 空間の一部に生じた状態の変化が、次々に周囲に伝わっていく現象。水の波・音波などの弾性波や、光・X線などの電磁波など。 と説明されていました。
(英語では wave または vibrational energy という表現を使うようです)人にも生物にも物質にもエネルギーがあり、そのエネルギーが波動です。
この宇宙に存在する物質は素粒子からできていて、常に振動しています。
私たち人間は素粒子が集まってできているため、振動している=波動があるという考え方です。波動の高さ=マイクとスピーカーの数
波動が「高い」「低い」をわかりやすく表現すると、マイクとスピーカーをいくつ持っているかというイメージです。
波動が高い人にはたくさんのマイクとスピーカーがありますから、周りに影響を与えやすく、たくさんの情報をゲットしやすい。
周りに影響を与えやすいということは「他人に振り回されない」→ 自分軸で生きている。たくさんの情報をゲットしやすいということは「必要な情報やキーパーソンなどが舞い込んでくる」→望んでいることを叶えるスピードが早い。引き寄せる波動が低いとマイクもスピーカーも1つずつ持っているかどうか。ある程度持っていても壊れていたりします(>_<)愚痴っぽくなっ
0

やっぱり大事!自分へのコトバ
こんにちは。
いつも
ありがとうございます。
いや~~
やっぱり
自分へのコトバって
ほんと大事だな~~~。
先日
イマノリのワークショップに
参加された方。
今まで
こんなコトバを
自分にかけてたそうです。
「どうせ自分はダメ」
「自分は人と仲良くできない」
「自分は人から好かれない」
こういったコトバを
自分の気づかないとこで
何回も何回も
自分にかけてしまう。
そりゃ~
自分が
つらくなっちゃいますよね。
でも
この無意識のコトバたちに気づければ
それを
意識して
違うものに変えていけばいいわけで。
自分へのコトバを
自分にとって
プラスになるものに変えていく。
あなたはどうでしょうか?
自分に
どんなコトバをかけてることが
多いでしょうか?
意外と
「どうせ自分は・・・」的な
マイナスなコトバを
かけちゃってたりするんですよね。
よく
「自分を大切にして」
って言葉を
見たり聞いたりしますね。
その
お手軽な第一歩目として
自分にやさしいコトバ
をかけてあげる。
まずは
ここから始めてみて下さい。
自分が楽しくなるコトバ。
自分が喜ぶコトバ。
自分をホメるコトバ。
周りからの言葉で
自分が変わっていくことも
もちろんありますが
いつ
良い言葉を言ってくれるか
わからないですよね。
周りからの良い言葉を待ってたら
いつになっても
自分を変えることができません。
だから
自分で
自分自身に
良い言葉をかけていく。
これなら
毎日毎日
コツコツコツコツ
自分で
自分を変えていくことができるでしょ。
0

自分を好きになるためにはどうしたら良いか?
今回は、「自分を好きになるためにはどうしたら良いか?」というテーマにつきまして、思うところをお話させて頂きます。
上記のYouTube動画でもお話させて頂きましたので、よろしければそちらもご覧頂けますと大変有難いです。
まず最初にお伝えしておきますと、私自身、必ずしも自分を好きになる必要はないと思っておりますので、「絶対に自分を好きになった方が良い!」というような押し付けをするつもりはありません。
ただ、これまで公私共に色々な方と接してきましたが、自分を好きな人と、自分を嫌いな人を比べますと、やはり前者の自分を好きな人の方が充実した人生を歩んでいるように見受けられます。
ですので、自分を好きになるという事は、これからより一層充実した人生を歩んでいきたいと考えている人にとりましては、一つの重要なポイントではないかと考えられるのです。
では実際、「自分を好きになるためにはどうしたら良いのか?」と言いますと、それはやはり自分に自信を持つ事であり、そして自分に自信を持つためには、自分の良いところを自覚する事が大切であると思っております。
そして自分の良いところを自覚するために、最も効果的な方法は成功体験や幸福体験を味わう事だと言えるでしょう。
やはり自分の良いところを自覚する上で、そのきっかけとなる成功体験や幸福体験がない状況にも関わらず、無理やり自分を好きになろうと思っても、なかなか難しいと思うからです。
もちろん、個人の性格も影響してきますので、特に成功体験や幸福体験がなくても、自分を好きになれるようなポジティブ思考の人も中にはいらっしゃると思います。
しかし、そもそもそういったポ
0
.png)
自己啓発本を読んで生きやすくなる
こんにちは、ユウ_Yuです。
みなさんは自己啓発本を読むことはありますか?
私は本のジャンルのなかでは、自己啓発が一番好きです書店の本棚でも、まずは自己啓発本の新刊が出ていないかをチェックします。
働いている人は、一度は手にしたことがあるのではないでしょうか😊そのきっかけは様々だと思います。
・ビジネスを成功させたい。
・仕事に行き詰まった。
・働くモチベーションが低下している。
・人間関係やチーム形成に悩んでいる。
私は、人の機嫌や環境の変化にメンタルが左右されることがよくあります。
社会人になってから、これがHSP気質であることを知ったので、どうしたら生きやすくなれるのかという答えを求めて、自己啓発本を読むようになりました😊自己啓発本には生きるヒントがたくさん
自己啓発本を好んで読んでいる人のなかには、どうやら私と同じ境遇の人は少なくないようです。
HSPや繊細さんという気質が自分にあてはまりそうだと感じ、その気質を持ちながら働くにはどうしたらいいのかを学びたいから読み始めたという人。
うつ病などのメンタル疾患を抱えたことをきっかけに、自分と向き合う手段として、自己啓発本を読み始めたという人。
また、本を書く側も、HSP気質やメンタル疾患を抱えていたり、克服したりしていて、その経験を発信している人がたくさんいます。
自己啓発本は生きるうえでのヒントがたくさん隠された宝庫なのではないかと感じています✨どう読むのがいいのか
本を読むうえでのポイントは、「自分に合っていること」「自分ができそうなこと」だけを取り入れてやってみるということです。
当たり前のことかもしれませんね😓ただ
0

「そうと気づく力」 ~ききょうの言に思う~
今年の大河ドラマ(光る君へ)面白いですね。2年前放送された鎌倉殿の13人以来、はまって観ています。貴族社会(の上層・下層)と平民の暮らしやキャリアのコントラストがよく描かれていて、格差社会の到来と言われている現代にも思いをやる場面が少なくありません。 さて、すでに紫式部(まひろ)と清少納言(ききょう)が交流する場面が何度か描かれていますが、前回、まひろの屋敷にききょうが訪れて言葉を交わす様子は実に圧巻でした。すべては書きませんが、私が特に感じ入ったのは、ききょうが和歌の会に集まった姫君たちについて「志を持たず、己を磨かず、退屈な暮らしもそうと気づく力もないような姫たち。・・・まひろ様だって、そうお思いでしょ。」と話したところです。まひろは「そこまでおっしゃらなくても・・・」とためらいつつも、「まあ、少しは。」と応じています。 *なかなか手厳しくも聞こえる、ききょうの言葉にはじわっと来るものがありました。「そうと気づく力」を自分は持っているかな、と思います。知らず知らずのうちにコンフォートゾーンから自分の身を押し出すこともなく、惰性で生きてしまっているようなことはないかな、と、気づく力を使おうとしているかな、と。「志を持って、己を磨く」ということは、自ら選んだことであれば楽しくもあり、しかし時には痛みもともなうこともあるでしょう。なぜなら、志のために自己を今の状態から変えることは、過去の学習を捨てたり、新たな姿を模索しようとしてもがいたり、ちょっとしんどいこともやらなければならなくなるからです。自分で自分を追い込むことを覚悟するということも…。Think yourself.自分を
0

ありがたき終わり
こんにちは。
いつも
ありがとうございます。
つまらない日。
モヤモヤな日。
イヤイヤな日。
調子悪い日。
大変な日。
つらい日。
苦しい日。
緊張の日。
勝負の日。
本番の日。
くやしい日。
我慢の日。
忙しい日。
イライラの日。
怒られた日。
ミスした日。
悲しい日。
さびしい日。
落ち込んだ日。
情けない日。
恥ずかしい日。
思い悩む日。
どんな日だって
今日という日は
ちゃんと終わってくれる。
ずっと続かずに
リセットされていく。
今日
どんなことがあったとしても
しっかり区切られる。
今日。
今日。
そしてまた今日。
人は
ついつい
昨日を引きずってしまう。
昨日なんて
バイバイでいいのさ。
この今日一日を
楽しくしていいけばいいのだ。
どんな日だって
ちゃんと終わってくれる。
だから人は
また
胸張って生きていけるのさ。
0

わたしは幸せになることを許可します
𝐽𝑒 𝑚𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑒𝑡𝑠 𝑑'𝑒𝑡𝑟𝑒 ℎ𝑒𝑢𝑟𝑒𝑢𝑥
“わたしは幸せになることを許可します”
𝐶𝑟𝑒𝑎𝑡𝑒𝑑 𝑏𝑦 𝑆𝑎𝑙𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑀𝑎𝑟𝑖𝑎
悲しみの世界にひとりでいるとき
どれだけ誰かが手を差し伸ばしてくれても
その手を繋げば光の差す世界へ
連れていってくれるとわかっていても
手を取れなかった…
その手を握ってもまた離される気がして怖かった
あなたは大丈夫だよと何度言われても
そんな声はわたしの耳には入ってこなかった
“わたしなんてどうせ幸せになれない”
”わたしなんてどうせ生きてる意味がない”
“わたしなんてどうせ幸せになれない”
“わたしなんてどうせ愛される価値がない”
毎日わたしの言葉でわたしを呪っていた
でも誰かがわたしにそんなことを言ったの?
あなたには愛される価値がないって?
わたしの心の中の呪いの声に耳を澄ませて
“愛されたい、幸せになりたい”
という本当のわたしの声を
聞こえないふりをしていたのは誰?
だって可哀想な
わたしを演じるのは心地良かったんだ
そうしていたら皆が優しくしてくれたから
頭を撫でてくれたから…
だからもっともっとそれがほしくなって
どんどん可哀想なわたしを演じていた
だけどわたしはそんな人生を生きたかったの?
目の前に何人も手を差し伸べてくれたのに
振り払ったのはわたしだった
次はわたしが幸せになる番だよ
わたしがわたしを幸せにするときが来たんだ
大丈夫、もう怖くないよ
幸せになることを恐れないで
わたしは幸せになるために生まれてきたのだから
𝑆𝑎𝑙𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑀
0

子供を見習って、無邪気に
こんにちは。
いつも
ありがとうございます。
例えば毎日が
なんかつまらなかったり
モヤモヤしてたり
憂うつブルーな時は
ちっちゃなことを意識してみる。
朝。
必ずと言っていいほど
鏡を見ますよね。
その鏡に向かって
ニッコリしてみる。
思いっきり変顔をしてみる。これだけで
自分の気持ちが
ウキんとするのがわかるはず。
出かける前。
ここでもおそらく
鏡を見るはず。
スタンドミラーなんかがあったら
なおさらのこと。
その鏡に向かって
「自分、イイネッ!」
って言ってみる。
クレイジーケンバンドの
横山剣さん並みに
体も動かしてみる。
自分の気持ちが
プラスの方に
ググンと動くのがわかるはず。
家を出て
ドアを閉める。
その閉める時に
「よしっ!
今日も楽しむぞぃ」
と言いながら
「ぞぃ」のとこで
カチャンと閉めてみる。
特に意味はないけど
なんとなく気持ちいいのがわかるはず。
家から職場まで。
勝手に
周りのすべてを
自分の味方にしてみる。
朝の太陽を味方にしてみる。
「おお~
自分のことを輝かせてくれてる。
太陽さん、ありがとね~~~」
鳥たちの鳴き声。
「今日も楽しんでね~って
自分に言ってくれてる。
ありがとねん」
樹々
空
雨だって
みんなみんな自分の味方。
「自分のことを応援してくれてる~。
ありがとん」
子供じみてる感じがするでしょ?
ハハッ!
それでいいんです。
子供みたいに
無邪気に
自分で自分を
喜ばせていけばいいんです。
だって
朝の子供たちを見ればわかりますよね。
朝からめちゃくちゃ元気でしょ~!
子どもたちを見習わないと~。
難しいことや
大それたことも
0

Thank you very much ....
ブログを見てくださってありがとうございます。また、ハートまで頂いて感激しております。力になりますよー!!!ジャケットはいつの日かの朝日になります。夜明けが来ました!!メッセージも絶賛受けつけております。お気軽にご連絡くださいませ。~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・午前中は、Wi-Fiを設置しなおしておりました。模様替えの一環ですね。なんとエレコムさんでは母屋とは別に離れでも使えるように工夫されている中継器が発売されております。セール時のものを半年くらい使っているのですが、友達は外でもアニメが見れると驚いておりました。家のネットワーク環境を整えていくのも今後の私の仕事と思っております。ちなみに、私のPCはLANケーブルでつないで仕事をしております。在宅、副業する時には相手方が8GBメモリのHDDのパソコンとLANケーブル接続を求めらお客様もいらっしゃいますのでご注意を。Adobeソフトは処理能力がいりますので16GBくらいは必要と通信教育校の営業の方からの情報です。では、午後からもより一層の幸福を受けとられますように。I wish for you to catch the happy in after evening .(皆様の幸運をお祈りいたします。)※英語は独学ですので、つっこまれませんように。
0

先手必勝をすることで相手の心が開き、やがては相手からの働きかけが始まる!【アラフィフ心理カウンセラー「うさぴょん」のココナラ電話相談
人間関係は、時には戦略のようなものであり、先手必勝の考え方が有効な場合があります。相手の心を開き、良好な関係を築くためには、自らが率先して行動し、相手に前向きな働きかけを促すことが重要です。
先手必勝の重要性は、対人関係において特に顕著です。例えば、新しい知り合いやビジネスパートナーとの初対面の場面では、相手の心を開くことが鍵となります。ここで先手を打ち、相手に好意を示し、信頼を築けば、その後のコミュニケーションはよりスムーズに進むでしょう。
では、具体的にどのように先手を打てばよいのでしょうか?まず第一に、相手の興味や関心事に関心を示すことが重要です。相手の話題に対して積極的に耳を傾け、共感を示すことで、相手は自分を理解してくれると感じ、心を開きやすくなります。
さらに、先手を打つ際にはポジティブな態度が不可欠です。自信を持って明るく振る舞うことで、相手に好印象を与え、関係の良好なスタートを切ることができます。また、相手に対して感謝の気持ちを示すことも効果的です。謙虚さと感謝の気持ちを持ち合わせることで、相手との絆をより深めることができます。
先手を打つことで相手の心を開き、やがては相手からの働きかけが始まるということは、人間関係において大切なポイントです。自らが率先して行動し、相手に良い印象を与えることで、良好な関係を築くことができます。先手必勝の精神を持ち、対人関係を築く際には、自らが積極的に動き、相手とのコミュニケーションを大切にすることが肝要です。
0

すべては移ろっていく
こんにちは。
いつも
ありがとうございます。
時代は移ろい変わっていく。
ついさっきなんですが
テレビのニュースを
聞くともなしに聞いてたら
こんな言葉が流れてきました。
「これで
明治生まれの男性は
いなくなりました」
えっ!
と
この初めての言葉に
思わず
テレビの方を振り返っちゃいました。
「いなくなりました」
という
言葉の響きのドキっと感。
ネットで調べたら
先月に
国内最高齢の男性が
112歳で亡くなられ
110歳の方が
最高齢男性になられたそうで。
いや~~
なんだろう~
なんか
時代が移り変わってくのを
とっても感じて。
寂しさのような
驚きのような。
もちろん
すべては移ろい変わっていくわけで。
生まれれば
いつかは
いなくなっていくし。
今あるものだって
いつかは
なくなっていくだろうし。
そうなんだけど
でも
確実に
時代は進んでいるというか
人も入れ替わるというか。
「えっ、じゃあ・・・」
と思い
江戸時代生まれの最後の方は
いつだったんだろうと調べたら
1976年とのこと。
時代も
人も
移ろっていく。
移ろいながら
令和時代を生きていく。
0
.png)
自分を好きになる
こんにちは、ユウ_Yuです。
みなさんは自分のことが好きだと言えますか?
・大好きだと言える人
・嫌いだとハッキリ言える人
・好きなところもあれば、嫌いなところもあるという人
答えは色々あると思います。
なぜ今回はこのようなテーマにしたかというと、クライエントさんから、自分のことが好きになれないというご相談にのることがよくあるからです。
その理由を聞いていくと、「自分に自信が持てない」と話されるクライエントさんがたくさんいらっしゃいます。
過去とどう向き合うかが重要
なぜ自分に自信が持てないのかを聞いていくと、過去の体験を話されます。
・親の方針で、選びたくない進路を選ばざるを得なかった。
・部活で、怪我をしてレギュラーに入れず、挫折した。
・受験で失敗して、第一志望ではない学校に行った。
・経済的に貧しくて、子供の頃はいい思い出がない。
・家族関係が悪く、いつも親の機嫌を伺っていた。
クライエントさんはそれぞれの置かれた環境のなかで、とても辛い想いをされてきたことを打ち明けてくださいます。
過去の体験は今の自分を形成するうえで、とても重要なパーツのひとつです。
過去を振り返り、過去から学び、そして、これからに活かしていくことは、これからよりよい人生を歩むために必要なことです。
しかし、過去にこだわり過ぎるのは、いいことではないと私は思っています。
なぜなら、私も、クライエントさんも、これを読んでくださっているアナタも、生きているのは過去ではなく、『今』だからです。
『今』を生きる
当たり前かもしれませんね。
でも、当たり前だからこそ、忘れがちなんです。
生きているのは『今』、
0

現在は贈り物「present」
こんにちは。
いつも
ありがとうございます。
先日
ある本を読んでたら
過去・現在・未来の英訳が出てきました。
それぞれ
past・present・future。
で
ふと
おもしろいな~と思ったのが
現在=present。
今現在という時はプレゼント。
贈り物だよってことです。
宇宙からの贈り物。
神様からの贈り物。
プレゼント
ありがとう~。
さらに
語源を調べてみたら
なるほど~って感じで。
「pre」って
「あらかじめ」とか「前もって」
っていう意味。
「sent」は
「渡す」「贈る」sendの過去形。
つまり
「present」=「前もって贈られていたもの」。
じゃあ
誰から
前もって贈られていたのか?
はい!
過去の自分からですね。
過去に
自分が選択して
その行動を取った結果が
今現在ということ。
その今現在が
「present」。
深いね~~~。
過去の
自分の選択のプレゼントが
今この現実。
あなたはどうでしょう?
今が
自分の望むようなものであるかもしれないし
まったくそうじゃないかもしれない。
これまでは
これまでとして受け入れて
大切なのは
未来の自分に
どんなpresentを贈ってあげるか?
ですよね。
最高のpresentを贈るためには
最高のpresentを贈れるように
選択をしていけばいいんです。
人生は選択の連続
って
よく聞く言葉ですね。
もちろん
すべてに対して
完璧にベストな選択なんて
できないだろうし
それを目指さなくてもいい気がします。
自分の心が楽しくなるような選択。
これを心がけていれば
おのずと
未来の自分に
楽しいpresen
0

我慢を手放して人生軽やかに・・・
初めまして!まさとしです。この度はまさとしの「我慢を手放して人生軽やかにしていくブログ」を見ていただき、大変ありがとうございます^^あなたとのご縁を持てたことに本当に心から感謝いたします。ところで、あなたは、これまで【我慢】ということを多かれ少なかれしてきたのではないでしょうか?幼いころから・欲しくても我慢しなさい・我慢は美徳・自分が我慢すれば、周りは丸く収まるみたいなことを体験したことがあったかと思います。ちなみに何を隠そう、こういったことを僕は幼いころから経験してきました。その体験談を少しお話します。僕は3人兄弟の長男として生まれました。幼少期から・お利口さんにしてないと怒られる・弟とケンカしてもお兄ちゃんなんだから我慢しなさいみたいなことをたくさん経験してきました。そして、いつのまにか親に、親族に怒られないように【僕が我慢すれば収まるんだ】という考えが刷り込まれた状態になっていました。そんな状態で幼稚園に入園し、同級生とケンカしたりしても、段々歯向かえず、そこからいじめがエスカレートしていきました。上履きを隠されたり、靴を隠されたり、粘土を盗まれたり・・・。同級生からしたら、なにも文句や歯向かいなどをしないから格好の標的として扱いやすかったのでしょう。毎日泣いて、幼稚園から帰ってきたのを今でも覚えています。でも、泣きながら帰ってきて母親や祖母に話しても返ってくる言葉は・男の子なんだから泣かないの!・それくらい我慢しなさい!という言葉だけでした。そんな幼少期の小さな小さなまさとしは、小さいなりに・我慢すればいじめられないんだって思っていたんだと思います。そうして月日が流れて
0

寛容でいきましょう
こんにちは。
いつも
ありがとうございます。
3月いっぱいで終わった
TBSのドラマ
『不適切にもほどがある』。
イマノリと同じ昭和世代には
かなり楽しめたドラマだったと思います。
毎回
ミュージカルのように
歌って踊るシーンがあるんですが
最終回では
「寛容になりましょう」と
みんなで歌いながら踊っていました。
これ
今の時代の
キーワードなんじゃないかな~と。
寛容って言葉
調べてみたら
「心が寛大で
よく人を受け入れること」
「過失をとがめたてせず
人を許すこと」
こんなふうに出てきました。
簡単に言ってみれば
広い心で
相手を受け入れ
許すこと。
こう見ると
まさに人間力だな~と思います。
簡単そうで
なかなかできないことですよね。
ついつい
自分の都合のいいように
相手を変えようとしちゃう。
違いを認められなかったりね。
どうしても許せなかったり。
で
相手に対しての寛容も大事なんですが
自分自身に対しての寛容
これも重要なポイントだと考えます。
過去の出来事を受け入れて許す。
これまでの自分を認めて受け入れる。
「今までよくがんばって来たね~」って
自分にOKを出してあげる。
これができると
自分がとってもラク~になって
周りに対しても
心の余裕が出てきます。
そう
寛容になります。
イマノリ
接客業をやってた時にも
感じてたんですが
意外にも
ある程度歳を重ねた人に
寛容じゃない人が多かったりするんです。
ちょっとのことで
ビックリするくらい怒ったりね。
広い心。
余裕のある心。
違いを楽しめる心。
こういった心を持つことが
人間力なんだと思いますね。
周りにも
0

今日も自分らしく
ほぼほぼ直感で生きてます!こんにちは。結心です。今年に入って、プライベートで色々とありまして、久しぶりの投稿になってしまいました(^-^;昨日はイベントに参加しており、電話待機もあまりできなかったので、今日は午前中からの待機予定でしたが、急遽予定を変更!今朝も直感が働き、早速行動に移し、そのおかげで充実した時間を過ごすことができました。今朝は、桜🌸満開のこの季節に、ご近所さんのママ友と久しぶりに連絡を取りたくなり、迷わずLINEしたのです。彼女も働いているのでどうかな?と思ったいたら、まさかのすぐに既読‼やったー!ヾ(≧▽≦)ノこれは何かのご縁ね!「今日仕事休み?」「うん、休みだよ!」「もし午前中、時間空いていたら、近くの公園でお花見がてらおしゃべりしたいんだけど、どうかな?」「うわぁ!ありがとう。いいね!」てな感じで、着々と決まり、久しぶりの再会になんだかワクワクと照れと、微妙な心境(#^.^#)私と彼女は10年以上のお付き合いで、着かず離れずの仲です。年に数回、どちらともなくLINEで連絡を取り合い、お互い近況報告している間柄。彼女から数年前に離婚することを打ち明けられ、そのことで話を聞いてあげていたことも何度かありました。彼女はとても芯の強い女性だということを、私は以前から知っています。だからきっと大丈夫だと思って静かに見守っていました。久しぶりに会ったけど、今もそれは変わってないなぁ。彼女は優しく、そして心が強い!「かっこいいなぁ…。素敵だわ」私は彼女に直接そう伝えました。お互いのプライベートなさまざまな分野の話もゆっくりできて、元気とパワーをいただいて帰ってきました。
0
.png)
人は、いつ死ぬかわからない。 朝起きて今日も命があったと思う。 だから、今日、精一杯生きる。
みなさん、こんにちは。全国的に、素晴らしい天気のようですね。どこかへお出かけされている方も多いでしょう。また、入学式が終わり、明日月曜日から、通常の生活が始まりますね。新社会人のみなさんも、これから通常の勤務が始まります。今のうち、羽を伸ばし、素敵な一日にしてくだいね。今日は、”人は、いつ死ぬかわからない。朝起きて今日も命があったと思う。だから、今日、精一杯生きる。”(イタリアの有名な政治家の言葉です。)最近、なんだか全国的に、大きな地震が相次いでいますね。私も、東日本大震災の被災地でした。不幸中の幸いで、私が住んでいる地域は、大きな被害はありませんでしたが、2日間停電が続いたときは、さすがに不安になりましたね。がその3.11以降、次々のいろんな災害が発生し、さらに、前代未聞の新型コロナウイルスがパンデミックになり、いろんな企業が倒産していきました…だんだんとこのような事態が年々増加し、そして加速しているような気がします。私は、ここで何が言いたいのかというと、「とにかく、今日精いっぱい生きる」ということです。私たちは、いつか必ず臨終を迎えます。この世に生まれてきた以上、必ずあの世へ行く。人の命は儚いです…明日、私たちの人生で、何が起こるかわかりませんよね。むしろ、今、何が起こるかわかりません。ただ、明日があるから…めんどくさいから、明日頑張ればいいや…この気持ち、今すぐやめましょう。ある余命を宣告された、50代で肺がんを発症し、数年前に亡くなった女性がいました。その方は、仕事にやりがいを感じ、某コンビニを数店舗経営していたビジネスウーマンでした。そんな矢先、病気を発症。そして、
0
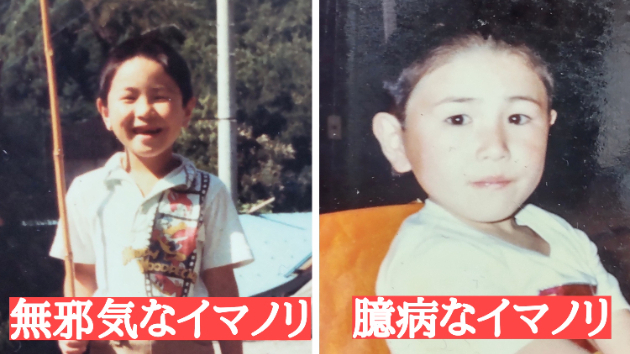
子供の頃の写真に、自分を知るヒントがある
こんにちは。
いつも
ありがとうございます。
先週なんですが
2年ちょいぶりくらいに
実家に帰りました。
イマノリ
山の中で生まれ育ったので
大自然が恋しくなっちゃうんですよねぇ。
樹々の中に
ぽつんと自分を置いてみると
大自然に圧倒されて
クラ~っとしてくる。
東京とはケタ違いの
人口密度の低さ。
何回も深呼吸したくなります。
大自然に触れるのも
楽しみの一つなんですが
これも楽しみなんです。
昔の写真を見ること。
高齢の父ちゃん母ちゃんと
これはいつの写真だ
とか言いながら
回し見をする。
それと共に
自分の根っこにある
自分を探すんです。
例えば
イマノリの場合。
無邪気に笑ってたり
人を笑わせたりしてるのもあれば
反対に
すごい神経質そうな
何かにおびえてるような
慎重で臆病な自分なのもあるんです。
で
4年くらい前までは
この
神経質で臆病な自分が
自分の中で優勢だったんです。
思い切れなかったり。
心配や不安の面ばかり見てたり。
臆病だから
怒って人を寄せ付けなかったり。
でも
自分と向き合う中で
根っこの根っこにあるのが
無邪気な自分だ
ってことに気づけたんです。
そしたら
ま~なんと
自分自身がラクになったことでしょう。
子供のように
いつまでも無邪気でいいんだよって。
自分が楽しくなること
自分がワクワクっとすることを
やっていけばいいんだよって。
こんなふうに
自分に許可というか
OKを出せたんですね。
今では
自分の中で
無邪気な自分が
ほとんどを占めています。
いつまでも子供だっていいよねぇ。
自分の
子供のころの写真を見てみる。
自分の根っこにある
自
0

体の姿勢が、心の姿勢を決めていく
こんにちは。
いつも
ありがとうございます。
全国各地
桜開花から
いよいよ満開の時期になってきましたね。
とは言うものの
東京の今年の桜は
いつもとは
ちょっと違う感じです。
ドバーッと感がないと言いますか。
同じ木でも
つぼみのままの部分があったり
また木によっては
すでに
3月中に満開になったものがあったり。
まあそれでも
やっぱり春ってのは
気分がいいですね。
なんで気分がいいのか?
もちろん
たくさんの花たちが咲いていく
ってのがありますよね。
個人的に
今年目立つのが
チューリップだと感じていて。
特に
赤色のチューリップ。
赤がね
ほんと赤なんですよ。
くっきりと鮮やかに赤。
他にも
大小
たくさんの花が咲いてますよね。
これだけでも
気分がいい。
そんでもって
これをするから
気分がいいんだと思います。
それは
見上げるから。
桜とか桃の花あたりですかね。
人って
見上げながら落ち込むことって
意外にもできないんですよね。
今度
試しにやってみて下さい。
だからね
どんどん見上げていきましょうよ。
桜もそうだし
空
雲
月
星たち。
体の姿勢が
心の姿勢を変えていく。
下ばかり向いていれば
心も下を向いちゃう。
なんかあったら
見上げてみる。
一日の終わりの帰り道で
見上げてみる。
すると
その日一日に
感謝したくなってくる。
今日の自分を
ホメたくなってくる。
体は
心とつながっているのであります。
0

夢の実現、目的達成の為のスキル
こちらのスキルはコーチングに限らず多くの場面でよく使われるスキルで、その過程で一番初めに決める事がゴールです。ゴール設定一番わかりやすいのは出かける時にまずはどこに行こうかと考えますよね。目的地が決まるとそこまでの道順を考え徒歩で行くのか電車で行くのかを考えて行動していきますよね。そのような感じでセッションの時にはクライアントが解決したいテーマを質問します。コーチングの場はどういう所かと言いますと、普段考えないような事を質問します。NLPの考え方に空白の原理と言うものがあり、それによって答えが分からないと分かるまで、潜在意識がいつまでも探し続けます。そこに思いもよらない気づきがあったります。これが自問自答では得る事が出来ないメリットですね。ココナラのカテゴリに生きがい、やりたい事を探すというカテゴリーがありますが、そのようなクライアントが来られた場合は、まず初めの質問をするとすれば「どんな自分でありたいですか?」と質問します。これはあるべき姿では無く、あなたの本当はこうありたい姿にフォーカスしていけば、あなたのやりたい事が見つかるかもしれません。それは子供の頃にやりたかった事かも知れないし、未来に向かって行く過程で見つかるかもしれません。コーチングの場では直感を大事にしております。あなたのその時の直感はなんと言っているのでしょうか?何かをするのに年齢は関係ありません。私のよく知っている警備員の仲間に55歳にしてやっぱりやりたかった夢に向かって行きたいという人が警備に転職してきました。彼は前は結構いい企業にいて、こっちにきて年収が半分になったと聞きました。その人も少しずつ役者とし
0

誰だって、新人の頃があった
こんにちは。
いつも
ありがとうございます。
朝の電車。
新入社員の方たちが
あちこちに。
その周りには
たくさんの会社員の方たち。
みんな様々な年齢。
よく考えてみれば
みんなそれぞれ
新人の時があったわけで。
緊張の初出社。
わからないことだらけの不安。
ミスしてしまって落ち込む。
人間関係の気疲れ。
怒られないか気をもむ。
誰でも最初は
こういう道を通って来たんじゃないかなぁ
と思います。
自分が新人の頃のことを
思い出してみれば
新入社員の人に
職場の人に
やさしくできるはず。
緊張をやわらげてあげたり
「わからなかったら
遠慮なく聞いて」と
声をかけてあげたりね。
怒ってビビらせる
みたいな
昭和な方法は
もうないんじゃないでしょうか。
自分の新人の時を思い出して
相手を思いやる。
自分にとっての当たり前を
相手にとっても当たり前だと思って
接してしまったり。
自分がかつてされて
イヤだったことなのに
同じことを相手にしてしまったり。
こういったことを
人はつい
やってしまう。
かつての自分を思い出して
新人の方を
相手を思いやる。
最初からできる人なんて
一人もいないのであります。
0

とにかく自分をホメていこう
こんにちは。
いつも
ありがとうございます。
人って
ほっとくと
自分のダメなとこ
できてないとこばかり見ちゃうでしょ。
でもって
「自分て
なんてダメなんだろう」
って
心の中で思っちゃう。
心の中で思うってことは
その思ってるコトバを
自分に投げかけてるということ。
「自分はダメ」
って
自分に言い聞かせてるようなもの。
これじゃあ
自信もなくなっていくし
気分も落ち込んでいっちゃいますよね。
だから
意識して
自分のできてるとこを
自分の良いとこを
見ていくようにする。
例えば仕事で。
昨日教えてもらったこと
今日はちょっとでもできてる自分。
わからないことを
わからないままにせず
ちゃんと誰かに聞けてる自分。
あいさつをちゃんとできてる自分。
ちゃんと仕事に行けてる自分。
もうほんと
ささいなことでいいんです。
できてる自分を
いっぱい見つけてみて下さい。
そして
そのできてる自分を
いっぱいいっぱい
ホメてあげて下さい。
ホメられれば
うれしくなるのが
人ってもの。
うれしければ
毎日が楽しくなる。
毎日楽しい自分でいれば
仕事だってなんのその。
変化の多い4月。
ちょっとでも
できてる自分を見つけて
その自分を
めちゃんこホメることを
心がけていきましょうね~。
0

新年度、とにかく毎日を楽しんでいこう
こんにちは。
いつも
ありがとうございます。
今年は
新年度のスタートが
月曜日ですね。
日曜日明けの
新しい職場
新しい環境って人も
いるんじゃないでしょうか。
不安。
ドキドキ。
心配。
イヤだな~。
行きたくないな~。
もし
もしですよ
ほんとにほんとにイヤでイヤで
ホントにホントにホント
行きたくないんだったら
そのことを正直に伝えて
行かなくてもいいと思います。
イマノリ
23歳くらいの時だったかな~
日曜の夜10時から
コンビニの夜勤の仕事があったんだけど
それこそ冗談抜きで
サザエさんを見てたら
マジで行きたくなくなっちゃって。
「やめます」って
すぐに連絡して
やめたことがありました。
まあ
これは最終手段として
朝出かける前に
「よし!今日を楽しもう!」
って
自分に声かけしてみて下さいね。
とにかく楽しんでいきましょうよ。
にこやかに
やわらかく。
できないこともあるし
ミスだってするかもしれない。
それだっていいじゃない。
OKOK~~。
いろんな人の力を借りちゃえばいい。
ちゃんと感謝すればOKでしょ。
頑なに張るの「頑張る」より
顔を晴れやかにの「顔晴る」を
心がけていきましょうよ。
明けない夜はない。
止まない雨はない。
春の来ない冬はない。
自分で
うまく気持ちを切りかえながら
新年度
新しい場所で
それぞれの場所で
ニッコリ楽しんでいきましょうね~~。
0
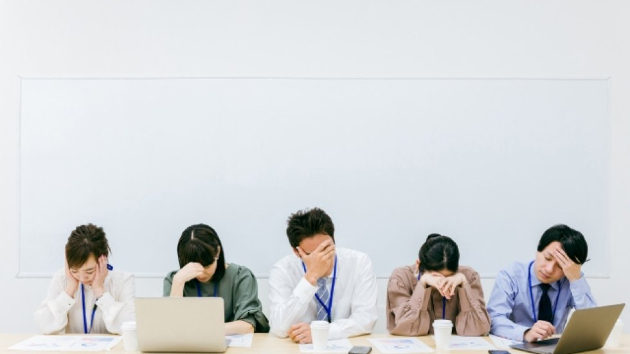
人は、いつもと同じをくり返す
こんにちは。
いつも
ありがとうございます。
遅ればせながら
先日
映画『PERFECT DAYS』を
観に行ってきました。
カンヌ国際映画祭で
主演の役所広司さんが
最優秀男優賞を受賞した作品です。
公衆トイレの清掃員
主人公「平山」の毎日を描いています。
二階の部屋で眠る「平山」。
ご近所さんが
竹ぼうきで外を掃く音で目覚め
布団をたたみ
一階に行って
歯を磨き
ヒゲを整え
顔を洗い
霧吹きを持って
二階へ。
育てている植物たちに
水をやり
つなぎの清掃着に着替えて
一階へ。
玄関で
財布や鍵など
順番に取って
外に出る。
自販機で飲み物を買い
車に乗り込む。
お昼は
いつもの神社で
サンドイッチとパック牛乳。
仕事を終え
銭湯に。
そのあと
浅草の地下の飲み屋へ。
家に帰って来て
布団の上で本を読み
眠りにつく。
くり返しの毎日。
自分だけの決められたルール。
変化のないことへの安心感。
私たちの日々の生活も
部屋のどこかにカメラを置いて
撮影してみれば
この「平山」と同じようなことを
してるんでしょうね。
朝の飲み物一つ取ってみても
いつも同じ自販機で
同じ缶コーヒーだったりね。
いつもと同じってのは
無意識にできちゃうので
ラクちんです。
考える必要もないし。
でも
同じことのくり返しがつまらない
と感じる人もいるわけで。
イマノリも
感じちゃう方。
なんか
もっと楽しくしたくなっちゃう。
いつもと同じを
自分で意識して
変えていく。
いつもと違うを
選んでみる。
いつもと違う缶コーヒー。
いつもと違う道。
いつもと違う時間にジョギング。
いつもと違う食べ物。
いつも
0

人はみんな、メガネをかけている
こんにちは。
いつも
ありがとうございます。
新宿駅。
いい言葉に
思わず立ち止まる。
『その感情に反射して
目の前が色づく。』
LUMINE(ルミネ)の広告。
今。
あなたの目の前は
色づいているでしょうか?
自分の気持ち次第で
世の中が違って見えてくる。
うれしい気持ち。楽しい気持ち。喜びの気持ち。こんな時は
世の中も
うれしい
楽しい
喜びいっぱい。
悲しい。
つらい。
寂しい。
こんな時は
世の中の何を見たって
悲しい
つらい
寂しい。
だから
できるだけ
自分の気持ちを
楽しくしておく。
マイナスな気持ちになってたら
ニコッと笑ってみる。
空を見上げてみる。
自分へのコトバを変えて
自分を喜ばせてあげる。
人はみんな
感情というメガネをかけて
世の中を見ている。
もし
そのメガネがくもってしまったら
自分で
キレイに拭いてあげればいい。
でもまた
くもったり
汚れたりする。
それでいい。
そのつど
自分でキレイにしていけばいい。
0

世間の人たちは自分が思っている以上にあなたに興味がない。人の興味は常に移り変わっていくもの。気にしないことが大切!【アラフィフ心理カウンセラー「うさぴょん」のココナラ電話相談
世間の人々が、自分が思っている以上に興味を持っていないことは、時折痛いほどに実感します。ソーシャルメディアや日常会話の中で、自身の関心事について熱心に語っても、相手がそれに全く関心を示さないことがあります。しかし、このような状況に嘆くのではなく、人々の興味は常に移り変わるものであることを理解し、それに気にすることの重要性を考えるべきです。
人の興味は常に移り変わるものであり、それは自然なことです。新しいトピックやテーマが現れ、人々の関心を引きつけます。時には、一つの話題が一過性のブームとして現れ、次々と新たな関心事が生まれます。このような状況下で、自分の興味が他人に共感されないことは、必ずしも個人の価値や興味の対象の価値が低いということではありません。むしろ、それは多様性のある社会において、異なる人々が異なる関心を持ち、多様性が生まれる一因とも言えます。
では、人の興味が移り変わることに対して、どのように対処すべきでしょうか?それは、自分自身を認識し、自己価値を育むことが重要です。他人の興味が自分の関心事と一致しない場合でも、自分の興味や趣味を大切にし、それを追求することが大切です。自分の内面的な充実感や満足感を追求することが、他人の興味に左右されずに生きる秘訣です。
また、他人の興味が移り変わることに過度に気を取られることは、自分自身の成長や幸福を阻害する要因となります。他人の興味が自分の関心事と一致しないことに悩むのではなく、自分自身の目標や夢に向かって進んでいくことが重要です。他人の視線や承認に囚われず、自分の人生を自分のルールで生きることが、真の充実感や幸福を得る鍵とな
0

あなたの使う言葉で、あなたの顔はできている
こんにちは。
いつも
ありがとうございます。
先日
ある男性政治家の会見が
ニュースで流れていました。
一人の記者からの質問に
その政治家は
こんな言葉で答えてました。
「お前もその歳、来るんだよ。
バカヤロウ」
もうね
イマノリ
腹立たしさはもちろんのこと
それを通り越して
寂しくなっちゃいました。
なんの学びもしてない。
生きるとか
人間についてとか。
人生から
なんも学んでいない。
人に対して
バカヤロウって言ったことあります?
周りを笑わせるために
ツッコミ的に言う場合はあるかもですが
いや~
ないですよね~。
相手に対して
「お前」
とか
「バカヤロウ」
なんて言葉を
もし使ってたら
心を作り直した方がいいですね。
そんな言葉を使ってたら
おそらく
毎日はつまらないだろうし
笑顔もないだろうし
幸せなんて
もちろん感じられないでしょうね。
事実
この政治家の顔を見れば
一目瞭然です。
毎日つまらなそう~~~。
あなたがよく使う言葉で
あなたの顔つきが作られていく。
ありがとうを
毎日たくさん言ってる人は
にこやかで
おんわりと穏やかで
やわらか~な顔です。
当然
そういった人のところには
たくさん人が寄ってくるし
いい事も寄ってくる。
何もなくたって
毎日を自分で楽しくできちゃう。
感謝いっぱいの方がいいのは
言うまでもないことですよね。
ちなみに
この政治家さんは
85歳だそうです。
どんなに
学歴が高かろうと
地位名誉があろうと
お金があろうと
周りの人への
思いやりの心と
感謝の心がなければ
毎日は楽しくなっていきません。
人生が
無味乾燥とした
殺伐なものにな
0

生き方。
20日と22~24日は天使預かりデー。合間、ココナラ。25日は朝8:30~娘宅で天使のお世話。11:00~高校時代の友人とランチ。15:00~30年ぶりに集う友人達にリモート参加16:00~美容院19:30~ココナラ目まぐるしい予定だったが無事終了。そこで思ったこと。まずは天使。1歳2か月になった彼は歩きまわり自我の表現から見ても、しっかり「人間」になっていた。彼の中での大好きランキングはジジがぶっちぎりトップ。ママよりパパよりババよりもジジが好き。そのジジ(私の現夫)と彼は、血の繋がりはない。そんなことを知る由もない彼はきっと、ジジの愛情を肌で感じている。ちょっとジェラっちゃう時もあるけれどおむつ替え・お着替え・その他のお世話全てイヤイヤ期に突入した彼に手を下すのはママや私。助けを求めて深まる絆。そしたらパパでもいいんじゃない?とも思うが、生活とお泊りは違う。現に25日、娘宅で寝起きの彼にサプライズ登場をしてみたら我が家でジジにしている大好き行為の全てを私に向けてきた。正直「可愛い~~~~!!!!」分かってるんだよね。その場で一番自分を守ってくれるであろう人を即座に判断。「人間」になったんだなーと感慨深いものがあった。でも、そんな中でうろたえもしない娘。「他に目が入ってくれてると楽~♬」という肝が据わった態度に何よりも感心した。高校時代の友人。彼女は現在有給消化中。同じ会社で7歳下の男性と再婚、子供なし。東京から福岡への旦那さんの転勤に着いていくことになった。お別れ会的なランチ。もともと子供のいない彼女は基本、働いて生きてきた。故に「退職=無収入」に対する恐怖感に苛まれている
0

こころのなかが不安でいっぱいなあなたへ
こんにちは、ユウ_Yuです。
漠然とした不安に悩まされることってありませんか?
私はしょっちゅうあります😓HSPさんや繊細さんによくあることかもしれませんね。
でも、具体的になにが不安かと言われると、将来?お金?仕事?健康?など、色々と思い浮かびはしますが、明確には分かりません。
もしも、こんな不安がいつもこころのなかを支配しているのなら、人生はとても苦しいものになってしまいます😣今回は、不安との付き合い方についてシェアしていきたいと思います。
不安との付き合い方が身につけば、ものの見方も変わって、生きやすくなる。
ぜひ最後までお付き合いください。
不安は決して悪い物ではない
今まで不安に悩まされ、色々な本やセミナーで勉強してきた人はすでにご存じかもしれませんが、そもそも不安というのは悪いものではありません。
不安は身の危険を察知し、自分自身を守るために必要な感情です。
遠い昔の人たちは、この不安の感情があるからこそ、猛獣などから身を守り、生き残ることができたんですね。
でも、理屈では分かっていても、不安は不安ですよね。
気付いたらこころが不安でいっぱいなんてことは私もしょっちゅうあります。
頭では分かっていても、こころは分かっていないんです。
でも、ここで知っておいてほしいことは、「行き過ぎた不安は害を及ぼす」ということです。
では、どうすればいいのか?
正しく不安になることを身につける必要があると私は思っています。
不安との上手な付き合い方・考え方を手に入れる
まずは不安を抱いている自分に気付くことが必要です。
気付かなければ、不安にマインドコントロールされ続けてしまいます
0

わたし、高校の卒業式でてません
私は、
自分の高校3年生の時期を
暗黒時代全盛期と
呼んでいる(笑)
高校3年の時のクラス替えで
仲のいい友達とは
バラバラになった💦
新しいクラスで気の合う友人もできず
休み時間はほとんど机で一人で
座っているか寝ているかだった😢
クラスの人に心を開くことなんてなく
学校で感情をだすことなんて
全くなく、学校でも家でも
感情を無にしていたΣ(゚д゚lll)ガーン
ただただこの時間が過ぎればいいと
だけ思っていた😨
卒業式に出るのも嫌で
わざと卒業式に入試試験日が重なる
短大の受験をした😂
だから高校の卒業式はでてない
嫌で苦痛で学校辞めたいって
何度も思ったけど、やっぱり親には
心配させるから言えず
感情押し殺してただただ無にして
通学してた💦
「自由に生きたい」
思えばその頃から
ずっとそう思ってた👋
私は星詠みで自分を知るまでは
そういう自分の心の奥底にある
感情に蓋をしていた
星詠みで自分を知って
「あ~そうしたかったな」と
思い出せた👌
ずっと我慢したり
当たり前のように自分の感情を
押し殺していると
本当は自分がどうしたいかわからなくなる💦
だから、まずは思い出してほしいんだ🌈
あなたは本当はどうしたいんだろう?
親がどう思うとか、周りからどう思われるかとか
常識や世間体とか、一切無視して考えたとしたら
あなたは本当はどんな風に生きたい❓
わからなければ
まずは自分を知ろう♪
あなたの魂が望んでいる生き方を
教えます☆彡
0

今ある現実がすべてではない。どうしようもなくなった時は、すべてをリセットしてやり直せばいいだけ!【アラフィフ心理カウンセラー「うさぴょん」のココナラ電話相談
現実が厳しいと感じるとき、私たちはしばしば自分の周りに閉じこもり、希望を見いだせない日々に囚われてしまいます。しかし、私たちの人生には、常に「リセットボタン」があることを忘れてはなりません。すべてをやり直すことができる可能性が、私たちの心の中に常に存在しているのです。
何かがうまくいかないと感じたとき、リセットボタンを押すことは、新しい可能性を開く第一歩です。これは単なる逃避行為ではありません。むしろ、自己成長と前進のための積極的な行動です。リセットは、私たちに過去の過ちから学び、新しい方向への勇気を与えます。
しかし、リセットは簡単なことではありません。それは自己省察と決断のプロセスを伴います。自分の価値観や目標を再評価し、本当に望む未来を描くことが必要です。そして、その未来を実現するために必要なステップを踏み出す勇気が必要です。
リセットはまた、周囲のサポートや資源を活用することも重要です。友人や家族、専門家の助言を求めることで、新たなスタートを切るための力を借りることができます。誰もが一人ではありません。私たちはお互いを支え合い、共に成長することができるのです。
さて、リセットは一度行えばそれで終わり、というものではありません。人生は変化し続けるものです。新たな挑戦や困難に直面したときには、またリセットボタンを押すことができます。それは、私たちが成長し、進化し続けるための永遠のプロセスなのです。
現実がどんなに厳しい状況にあっても、リセットボタンを押すことで新たな道が開けます。過去の失敗や不安に囚われるのではなく、前向きに未来を見据えましょう。リセットは私たちに、常に新た
0

成功者の定義はときに曖昧だが、確信を持って行動すれば、現実は音をたてて動き出す!【アラフィフ心理カウンセラー「うさぴょん」のココナラ電話相談
成功者の道は、時に曖昧で見通しが悪いように思えることがあります。何をもって成功とするかは人それぞれであり、その定義は一概には言えません。しかし、ひとたび確信を持って行動を起こすならば、現実はまるで鼓動のように音を立てて動き出すものなのです。
成功を求める人々は、時に不確かな未来を前に不安を感じることがあります。しかし、確信を持って行動することで、その不確かな未来を自らの手で切り拓くことができるのです。確信は、希望の光であり、行動はその光を現実に変える力なのです。
成功者とは、単なる目標の達成者ではありません。彼らは確信を持って自らの夢を追い求め、途中で挫折や困難に直面しても諦めることなく前進する人々です。彼らは行動の力を信じ、その力を日々の生活の中で実践し続けることで、成功への階段を上っていくのです。
確信と行動には、不可分の関係があります。確信がなければ行動は力を持ちませんし、逆に行動がなければ確信もただの幻想に過ぎません。成功への道は、確信と行動の相乗効果によってのみ開かれるものなのです。
成功を手にするためには、自らの心の声に耳を傾け、その声が示す方向に向かって確信を持って進むことが重要です。そして、その確信を元に行動を起こし、一歩ずつ前進することで、成功への道は必ず開けてくるのです。
さあ、今こそ確信を持ち、勇気を持って行動に移す時です。未知の世界への挑戦は恐れることではありません。むしろ、それが成功への扉を開く第一歩となるのです。確信と行動を武器に、自らの人生を輝かせる旅に出ましょう。成功は、あなたの手の届くところにあります。
0

【人間関係改善】温良恭倹譲で周囲から信頼される人になる
おはようございます。きょうは40代から60代に知っておいてほしい言葉です。温良恭倹譲(おんりょうきょうけんじょう)職場、とくに中小企業のトップ、家族経営の経営者などは、時に強引で大声をあげて叱咤激励。そんな昭和の時代は終わったのに、まだ少し生き残っているようです。令和の時代に求められる孔子の教え「温良恭倹譲(おんりょうきょうけんじょう)」という言葉をご存知でしょうか。これは、孔子の教えである「論語」から生まれた言葉であり、「温和で優しく穏やかに、人を敬ってつつましく応対すること」という意味です。孔子が人と接するときの態度を指す言葉として、古くから大切にされてきました。現代社会は、情報化社会、グローバル化社会と、目まぐるしく変化しています。そんな時代だからこそ、私たちは改めて孔子の教えである「温良恭倹譲」の重要性を認識する必要があるのではないでしょうか。50代前後こそ温良恭倹譲を意識すべき50代前後になると、人生経験も豊富になり、社会的地位も高まってくる人が多いでしょう。しかし、同時に、傲慢な態度をとったり、大声で自分の意見を押し通したりする人も見受けられます。しかし、令和の時代において、そのような態度は時代遅れです。求められているのは、温良恭倹譲の精神に基づいた、謙虚で誠実な態度です。温良恭倹譲を実践することでは、具体的にどのように温良恭倹譲を実践すればよいのでしょうか。以下に、いくつかの例を挙げます。温和で優しく接する: 相手に配慮し、思いやりの気持ちを持って接しましょう。謙虚な姿勢を忘れない: 自分の意見を押し付けず、相手の意見にも耳を傾けましょう。誠実に対応する: 常に誠
0

自分でちゃんと選ぶ
こんにちは。
いつも
ありがとうございます。
『正解はない。
大切なのは、
自分で選ぶことだ。』
これは
転職サイトdodaの広告コピーです。
う~ん
いい言葉。
例えば
友達とご飯を食べに行ったとします。
メニューを見ながら
何食べようかな~と思ってたら
その友達が
自分の分まで
どんどん選んで注文していきます。
まあいいか~と思いながら
料理を待ちます。
で
やって来た料理。
どうなんだろうと思いながら
食べてみる。
微妙~~~。
ていうか
自分にとってはイマイチ~~。
いや~
ちゃんと自分で頼んでおけばよかった~。
人生。
誰かに
こうしなさいと言われて
そうしてみた。
そしたら
全然おもしろくないし
むしろ
苦しいことが多くなった。
こうなったのは
あの人のせいだ。
しっかり意識して
自分で選ぶ。
でないと
人は後悔するし
周りの人や
周りの環境のせいにしてしまう。
もちろん
どれが一番いい選択なのかなんてわからない。
いい人生ってのも
人それぞれに違うし。
それでも
ちゃんと自分で選んでいく。
一番いいのを選ぼうと
カチコチにならずに
よりいい方を選ぼうと
やわらかい感じでいく。
ちゃんと自分で選べば
結果がどうであれ
自分の責任だと納得して
受け入れることができる。
後悔も少なく
はい次っ!
て感じで
切りかえることもできる。
自分の気持ちが
楽しくなる方を選んでいく。
これを心がけていれば
それがある意味
正解なんだと思う。
0

いろいろでいい、いろいろがいい
こんにちは。
いつも
ありがとうございます。
今日
髪を切りに行った
イマノリ。
最初
お客は自分一人でした。
少ししたら
かなり若い感じの女性が来ました。
その女性と
スタイリストさんのやり取りを
聞くともなしに聞いていました。
どうやら
4月から社員で働くので
黒にカラーリングしに来たみたいで。
鏡越しにチラッと見ると
確かに
明るめな茶髪。
「そうか~
まあ
社員じゃ
髪色も仕方ないか~」
と
心の中でイマノリ。
もうちょっとして
かなり若い女性が来店。
「カラーとトリートメントで」
とその女性。
常連さんらしく
担当のスタイリストさんとも仲良さそうで
声もかなり大きめ。
「仕事が始まるんで
長持ち系の黒で」
「いや~
そうなんだ~
なんか淋しいね~」
チラッと
その女性の方を見ると
ピンクの髪色。
「今は
こういう人が多いんだ~」
と
心の中でイマノリ。
そのうちに
「まだ
髪色は黒じゃなきゃダメ
とか言ってんだ~。
髪色なんて
なんだっていいじゃん」
と思い始めちゃいました。
社会人なんだから黒。
公務員系だから黒。
接客業だから黒。
こういう変な常識みたいなの
ガンガン
ぶっ壊したくなっちゃうのよね~。
もうほんと
自分の好きな色でいいでしょって。
髪の色。
肌の色。
土の色。
水の色。
人の色。
人生の色。
こうじゃなきゃダメ
とか
こうじゃないとおかしい
なんてことはない。
それぞれの表現でいい。
それぞれの捉え方でいい。
それぞれの生き方でいい。
で
その
それぞれの違いを楽しんでいく。
これができない大人が多いから
クレームを言ったり
差別したり
争いになっ
0

はじめまして
ココナラのサービスをスタートしましたこれまでの経験をフル活用しキャリア作りを真剣に考えている方のお力になるよう努めます
グローバル製薬企業の様々な部門で働いた経験を活かそうと
キャリアコンサルタント業界に転籍し6年が経ちましたハイクラスを対象にした”ヘッドハンター”と言われる仕事をメインにしています
このクラスの案件では、クライアントが欲しいと考える候補者を探して紹介しますどちらかと言えば、クライアント側に立ったお仕事です
私の働く目的がお金でなくなった最近は、若い候補者の方のキャリア作りについて様々なお話をすることにやりがいを感じていますココナラでは”候補者の立場に立ったキャリア支援”に努めます
しっかりお話を伺い皆さまのお考え、お気持ちに寄り添えるアドバイザーを目指します❗️よろしくお願いいたします🤲
0

【あなたはどのように生きたいのか】
今ぱっと浮かんできた言葉は「解放」・・・って昔から好きな言葉です。一時期、僕はこの言葉の意味をやたら重々しく、そして神聖な言葉として胸に秘めていた。自分はもっといけるんだ!やれるんだ!激しい疼きにかられる自分を解放したくて、ネガティブな環境から解放されたくて、もがきにもがいた30代半ば。あたかも「全てを変えなければ達成できないのだ」と大げさに構えていた。それでもやれなかった自分がいた。なぜなのか。何でって、変わらないための言い訳なんだもの。かの有名なアドラーさんも言ってるね。悲劇のヒロイン、かわいそうな自分、悪いのは周り。「これからどうするの」の視点が抜けていた。そんな考え方をしている自分に本気で自覚的にならないと、ポジティブな願い思考があったとしてもなんか知らんけど元の状態に戻るのね。コーチング受けて変わったっす。そりゃあもう劇的に。実はコーチングに出会う前もその兆しはあって、でもその取り組みはゆっくりで。誰しも現状に慣れる。その状況を知ってしまっているから。実は自らその状況を「選択」しているから。びっくりするでしょ。その状況を自分で選択しているからね。そんなこと認めたくないから他責するんだよ。私のパーソナルコーチの、「あなたを信じている」「あなたには自分を超える力がある」がめちゃくちゃ安心感。なんでも話せるし、話さなくてもいい。時に優しく寄り添うように、時に厳しく奮い立たせてくれる。そして「最強の壁打ち」 であり「最強のミラー」 である人は元々創造力と才知に溢れ、欠けるところのない存在である。実際私は、・状況が何に起因していたのかを正しく理解したし、・それついて徹底的に向き
0

きちん感謝をと伝えられる人は、ポジティブな考え方が身につき、自然と同じ考え方を持つ人たちが集まってくる!【アラフィフ心理カウンセラー「うさぴょん」のココナラ電話相談
感謝の力は、私たちの人生に素晴らしい変化をもたらします。感謝の心を持つことは、ポジティブな考え方を養い、周囲に同じようなエネルギーを引き寄せます。実際、感謝を表現することで、自然と同じような考え方を持つ人たちが私たちの周りに集まってきます。これは、感謝が持つ魔法の一つであり、私たちの人間関係や成功に大きな影響を与えるものです。
感謝の力は、ポジティブな考え方を身につける手段として強力なものです。日常生活の中で感謝の心を持ち、小さなことにも感謝することで、私たちは自然と楽観的な視点を身につけることができます。困難な状況に直面しても、感謝の心を持ち続けることで、その困難さえもポジティブな学びや成長の機会として捉えることができるのです。
さらに、感謝の心を持つ人々は、同じようなエネルギーを持つ他の人々を引き寄せます。ポジティブな考え方を持つ人たちは、自然と共鳴し合い、心の豊かさや幸福感を共有することができます。その結果、ポジティブなサークルが形成され、お互いを励まし合い、成長し合う場が生まれます。
さらに、感謝の表現は人間関係を深め、成功をもたらします。感謝を伝えることで、他人とのつながりが強化され、信頼関係が築かれます。また、感謝の意識を持った人々は、自分の成功や幸福を共有し、周囲の人々と共に成長する喜びを味わうことができます。これによって、ポジティブなエネルギーがさらに増幅され、成功への道が開かれるのです。
感謝の力は、私たちの人生に喜びと幸福をもたらすだけでなく、ポジティブな考え方を持つ人々を引き寄せ、共に成長するチャンスを与えてくれます。日々の生活の中で、感謝の心を忘れずに、
0

大人の必須科目
こんにちは。
いつも
ありがとうございます。
イマノリ
電車に乗ると
車内全体を見渡すんです。
特に上の方。
そう
車内広告を見るためです。
この前も
あっちこっち
ザーッと見渡していたら
「あれっ?
全部似たような広告じゃない?」
そう
シリーズ広告でした。
ツムラの
One More Choiceプロジェクト広告。
もうすぐ社会人になる方へ
社会人の先輩から
メッセージが書かれています。
「完璧にできないのが当たり前。」
「何でも一人で何とかしようとしない。」
「無理は禁物。我慢する時代は終わり。」
「自分を大事にできるのも、
理解してあげられるのも
全部自分。」
こういった言葉が
それぞれの広告に書かれています。
これを見て
思いました。
これからは
自分で自分を
コントロールしていく技術を
身につけることが必須だな~
と。
自分の感情をコントロールしていく。
自分の体をコントロールしていく。
自分へのコトバをコントロールしていく。
自分への良い言葉で
気持ちを切りかえる。
仕事以外の時間をうまく使って
体を切りかえる。
そう
コントロールとは
切りかえていくこと。
心。
イラっとする時もあるし
落ち込む時もある。
体。
ダルい時もあるし
しんどい時もある。
これらは
ある意味
生きていれば当然のこと。
なにしろ
人間ですからね。
いろんな時があるわいね~。
なので
自分で切りかえていく。
自分でリフレッシュしていく。
この技術を
習得していくことが
とっても大事。
切りかえ方は
人それぞれ違ったりもするので
自分なりのものを見つけていく。
その中で
手っ取り早く
誰にで
0

宇宙的「超!軽く生きる」12
おどりば私、趣味でテニスをします。練習してもなんだか横ばいだな〜とか、もしかしたらちょっとくだってる?なんて感じるとき、「いやいや踊り場だぜ」と思うようにしています。ずーっと上りだったら大変。立ち止まったら落ちちゃうかも。上ったことを確認できる場所=踊り場。方向転換だってできちゃう。休憩だってできちゃう。素敵な場所=踊り場。先日、宇宙メンタリング中「あ、踊り場」だなということがありました。十分軽くなってきている、十分変わってらっしゃる、気づいていらっしゃる。でもご本人の実感が伴ってないことがある。ご本人が少し寂しそうだったんです。踊り場ですよ〜とお声かけさせてもらいました。英語では、おどりば=landingやmiddle floor。そこに「ダンス要素」なし。日本語のセンス🙌なかなか成長できないな、とか、まだまだだ、とか、もうここが限界かも、そんなふうに思ったときぎゃくぎゃくぅ〜成長しているからこそたどりつけた、踊り場ですよ〜!自分に拍手。せっかくだから休憩しちゃって、そしてどうせですよ、踊りませんか〜♪写真は先日朝のカフェラテ。ラテアート技術も踊り場かも🤭いい日になりますように♪u and i
0

とにかくニコニコ
こんにちは。
いつも
ありがとうございます。
あなたの周りに
いつもニコニコしてる人って
いませんかぁ?
ちょっと
やり取りするだけで
こちらを二コリンとさせてしまう
そんな人。
職場に出入りしている業者さん。
掃除をしてくれている方。
食堂の方。
ママ友パパ友。
仕事仲間。
ニコニコしてると
声も明るいしね。
言葉の内容も元気だし。
自己啓発とか
人間関係
心を磨くとか
たくさんの本があり
動画もありますね。
もちろん
学ぶことは大事だし
素晴らしいことなんだけど
もうね
四の五の言わずに
毎日ニコニコしてればいいと
イマノリ考えます。
口角を上げて
ニッコリマークを意識していく。
これだけで
人間関係は良くなるし
自分自身もやさしくなってくるし
心もやんわりしてくる。
元気にあいさつもしたくなる。
人も寄ってくる。
人は
明るく楽しいとこが大好き。
人もそうだし
場所もそうでしょ。
ブスッとイライラな人のとこに
近づきたくないですもんね~。
暗いとことかね。
ニコニコが
あなた自身を変えていく。
ニコニコが
あなたの人間関係を変えていく。
ニコニコが
あなたの毎日を変え
あなたの人生を変えていく。
ニコニコ
ニコニコ。
0

天文学的出会い
こんにちは。
いつも
ありがとうございます。
3月も半ばを過ぎ
人との別れの場面が
あちこちで
あるんじゃないでしょうか。
「さよならは別れの言葉じゃなくて
再び逢うまでの遠い約束」
この季節になると
思い出す歌詞です。
『セーラー服と機関銃』。
なんとも良い言葉ですねぇ。
ある本に出てたんですが
人が一生のうちで
なんらかの接点を持つ人の人数は
3万人だそうです。
同じ学校・職場・近所の人は
3千人。
親しく会話を持つ人は
300人。
友人と呼べる人
30人。
親友と呼べる人
3人。
なんらかの接点を持つ人と出会う確率は
なんと
0.000004%だそうです。
ヒョエ~~~。
なんという奇跡的な出会いでしょうか。
こんなふうに見てくると
日頃会ってる
あの人も
職場で会ってる
あの人も
なんか
とっても大切に思えてきますよねぇ。
だって
このとんでもない確率をくぐり抜けて
こうやって関わっているんですから。
日々
人は
相手に対して
いろんな感情を持つ。
腹を立ててみたり
使えねぇなんて思ってみたり
おもしろいことを言って笑い合ったり。でも
この出会いの確率を見れば
もう
出会うべくして出会ってるとしか
言いようがない気がしますよね。
運命というか。
そう考えると
「さよならは
再び逢うまでの遠い約束」
という言葉が
本当にそうだな~と思えてくる。
この確率の中
出会ったんだから
いつかまた
会うんだろうなって。
会わないで終わりなわけないよな~って。奇跡的
天文学的出会いに
感謝しかないですね。
この出会いへの感謝が
良い人間関係を築くための
出発点なんだと思います。
0

幸せの種類が多ければ多いほど、幸せを感じられる人は増えていく!
今回は『幸せの種類』につきまして、思うところをお話していきたいと思います。上記のYouTube動画でもお話させて頂きましたので、よろしければそちらもご覧頂けますと大変有難いです。
いきなりですが、今回私が強く言いたい事としましては、『幸せの種類は多ければ多いほど良いのではないか』という事です。
というのも、まずこの世の中は「ヒト、モノ、カネ」に限りがありますので、皆が皆『同じ種類の幸せ』を求めてしまうと、必ずそこに奪い合いが生じてしまって、結果的に求めているものが手に入らず、必然的に奪い合いに負けてしまって、皆が求める幸せの形から溢れてしまう人が出てきてしまうからです。
まず「ヒト(人)」には限りがあり、しかも男女の比率が完全に同じでないという事は、数字上はどうしても世の中の人全員が必ず異性の人と結婚できる訳ではありませんし、「物(モノ)」に限りがあるという事は、世の中の人全員が資源に恵まれた生活を送れる訳ではありません。
また、「カネ(お金)」に限りがあるという事は、世の中の人全員がお金持ちで裕福な生活を送れる訳ではありませんので、どうしても人々の生活水準に差が出てきてしまいます。
そう考えますと、『幸せの種類』というのは、少なければ少ないほど幸せを感じられる人が少なくなってしまいますが、逆に『幸せの種類』が多ければ多いほど、それに伴って幸せを感じられる人も増えていくと思うのです。
そして何より、ある人が幸せだと感じる『幸せの種類』というのが、他の人にとっても幸せを感じられるとは限らないのです。
例えば、Aさんは結婚して平穏な家庭を築いていく事に幸せを感じるかもしれませんし、
0

幸せでも悲しくても
こんにちは。
いつも
ありがとうございます。
「人は
幸せでも泣くし
悲しくても泣くのよ」
これは
先日放送された
NHK大河ドラマ『光る君へ』の
第10回目の中で
主人公のまひろ(のちの紫式部)が
藤原道長に言った言葉です。
「あ~~
確かにそうだ~」
と
心にジ~ンときました。
ちなみに
この回は
これまでの10回の中で
1番良かったと
イマノリ感じました。
「自分は
人前では絶対泣かないです」
という人
まあまあ
いませんか?
イマノリの知り合いにもいますよ。
「え~~
ガンガン泣いちゃえばいいのに~」
って言いますけどね。
泣きたい気持ちを抑え込む。
これって
やっぱり
人にとってムリなことなんだと思うんです。
抑え込んでると
心に
いつか異常が出てくる。
苦しくなる。
生きづらくなる。
だから
自分の気持ちを
素直に出しちゃえばいい。
うれしい時は
おもいっきり笑って
幸せを感じたら
じんわり涙をこぼして
悲しかったら
気の済むまで大泣きして。
自分の気持ちは
自分でプラスの方に切りかえられるから
安心して
その時の悲しい気持ちを
涙で
表現しちゃえばいい。
それが
人として自然なことなんだと思います。
水の入った風船のように
自分の気持ちも
ムリヤリ抑え込めば
いつかは破裂しちゃうでしょ。
心だってそう。
泣く。
恥ずかしいことじゃない。
悪いことじゃない。
性別だって関係ない。
年齢だってお構いなし。
涙は
自分の心を
スッキリと洗い流してくれますもんね。
0

人は、「同じ」を積み重ねる
こんにちは。
いつも
ありがとうございます。
人は
日々
「同じ」を積み重ねている。
いつもと同じ食べ物。
いつもと同じ飲み物。
いつもと同じ道。
いつもと同じ席。
いつもと同じ行動。
いつもと同じ考え方。
いつもと同じ捉え方。
そして
いつもと同じコトバ。
仮に
あなたが
何かの病気になったとします。
そしたら
いつもと同じを
変えていかなければなりません。
食べるもの
飲むものを変えて
病気を治そうとします。
仮に
あなたが
毎日がつまらないと感じているとします。
そしたら
いつもと同じを変えていかなければなりません。道を変えてみたり
お店を変えてみたり
違うことをしてみたり。
仮に
あなたが
いつもネガティブな気持ちでいるとします。
そしたら
いつもと同じを変えていかなければなりません。
自分の当たり前を疑っていく。
良い面を見ていく。
そして
自分へのコトバを
ポジティブなものにしていく。
「同じ」はとってもラクちん。
何も考えなくて済むしね。
それだけに
ついつい
かたよってしまう。
自分の好み。
自分だけの常識。
自分へのコトバづかい。
体も心も
生活習慣病になりがち。
予防するには
意識して
日々の自分を見ていくことが
大事になってきます。
自分を意識して見ていく上で
この2つのことがポイントだと
イマノリ考えます。
1.自分へのコトバを変えること
2.感謝の心で周りを見ること
いつもと同じ部分を保ちながらも
この2つのポイントを心がけて
自分から
毎日を楽しくしていきましょう。
0

その感情、あなたが決めて選んでいる
こんにちは。
いつも
ありがとうございます。
うれしいも
楽しいも
つまらない
ガッカリ
イライラも
すべて自分が決めて
そうしている。
例えば
信号が赤になる。
ふざけんなよと
イライラしながら待つ人もいれば
ゆっくり行けばいいやと
穏やかに待つ人もいる。
例えば
仕事でうまくいかなかった。
自分ダメだな~と
ガックし落ち込む人もいれば
今回のことをムダにせず
次につなげようと
ある意味楽しめる人もいる。
プラスの感情
マイナスの感情。
ポジティブな感情
ネガティブな感情。
実は
あなた次第で
どっちでも選べるんですね。
あなたは
自分の好きな感情を選べばいいんです。
いいんだけども
人にはそれぞれ
クセがあるので
好きじゃない方の感情が
無意識に出て来てしまうことが
ちょくちょくある。
心のクセ。
考え方のクセ。
捉え方のクセ。
つい
マイナスの方に捉えちゃうクセ。
否定的に捉えちゃうクセ。
だから
まずは
自分の心のクセを知ることから始めていく。
自分のクセがわかったら
次に
自分へのコトバを変えていく。
自分へのコトバの使い方で
自分の望む
好きな感情に
切りかえていくことができる。
これが
自分で自分のご機嫌を取る
ということ。
感情は
自分へのコトバ次第で
コントロールできるのであります。
0

人は、何かしら抱えて生きている
こんにちは。
いつも
ありがとうございます。
昨日の土曜日
フジテレビの音楽番組
『ミュージックフェア』に
松田聖子さんが出ていました。
どんな様子なのかなぁと思いながら
見ました。
にこやかな表情で元気そうでした。
人は
誰でも
いろんなことを抱えながら生きている。
悲しいこと。
つらいこと。
大変なこと。
それでも
前を向いて生きている。
聖子さんのような芸能人なら
どんなことがあって今に至っているか
ほとんどの人が知っている。
でも
私たち一般の人同士では
相手の人に
今までどんなことがあったかなんて
よほど親しくない限り
わからない。
よほど親しくても
知らないかもしれない。
パッと見
外からは気づけない。
無口な人。
冷たそうな人。
ツンケンしてる人。
これまでの何かを抱えてるから
そんなふうなのかもしれない。
抱えながらも
にこやかに
穏やかでいること。
これが
人間としての成長なんだと思う。
悲しいこと
つらいこと
大変なことを
自分の心の栄養にしていく。
人生の糧にしていく。
その時はもちろん
悲しくて
つらくて
大変なんだけれども
時間と共に
捉え方を切りかえていく。
「このことが教えてくれてることは
何だろうか?」
人間を学ぶ。
人生を学ぶ。
抱えたものを
堂々と素直に受け入れ
大切に抱きしめて
その自分で
にっこり前を向いて
これから先の人生を歩んでいく。
これが
「ありのままの自分で生きる」
ということなんでしょうね。
0
あなたも記事を書いてみませんか?
多くの人へ情報発信が簡単にできます。
ブログを投稿する
多くの人へ情報発信が簡単にできます。






.png)




.png)



.jpeg)

.png)
























