すべてのカテゴリ
新着有料ブログ
65 件中 1 -
60 件表示

私の仕事ぶり
この場をお借りして、自己紹介させてください。現役の塾講師で、主に国語を担当しています。小学生から高校生まで、現代文も古典も担当します。塾業界に入ってそろそろ30年が経ちます。去年からそのキャリアで得た知見をnoteに書いてアップしています。ルール上ここにはリンクを貼れませんので、一部記事を引用しておきます。例えば先日は、指示語問題についての記事を書きました。こんな感じに。(以下、自分の記事の引用)そうした物語を掘り起こすことこそ、漫画評論家の使命ということができるでしょう。漫画の再発見とは、価値の再発見でもあり。漫画評論家は特にそのことにこだわらねばなりません。
【問】太字部分「漫画の再発見」とはどういうことか。本文の言葉を用いて35字以内で答えなさい。
「分析」とは、語句の関係性をつかむことです。問いが設定された最後の一文でやってみましょう。
漫画の再発見=価値の再発見=漫画評論家がこだわら★ねばならないこと
変な場所に★をつけていますが、理由はすぐに明らかになります。その前の一文も同様に。
そうした物語を掘り起こすこと=漫画評論家の★使命
「使命」とは「与えられた任務」の意。つまり、やらなくてはいけないこと。上で2か所つけた★がイコールでつながります。これも立派な関係です。
そうした物語を掘り起こすこと=漫画評論家の使命=漫画の再発見(設問)=価値の再発見
語句の関係性は、文章表現から分かるものも当然ですが、先の★のように、語句知識を活用して見出すものもあります。
(引用終わり)
0

登場人物の気持ちを読む その2
国語の読解は漠然としたもの、雲をつかむようなものと思われている方が多いと思います。
また、読書をしないと読解力は身につかないと思われている方も多いと思います。
もっとも、ある程度の読書は必要だと思います。それは読解力を身につけるためと言うよりも、時間内に読みきる技術を身につけるためです。
一昔前は学校に行っているだけで朗読する技術は自然と身に付きましたが、最近は中学受験をする子でも、まともに音読できない子が増えています。
国語で得点するためには、絶対に語彙力が必要になります。皆さんもわかっているはずなのですが、とにかく後回しにされてしまいます。
語彙力がほとんどない状態でいくら問題を解いても、全く力は付きません。ただ適当にクイズをやっているだけです。
次に、こういう場面では『こういう気持ちになる』というパターンを覚えます。このパターンの組み合わせで物語文は出来上がっているので、このパターンを覚えてしまえば数学の公式や法則のように解けます。物語文の読解は気合いと根性でやるものではなく、ある程度機械的に解けてしまいます。もちろん最難関校になれば、この法則を外してしたり、書きにくくしてきたりしますので、その対策は必要になります。
最後に、記述力(読みとったことをまとめて、わかりやすくシンプルに表現する力)が必要です。これは日頃の日常会話でも練習できます。最近は何を伝えたいのかがわからない子が増えています。きっと親が先回りして汲み取ってあげてしまうからなんだろうな、、、と思っています。日頃から主語、述語、目的語を意識させて、かつ論理的に話すように仕向けていれば、かなり変わって
0

国語講師のひとり言「100点満点のテストにしよう」
『個別の授業で面と向かっては言いにくい話をコラムにしています。言いにくいワケは、生徒さんは1人1人状況が異なり、一般論のアドバイスがつねに当てはまるとは限らないからです。
ですのでタイトルも「ひとり言」。本コラムの内容に有効性があるかと問われれば、私自身の中学受験や長年の指導で実践を心がけ、結果を出してきた事実を挙げるのみです。』「いや~まあ、そりゃねえ…100点取れれば文句はないけど…」ちらりとタイトルだけ見た人からは、ため息まじりにそんなつぶやきが聞こえてきそうです。しかし!私はなにも「テストで100点満点を取ろう」だなんて、そんな大それたことを言っているわけではありません。(だいたい私自身、塾のテストで100点なんて取ったことがないですし…)では一体、「100点満点のテストにする」とはどんな意味なのでしょうか?オンライン授業でのやりとりで、返却された生徒さんの答案を見せてもらうことがよくあります。そこで気になるのが、答案に空欄が目立つケース。私に言わせると、空欄とはすなわち「試合放棄」なんですね。だって何も書いていなければ、絶対に点はもらえませんから。たとえば試験時間終了時に、10点ぶんの空欄があったとしましょう。仮に埋めたところが全部合っていたとしても、そのテストは90点止まりですよね。空欄を残したまま終えたことで、自ら望んで90点満点のテストにしてしまったことになります。全部合えば100点の答案を提出した生徒と、全部合っても90点の答案を提出した生徒。どちらが合格の可能性が高いでしょうか?ちなみに子どものころの私は、中学受験のための国語のテストで、ただの一度も空欄を残
0

国語・現代文 長文読解 解き方伝授
はじめに
皆さん、こんにちわ。合格サポーターの佐々英流(ササエル)です。今回は、ササエル式 国語・現代文 長文読解サポートのご紹介です。長文読解って難しいですよね
国語・現代文の長文読解って、難しいですよね。まずは、長文の長さに圧倒されますね。場合によっては、同じ大問の中に、二種類の文章が提示されるなど、解きづらさが加速していますね。皆さんは、国語、現代文の長文読解問題を解けていますか?勘やセンスで解いていませんか
国語は、まず、解き方が分からないという声が多い教科です。実際、勘やセンスで解いている人も多数いるでしょう。そう、長文読解で、苦しんでいる受験生が、多いんです。でも、この方法では、得点が安定しませんね。このような解き方で、随分、損をしている受験生も多いんです。読解問題の解き方は習わない?
なんで、このようなことになるのでしょうか?国語、現代文の読解問題の解き方は、学校でしっかり習ってないのではないでしょうか?確かに、ここは、比喩、ここは言い換え、ここは対比と、様々な技法は学びますね。選択肢問題は、消去法で解くなどの解法も学ぶことでしょう。ですが、ですがですよ。数学みたいな、完全無欠の、設問から正解までのまっすぐな道は、示されませんよね。それで、国語、現代文難民が大量生産されているのではないでしょうか?つまり、数学のような明快な解法を、国語、現代文では学んでいないまま、試験を受けているのではないでしょうか?国語、現代文はサービス科目?
そのような、難民生活にあっても、現実には、すごいことが起きているんです。共通テストの国語で確認しましょう。令和5年の本試験です
0

国語の学習はなにをすればいいの?
国語は出たところ勝負だから、勉強しなくてもOK!!一回三万円の「試験ガチャ」思考みなさん、こんにちは。年の暮れも近くなり、すっかり追い込みモードになってきた今日この頃。いかがお過ごしでしょうか。さすがに上のようなのんきなことは言ってられないなと思いつつ、でも実際は何も対策をしないままここまできてしまった……。そんな方も多いのではないでしょうか。もちろん、「自分は国語、現代文の学習にしっかり戦略を持って取り組んできたぞ!」と自信がおありの方もいらっしゃるでしょう。ただ、多くの方は「入試問題は解いたし、一つ一つの問題に対して反省点を見つけたものの、どうも一皮剥けないな……」という所感をお持ちなのではないでしょうか。何を隠そう、筆者が受験生の時も同じような状況でした。学生時代の筆者は現代文の受験勉強らしい勉強はしたことがありませんでした。古文や漢文は、文法事項や句形を覚えたり、古典常識や漢文脈の世界観を知ってみたり、塾や学校、参考書でも学習方法がよく整備されていますよね。しかし、現代文は例えば『〇〇の最強の国語』など有名予備校講師の著作はあるものの、全ての文章を読むにあたって例外なく使えるワザや知識が載っていることはありません。傍線の付近に答えがあるなどと言われたりもしますが、まず「傍線の付近って具体的にどこ??」という疑問も抱きますし、段落内を探すくらいな経験則を得たとしても、「随分と離れたところに答えがあったな」と腑に落ちない気持ちが続きます。そういう、正しいような正しくないような「解法」に触れることで、得点率が上がらなかったわけではありませんが、どうしても数学や物理のように10
0

ナイスな質問から生まれる気づき
私は、週に3日塾で生徒に国語を教えています。こんなことを言って、恥をさらすことになりますが、国語を教えていながら、じつは言葉の扱い方、文章を書くことが人よりも下手です。おしゃべりも、めちゃくちゃ下手です。笑ってしまうくらいヘタれです。そんな私は、集団塾でたくさんの子どもを前に話すことはできないので、個別塾で生徒一人と一人とお付き合いしています。4年続けているので、慣れたものです。言葉の扱い方を覚えれば、少しはマシな人間になれます。でも、いまだに失敗ばかり。。さて、先日、中学受験をする生徒に「どうして、国語を勉強しなきゃいけないのか」と尋ねられ答えたことがあります。正直、少し答えにくい質問だったのですが、自身で考え直すきっかけを与えてくれたナイスな問いだったので、残しておきます。言葉はコミュニケーションのためにある。情報を読み取り家族や友達に伝える時に大切な役割をもつこと、そして、書かれた文章は、必ず読み手となんらかの関わりがあるということ。筆者がいて、原稿を編集して本にして出版して本屋に並べる過程でたくさんの人たちが関わっている。そうして目の前にある文章は、必ず社会的な文脈を持っている。つまらない文章だということは簡単だけれど、読む側の想像力と関係しているということを伝えたのです。読解力がおぼつかないと、楽しめるものもそのぶん減ってしまうかもしれない。同じ時間を生きているのに、楽しむ時間がずーーっと半分のままだったらやでしょう?と。うんうんと、テキストに目を落としながら首を縦に振る少年。じゃあ、物語文はなんで必要なの?と畳みかけてくる。彼は、物語文が苦手である。存在理由を問う彼
0
.png)
人生という小説の主人公は「あなた様」
そもそも英語の学習も「三人称単数」というようなものが出てくるともう、雲行きが怪しくなり、楽しくなくなるものだ。三人称、というネーミングが失敗だと思う。昔の偉い人が考えたのだろうが、三人などというから、てっきり人数のことか思ってしまう。三人だから、複数、なのに三人称単数だなんていったい何だよ、と思ってしまうのも無理はないと、私は考えている。
私はよく、「小説なんて、所詮つくり話」「国語の教科書や問題に出てくる小説はおもしろくない」「国語の小説はストーリー展開よりも人間の心情(の変化)に重きがおかれているのでそれを確実に読み取ることが大切である」のような趣旨のことを言ったり書いたりすることが多い。そして、(国語に出てくるものに限らず)小説というものは、「人称」で言えば「一人称」か「三人称」のどちらかで書かれている。一人称小説の場合は特に「私小説」と呼ばれ、「私」を主人公として話が進められる。作者はおっさんなのに妙齢の女性や思春期の「私」になってスト―リーを展開させてゆく。日本人はこの私小説が好きと言われる。三人称小説というのは、太郎や花子のような一人の主人公がいて、その一人の視点で描かれる小説である。私小説の場合は当然のことだが、三人称小説でも「視点」は主人公に固定されていて、心情が直接書かれているのも主人公だけである。他のキャラクターの心の中までは記述されないのが普通だ。「神の視点」という手法であらゆる登場人物の心理が描写されている小説もないわけではないが、きわめて珍しいといってもいい。
コミュニケーションというのは、発信者がいて受信
0
.png)
三つ子の魂百まで
三十年以上も塾の講師をする中で、様々な生徒さんに出会ってきた。アイドルになった子、有名人のいとこ、お笑い芸人を目指して高校卒業後にNSC吉本総合芸能学院に進んだ男子など、本当にいろいろな人生に遭遇した。そんな中でも、印象的な兄弟がいる。別に有名人になった訳ではない。正確に言うならば、兄妹だ。入塾するためのお問い合わせの電話を受けたとき、「中学3年生を3人入れたいのですが。」と先方がおっしゃるので、てっきりお友達も一緒にか、と思ったのだが、「いえ、きょうだいです。」とのこと。つまり、三つ子だったのである。生徒はもちろん、それまでの人生で三つ子に巡り合ったことは一度もない。そして、その後も皆無であるから、稀有なことと言える。一卵性双生児の場合は、(少なくとも外見は見分けがつかないほど)うり二つという場合が多いが、そうでなければそれほどでもない場合がある。普通の兄弟が、時間差なく同日に生まれたというだけ、というふたごのパターンである。この三つ子は後者で、性別も、上から順に、男、女、女である。姿形もそれほど似てはいない。それに加えて、性格はまるで違う。さらに、成績の方はというとこれもまた三者三様で、見事なまでに上位、中位、下位なのである。これにはさすがに少し驚いた。
この体験をしてからというもの、学習する能力は両親からの遺伝が多くを決めるものなのだろうかと疑念をもつようになった。「外見」に関しては、「後ろ姿がお父さんにそっくり。」「目元はお母さんによく似ているね。」などということはよくあるけれど、勉強に関してはそれほど単純ではない、という考え方に変わったのである。だから、子どもに「お父
0
.png)
何か誤用?
お盆あたりの日のこと、なじみのお店を訪問してみると、シャッターが降りていて、そこには「誠に勝手ながら、本日から3日間、休業させていただきます」との貼り紙が。別に休んでもらっても構わないが、この誤用表現が、つい、気になってしまう。間違いを堂々と紙に書いて世にさらしているのだから、これを見た人が正しい表現と認識し世に流布してしまうだろう。丁重な謙譲語として、改まった席でも使われる「~させていただく」。元来、どんな意味なのだろうか。「させていただく」は、動詞「する」+接続助詞「て」+「もらう」の謙譲表現である補助動詞「いただく」で成り立っている。「(ご了承のうえ)訪問させていだだきました」のように、基本的に相手の許可を得て自分が何かを行い、その恩恵を受けることに対して敬意を払う場合に使うのがもともとの意味である。とにかく、相手の許可を得て〜するというのが基本義であるから、先のお店の貼り紙の場合であれば「いや、だれも休んでいいとは言っていないよ。」、とついツッコミを入れたくなるのである。厄介なのは、この誤用が、あまりにも定着しすぎていて、使っている本人は、正しいと思いこんでいるどころか、最高の謙譲表現を用いていて、充分にへりくだった気分になっていると思われる点だ。このケースなら「誠に勝手ながら、本日から3日間、休業いたします。」でよい。「休業いたします」、ときっぱり言い切ってしまうと、断定的で何かもの足りない感じがするのだろうが「休業する」の部分が「休業いたす」のという謙譲語になっていて、それに「ます」という丁寧語までついているのだから、何も問題はないのである。
もちろん、「させてい
0
.png)
たとえたとえでたとえてもたとえられない例
美咲先生は「すもも小学校」に大学新卒で赴任したばかりの1年生教師。元気過ぎる児童たちに多少は手を焼きながらも、夢であった小学校教諭の仕事だから、不平を言えば、罰が当たると思っている。
4年2組。1時間目は、国語の時間。「みんな、たとえって分かるかな。そうねぇ、じゃあ、星を何かにたとえてみよう。分かる人は手を挙げて。」説明の流れの中で、「たとえ」という事柄が出てきたので、問うてみた。いっせいの挙手。こういう場面で元気がいいのは好ましい。
「はい、颯太君。」指名された颯太君が答える。「ええっと、海王星。」おお、というどよめきが起きる。太陽系の中でも目立たない星を出すところが颯太君らしい。「はい、じゃぁ結菜(ゆいな)ちゃん。」結菜ちゃんはにこりとして「月です。」と答える。「月は星と違うと思います。」と誰かの発言。教室内の何割かがそれに賛同するような空気だ。「いいえ、月も星の一つよ。地球に近すぎて大きく見えるから、あんまり星っぽくないけどね。」そうか、という納得の雰囲気で教室が静まる。
「はいっ。」元気よく龍之介君の手が挙がる。「じゃぁ、龍之介君。」龍之介君は立ち上がりこう言った。「うめぼし。」爆笑が起きる。いつもこうである。龍之介君の発言は笑いを呼ぶ。しばらく収まらない。
「正解。龍之介君が正解よ。」ええっ。疑問符が教室じゅうに散らばる。「何故だか分かるかな。たとえるということはそういうことなの。例を出すなら火星でも金星でもいいけどね。もし、夜空に赤っぽく輝く星があり、それを龍之介君が梅干しにたとえたんだったら、龍之介君は天才ね。」
小学4年生がどこまで理解したかは分からないが、美咲
0
.png)
王朝時代のトップブロガー
清少納言が現代に生きていれば、間違いなくブログをやり、人気ブロガーになり、本も刊行してベストセラーを連発するエッセイストになっているでしょう。日常のちょっとした面白いシーンをTik Tokに上げたり、綺麗なお気に入りのお召し物の写真をインスタグラムにアップしたり、と現代の文明の利器をフル活用していると思います。残念ながら、約千年前の時代にはそんなものはなく、紙と筆というツールに頼るしかなかったのです。
「君俟つと 我が恋をれば わがやどの すだれ動かし 秋風の吹く」、万葉集、額田王。あなたを待って私が恋しく思っておりますと我が家の戸のすだれを動かして秋風が吹いてきます、と口語訳はこんな感じで、「何だ、愛しいあの人かと思ったら、ただの風か」という額田王の落胆が千年以上の時を超えて伝わってきます。額田王は言うまでもなく女性ですから、現代に置き換えると次のようになるでしょう。「LINEが来たので大好きな〇〇君からかと思って急いで見てみると、何だ、ブー太郎からか、とがっかりして読みもしない。」高貴な額田王になぞらえるのも不適切で、どうかと思いますが、人間などいつの時代も同じだと私は思います。
古典、古文というと異次元・異世界のことのように感じがちです。もちろん、生活の便利さなどはまるで違います。でも、そこで生活しているのは私たちと同じ生身の人間なのです。古典は文語で書かれていますから、余計に違和感をもつと思いますが、結局のところ人間はいつの時代も同じなのだということを学ぶのも古典学習の意義だと思うのです。
清少納言のことを、同時代の才女である紫式部がライバル視していたと習ったことがあり
0

なかなか動かなかった成績が…
今日は「国語力養成コース」をご受講されているラボ生から嬉しいお話を伺いました。 「今まで現代文でさっぱり点数がとれなかったのに、急にグッととれるようになったんです!!」と。 「国語力養成コース」をはじめてまだ半年ぐらいなのですが、学校・部活と忙しいなか頑張って勉強してくれているからでしょうね。論理的に読めるようになったのだと思います。 なかなか動かなかった成績が、読み方一つで変わるのですからね。 とても嬉しそうだったので、私も「ホント〜!!」と叫んじゃいました^_^ 「国語力養成コース」は小学1年生からはじめられます。 ご興味があればぜひ体験にいらしてくださいね。 それでは今日もゆっくりおやすみくださいませ。
0

国語講師のひとり言「『やればできる』はNGワード」
『個別の授業で面と向かっては言いにくい話をコラムにしています。言いにくいワケは、生徒さんは1人1人状況が異なり、一般論のアドバイスがつねに当てはまるとは限らないからです。
ですのでタイトルも「ひとり言」。本コラムの内容に有効性があるかと問われれば、私自身の中学受験や長年の指導で実践を心がけ、結果を出してきた事実を挙げるのみです。』受験勉強をしているとき、「やればできる」というフレーズは禁句にしてください。なぜでしょうか?理由はかんたん。受験に関して、まったく意味をなさない言葉だからです。志望先の中学校が見ようとしているのは、受験生が「やればできる」子かどうかではありません。端的に言えば、「できる」子かどうかにしか興味はないわけです。入試問題の難しさを知っている人なら、この点はすぐに納得してもらえるでしょう。そして「できる」とはすなわち、「必要とされる課題を『やり遂げられる』能力」以外の何物でもありません。「やれば」というまさにその条件を、条件のままにとどめおかず、勇気をもってすみやかに実行できるか否か。合格のためにはアレとコレとソレをやらなきゃいけないとわかったときに、アレとコレとソレに真正面から向き合い、必死でこなせる生徒なのかどうかが、入試で一番問われていることなんですね。要するに「やる」ことができるかどうかが試されているのであって、もし現状「やる」ことができているならば、その生徒さんはすでにある種の力を証明しつつあるわけです。一方、「やればできる」の方はどうでしょうか。たんに「今はまだやれていない」状況や、「今後もおそらくやるつもりがない」展望を、言い訳がましく表明したむ
0

古文単語帳の選び方
難関大学(国公立2次、早慶上智、関関同立、GMARCHぐらいの偏差値の大学)を志望する人
↓
場面別になっているもの
(例:『合格古文単語380』(桐原書店))
難関大学以外(共通テストのみ=主に理系、日東駒専、産近甲龍ぐらいの偏差値以下の大学)を志望する人
↓
頻出順になっているもの
(例:『核心古文単語351』(尚文出版)←学校しか販売してないかも)
です。今のところ。
目次を見れば判断できます。
理由は、
場面別になっているもの
→古文常識(古文を読むために必要な当時の時代背景や常識)も身につけることができる。それに、難しい文章は古文常識が必要。
頻出順になっているもの
→よく出てくる単語から覚えられるため、古文が読みやすくなる。
からです。
もうすぐ夏休み。
受験生にとっては、「夏を制する者は受験を制する」といっても過言ではないくらい、重要な時期です。
その時期を無駄にしないために、なにをしようか考えている人が多くいると思います。
古文は、なんといっても、まずは単語。
単語を知らなければ、読めませんし、おもしろくないし、やる気も出ない。
ということで、まずは単語から始めてみるのはどうでしょうか。
少しは変わると思います。
0

国語講師のひとり言「漢字の得点が国語の成績に比例するワケ」
『個別の授業で面と向かっては言いにくい話をコラムにしています。言いにくいワケは、生徒さんは1人1人状況が異なり、一般論のアドバイスがつねに当てはまるとは限らないからです。
ですのでタイトルも「ひとり言」。本コラムの内容に有効性があるかと問われれば、私自身の中学受験や長年の指導で実践を心がけ、結果を出してきた事実を挙げるのみです。』結論から申し上げましょう。塾のテストでの漢字の得点率は、往々にして国語の成績そのものに比例します。
現実に即してより具体的に言えば、入試が近づいても10問のうち3問4問と漢字で落としている生徒さんは、第一志望校への合格がかなり危ういです。このコラムでは、なぜ漢字の出来不出来が国語の成績そのものを左右するのかについて分析。
最後まで読んでいただけたら、漢字学習のモチベーションが確実にアップするはずです!漢字はサービス問題入試では漢字は明らかにサービス問題です。よって「失点はありえない」との認識で臨む必要があります。
仮に漢字の読み書きが5問出て、全部できると10点の配点だったとしましょう。
0
1,000円

国語講師のひとり言「国語の成績はどれくらい伸びるもの?」
『個別の授業で面と向かっては言いにくい話をコラムにしています。言いにくいワケは、生徒さんは1人1人状況が異なり、一般論のアドバイスがつねに当てはまるとは限らないからです。ですのでタイトルも「ひとり言」。本コラムの内容に有効性があるかと問われれば、私自身の中学受験や長年の指導で実践を心がけ、結果を出してきた事実を挙げるのみです。』中学受験での国語の伸び率はどれほどか国語はたとえば算数に比べて、成績が上がりづらい教科です。ココナラでのオンライン授業での経験をもとに、伸び率の目安を具体的な数字でお示ししたいと思います。受験までおよそ8ヶ月のあいだ、週1回1時間の授業を継続受講していただいた生徒さんの場合を例にとりましょう。国語の偏差値ですが、わかりやすいことにきっかり10上がりました。
これぐらい伸びれば、第1志望の圏外から十分狙える位置までステップアップできます。
実際、見事第1志望の中学校に合格してくれました。
むろん講師との相性もあれば、生徒さんの性格、学習環境などさまざまな要素がからんできます。同じ期間、同じ頻度で取り組んだからと言って、全員必ず10上がる保証はありません。また「倍の週2回にしていたら20上がる」というような、単純な計算の話でもないのは当然です。
それにひと口に「10上がる」と言っても、「44から54」と「57から67」では状況がかなり異なります。この生徒さんの場合は、あくまでどちらかと言えばですが、後者よりは前者に近い状況でした。もっと言えば50台後半の偏差値を60台後半にまで上げるのは、私の体験では至難の業です。最低でも1年半は時間がないと、そもそも無理で
0

音のイメージ④「え」
はじめに(今回はじめて読む方)
音のもつイメージを捉えようというのが大テーマの記事です。
文学的表現の向上やワンランク上のコミュニケーションを目指す方向けの文章となっておりますので、乞うご期待。基本説明「え」は母音音素のひとつであり、口を開け、舌を中央付近に持ち上げながら発音されます。口蓋と舌の間にスペースを作り、のどからの息を自然に出すことで響きを生み出します。発音は短め、中音域で発声されやすい特徴があります。ではみなさん、せーの!「えーーーーーーー」想起イメージ
さあここが本記事のメインです。「え」の音から導びかれる感性、感覚、感情といったものを深掘りしていきます。・明るい朝日のような「え」 明るく開放的な響きを持っています。・軽やかな風のささやきのような「え」 短めの音で、中音域で響くため、軽やかな風のささやきのような印象を与えます。・清涼な水の流れのような「え」 明快でクリアな響きを持ちます。・活気に満ちた市場のような「え」 活気に満ちた光景を連想させるような響きをもっています。まとめ:明るさ、開放感、軽やか、明快、クリア、活気このような印象を得られるのが日本語における「え」の音です。
これらはポジティブな意味合いをもつこともあれば、語の内でネガティブなニュアンスを付加する方向に作用することもあるでしょう。単語・オノマトペ
上記のイメージを想起させる「え」音からどのような単語がつくられているでしょうか。ここでは例によって日本語の単語を考えていきます。
・「えがお」…明るさ・「えー(嫌だよ)」…明快、活気(ネガティブな)・「ぺらぺら」…軽やか・「エイエイオー」…解放感、活
0

音のイメージ②「い」
はじめに前回に続いて今回は「い」について。音のもつイメージを捉えようというのが大テーマの記事です。文学的表現の向上やワンランク上のコミュニケーションを目指す方向けの文章になります。基本的説明
「い」は日本語の母音音素のひとつで、非常に短く口の中で高い音を発する特徴があります。口を半開きにして舌を前方に持ち上げ、口蓋との間にスペースを作りながら発音します。舌の位置は前方にあるため、口がやや細長くなります。なんて言葉で説明するより実際に、「い」と言ってみればいいですね笑想起されるイメージ
さあ、本番です。「い」という音から導出される感性、感覚、感情といったものを思いつくまま深掘りしていきます。1.「い」の音は短く、細く高い響きを持ちます。まるで水滴に光が反射し、美しい輝きを放つ様子が頭に浮かびます。2.短く、高い音は遠くの方で鳴る鐘の音のようなイメージを連想させます。静かな風景の中に遠くで響く鐘の音が染みわたっていくような感覚でしょうか。3.明るく、軽やかな響きからは、微笑みや幸せな表情が想起されます。人々が笑顔でいるような明るい場面が思い浮かびます。
4.繊細な楽器の音色を連想させることもあります。例えば、ピアノやヴァイオリンのような楽器の高音域の音が、優雅で繊細に響くイメージです。まとめ:輝き、瞬間、染みる、鋭さ、明るさ、軽やか、繊細このような印象をもつのが日本語における「い」です。「い」音が使われている単語・オノマトペ
上記のイメージを想起させる「い」音からどのような単語がつくられているでしょうか。ここでは例によって日本語の単語を考えていきます。・「いたい!」「いい!」…瞬間
0

「あ」の話(音のイメージ①)
どんな内容?何のブログだろうと思われたかもしれませんね笑タイトルのとおり、一音「あ」について少し語ってみようという記事です。音韻論とか音象徴とかとか、そういった領域の内容を簡単に紹介しようと思います。音のもつイメージ、これを捉えようというのが大テーマです。文学的表現の向上やワンランク上のコミュニケーションを目指す方向けの文章になります。基本的説明
「あ」は日本語の母音のひとつです。五十音図の最初に位置し、日本語の単語や音節の中で非常に頻繁に使用されます。
口の形や発音の特徴
口を大きく開けて、のどからの息を自然に出すことで発音されます。舌は下あごの前に置かれ、口蓋の上との間にスペースがあります。発音すると開放的で、よく響く音になります。こういった筋肉の使い方や音の特徴というのが、次のイメージに大きな影響を与えてきます。想起されるイメージ
ここが、本記事のメインです。「あ」という音から導出される感性、感覚、感情といったものを思いつくまま深掘りしていきたいと思います。1. 「あ」は穏やかで優雅な響きを持ち、柔らかな朝日の光が心地よさをもたらすような感覚を与えます。2. 「あ」は穏やかで広がりのある音であり、澄んだ水面に投げ込まれた石が広がる波紋のような感覚にさせられることがあります。3.「あ」は開放的な音であり、まるで鳥が自由にさえずるような雰囲気を連想させます。4.「あ」はリラックスした状態を表現し、深呼吸をするような安らかな感覚を想起させます。
まとめ:穏やか、優雅、心地よさ、広がり、開放感、リラックスこのような印象をもつのが日本語における「あ」です。「あ」が使われる単語やオノ
0

【2023.05.28】作文を学んで、算数を伸ばす!
久々の投稿です。作文添削教室をしているから、という理由で作文の有効性を紹介しているのでは?と思われがちです。が、そんなことはなく、伸び悩み特に算数ができないと言っているお子さまたちには、共通の特徴があります。問題の趣旨が理解できないという課題50人のクラスで理科の点数が社会より高かった人数は、社会の点数が理科より高かった人より10人多い。社会と理科の点数が同じだった人数は6人であった。理科の点数が社会より高かった人数は何人か?答え:27人50人から6人を引いて、44人。これが同点以外の人数。つまり、「理科>社会」+「社会>理科」=44人ということ。「理科>社会」は「社会>理科」よりも10人多いから、「理科>社会」=「社会>理科」+10と表わすことができる。これを、「理科>社会」+「社会>理科」=44人に代入すると、「社会>理科」+10+「社会>理科」=44人。つまり「社会>理科」×2+10=44人。両辺から10を引くと、「社会>理科」×2=34人。よって、「社会>理科」が2つで34人だから、1つ分の「社会>理科」は17人。求められている答えは、「理科>社会」の人数だから、17人+10人=27人。この思考を、3分で正確に行うことが大切。これはサービス問題のようなもので、おそらくほとんどの受験生が正解する問題。何分で正しく解けるかがポイントなのです。国語的算数問題とは?これが、国語的算数問題のほんの一部です。算数を理解するというよりも、国語の構造を理解して解くというものです。何が何より多く、という整理整頓を頭の中だけでするのは無理でしょう。大学入試でも顕著ですが、数学や物理、化学の
0

【2023年1月22日】受験読解力とはどんなものなのか??
寒いですね。毎日ブログ更新を目標にしていましたが早くも断念してしまうという、意思の弱さ。ですが、大切なのはやめないこと。そう自分を甘やかして、またブログ書きを再開しました。今日のテーマは「読解力」です。読解力って、どんなイメージでしょうか?・読む・解く力ですよね。■読むってのは、・表面的な内容を理解する一方、■解くっていうのは、・奥側にある意図・真意を見つけるどちらも相関関係があって、読みながら解くというイメージです。読むということを詳しく説明表面的な内容ってのは、5W1H的な「いつ」「どこで」「だれが」「なにを」「どのように」を理解することですね。事実を正しくおさえる、意外と難しいですし、テストで問われる範囲としては7割ぐらいこの事実確認です。試験のわずかな時間でこの事実確認を行うのは難しいものです。そのため、・出題された文章の「タイトル」からの全体把握・各設問を先読みしてから本文を読んで、ピンポイント事実確認。※先に問題を読んでから本文を読むと、問われている内容の事実確認が早くできるたとえば、このような時間短縮のワザができます。事実確認は、このあとの「解く」とも絡まり合いますが、まずは表面的な理解を進めるということがポイントです。解くということを詳しく説明解くというのは、これまた厄介な話で誤読をしやすいんですよね。筆者の意図または出題者の意図、を汲み取らないと「解く」ことができず書かれている文章の意図を理解しながら、出題者が答えて欲しい解答とはという出題者側の意図も把握するというものです。これはこうすれば正解というものがあるのではなく、どちらかというと「見つける」=発見する
0

大学入学共通テスト国語2023:論説文出題に見た「引用」への問題提起
大学入学共通テストを受験された皆様、お疲れさまでした。仕事柄、毎年国語の問題は必ず解きます。今年は生後二か月の乳児を膝に抱えて解きました。。さて、今回の出題で印象的だったところを大問ごとに書いていきたいと思います。まずは大問1の論説文について編。なお、私の別ブログ(note)でも、同様の内容を記載していることをご容赦願います。論説文で印象に残ったのが「引用」の効果についての出題です。情報化社会の中で、情報の真偽を見抜く力が今まで以上に求められる中、厄介な存在である”引用”の難しさを問題提起した(出題者にそこまでの意図があったのかわからないが、おそらくあると思う)問題だと感じました。引用が「厄介」なのは、「原文そのまま引用していますよ」というと、あたかも原文の趣旨を保っているかのように見えてしまう点です。しかし実際は、前後の文脈や、「中略」という”悪手"によって、原文の趣旨はいかようにでもねじ曲げられます。
今回の共通テストの論説文では、二つの文章で同じル・コルビュジェの『小さな家』が引用されているわけですが、問6の(i)で問われているように、二つの文章は方向性が異なるのにも関わらず、その根拠として同じ文章の同じ部分が使われているのです。
文章Ⅱでは、前後の文脈に合わない部分が【中略】という裏技によってカットされています。そのことに気づかせる問6(i)はなかなかに批判的で、よい出題だったと思います。
現実世界でも、(意図的にせよ、そうではないにせよ)元の記事の引用に、趣旨をねじ曲げるような解釈を加えて再発信する例は枚挙にいとまがありません。国語の新指導要領では、批判的な情報処理力
0

【YouTube】国語の文法まとめ ~第1章 11節:助詞~
皆様、ごきげんよう! 今回共有させていただく動画は、「助詞」についてをまとめた動画です。 動画では、ポイントのみをまとめており、例文を省略しているのですが……ココナラブログ内では他サイトのリンクを共有することができないので……ココナラブログ内で私なりに考えた例文等の紹介ページを作ったほうがいいのでしょうかね? 悩みどころです。 しかし、基本的なポイントは動画でも十分確認できますので、高校入試対策等に活用していただけると嬉しいです!!
0

【YouTube】国語の文法まとめ ~第1章 10節:助動詞~
皆様、ごきげんよう! 今回共有させていただく動画はこちら! 「助動詞」の動画はちょっとだけ長めですが、頑張ってポイントをまとめたので……。各助動詞の活用、意味・用法、助動詞の覚え方をまとめています。 家庭学習や高校入試対策等で活用していただけると嬉しいです!
0

【YouTube】国語の文法まとめ ~第1章 9節:感動詞~
皆様、ごきげんよう! 今回共有させていただく動画はこちら! 品詞をピックアップしていく動画のそこそこの本数になってきました。動画そのものは、結構シンプルにできていると思います。気になるテーマだけでもいいので、観てみてくださいね! 定期テスト対策や高校入試対策等に活用していただけると嬉しいです!
0

【YouTube】国語の文法まとめ ~第1章 8節:接続詞~
皆様、ごきげんよう! 今回共有させていただく動画は、「接続詞」についてです。定期テスト対策や高校入試対策に活用していただけると嬉しいです!!
0
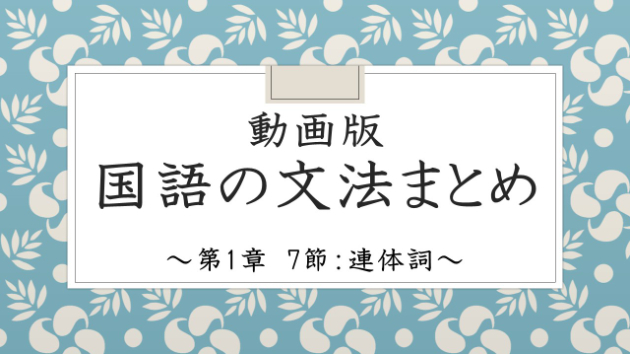
【YouTube】国語の文法まとめ ~第1章 7節:連体詞~
皆様、ごきげんよう! とても久しぶりですね……ココナラブログの投稿。 ブログは久しぶりですが、YouTubeでの動画投稿はちまちまと続けておりました。今回共有させていただく動画はこちら。 今ちょうど、高校入試直前対策の時期なので、文法のおさらい・最終チェックに活用していただけると幸いです。※序章~6章の動画については、過去に投稿したブログで共有しております。よろしければ、そちらもご覧ください!
0

歳時記( さいじき )
小学5年生の息子が学校から帰ってきたら、
「さいじき、家にある?」と聞かれました…
え?歳時記…そもそもなんだったかな…と心の中で思いながら、「なんで必要なの?」と聞くと、国語の俳句や短歌を授業で習ったときに、歳時記に色々載っているって先生が言っていたそうで。
おーなんとも勉強熱心ではないか^^と感心しながら、ネット検索…w
歳時記:四季の事物や年中行事などをまとめた書物のこと。
主として俳句の季語の解説や例句が載っている書物。
ただ、本物の歳時記は大人向けで細かく季語が辞書のように載っているので子どもにはわかりにくそう…
そこで、子供用歳時記で検索したところ、
ありました!!
『心をそだてる 子ども 歳時記 12か月』
講談社 出版
カラフルでイラストも載っていて、子どもが読むにはピッタリです!
現代では使わないもがたくさん載っているので、これからの子ども達は必要な知識なのかな?と思ったりもしますが、
日本の四季や歴史、文化を知る、昔の人々の生活や気持ちを知るにはやはり必要な知識かと思います。
俳句はその時代を生きた人々の景色や心・気持ちを表しています。
それを理解することは、まさに子どもの心を育て豊かにすることに繋がると感じました。
最近、四季を感じることが少なくなっている気がします。
日本の良さでもある、春夏秋冬。
私が子どもの頃はそれぞれの季節を感じながら過ごしていたのですが、
今は気候変動により、春や秋を感じる日数が少ない気がします。
夏暑く、秋も暑く、冬もあたたかい…
そして一気に冷え込む。気づいたら真冬…
それにコロナもあり、様々なイベント・行事が減り参加
0

「雨上がり体育」
【スポンジ捜索】
11歳の時
前日の凄い台風が過ぎ去って
快晴の青空が広がり
学校の校庭が水浸しになってた。
(´・д・`)ショボーン
その学校は
荒川区立第七峡田小学校と言い
校庭がコンクリートの校庭で
雨が降ると全然水がはけない。
このせいで4時間目の体育の授業が
国語の授業になってしまい
この事が嫌でリーダーの子が
校庭の水を取る作戦に出た。
水を取る方法は
校庭の水取用の巨大なスポンジを
以前見た事あるからそれを使い
校庭の水を取るというもの。
でもスポンジがあるは確証がなく
休み時間に体育倉庫を探しに行くが
スポンジが見つからず
ガッカリして戻ってきた。
(ノД`)・゜・。
しかし国語の授業が嫌で
諦める事が出来ず
次の休み時間もスポンジを探しに
体育倉庫に行ってみた。
すると体育倉庫の裏で
スポンジが干されてるのを発見し
これで校庭の水が取る事が出来
体育の授業ができると喜んだ!
〓=〓=〓=〓=〓=〓=〓=〓=〓=〓
【体育授業開催】
そして3時間目先生に水取用のスポンジで
校庭の水みんなで取るから
国語中止で体育しようと提案した。
すると先生は
「あの水全部取って体育するなんて
かなり時間かかるぞ」と言い
あまり乗る気じゃない。
( ;'д`)ウーン
しかしクラスの子達が
「国語より体育の方がいい!」と
みんなで騒ぎ始めたので
先生もしかたなく提案を飲んだ。
そして4時間目体操着に着替えリーダーの子達と体育倉庫に行き
巨大なスポンジ5枚と
小さなスポンジたくさん用意した。
4時間目が始まり
大きなスポンジで男子が水取し
小さなスポンジで女子が水取し
どんどんセ
0

「雨上がり授業」
【みんなでずぶぬれ】
11歳の時台風が来て大雨になり
あまりの風の強さと大雨で
5時間目の授業が中止になり
みんなで早退できた!
°˖☆◝(⁰▿⁰)◜☆˖°
しかし帰る時
みんな雨に濡れるのが嫌で
数人が傘をさして外に出るが
突風で一瞬に傘が破壊されてた。
数人が風の犠牲になったのを見て
残りの生徒が呆然としてしまい
雨に濡れて帰るしか方法がないと
このとき覚悟を決めたのだった。
そして1人の男子が先陣をきり
傘をささずに外に飛び出すと
一瞬でずぶ濡れになってしまい
みんな恐れおののいてしまう!
でもずぶぬれになった子は
何もかもどうでも良くなったのか
「気持ち~!」と叫んで
空を見上げてた。
なので我々も
その気持ち良さを味わいたくなり
みんなで一斉に外に出て
全員でずぶぬれになってみる。
すると本当に気持ち良くて
何だかもう全てがどうでも良くなり
確かにシャワーを浴びてるようで
爽快な気分になった!
(∩´∀`)∩ワーイ
〓=〓=〓=〓=〓=〓=〓=〓=〓=〓
【朝の仕事】
翌日の朝
完全に台風が通り過ぎてくれてて
すっかり雨も止んで空も快晴で
すがすがしい朝になってた。
その後おれは
飼い犬のダックスフンド2匹を
朝の散歩に連れくと
そこら中が水たまりになってる。
こんな日は
犬も散歩を嫌がりすぐ帰ろうとして
あまり歩いてくれないから最低限の
ウンチとおしっこをさせて帰った。
( ´ー`)フゥー...
散歩を早々と切り上げ家に戻ると
足の短いダックスフンドは
歩く時はじけれた地面の水が
全部お腹にかかってしまう。
なので雨の日は
いつもお腹がびしょ濡れになるので
タオルで
0

大変お世話になっている生徒さんについて+本紹介(国語教科書・IELTS問題集)
大変お世話になっている生徒さんについて(もっと多くの人・お客さんにきて欲しいと思ってこの記事を書いています。)本日、対面で個人授業をしてきました。この生徒さんは、1年7ヶ月ほどお世話になっている生徒さんです。非常に真面目で素直で謙虚で勉強熱心な方です。歳を取っても学び続けたいとおっしゃり、それを実行している数少ない方だと思います。本当にお世話になりました。この方は間も無く日本を離れるので、その前に、ひと段落として、授業を行わせていただきました。授業と言っても、僕が英語に関係ない話を含めて、色々お話しするという、授業とは言えないようなものでした。それでも2年間、通っていただきました。本当に感謝です。自分の拙い話に興味を持っていただき、英語だけでなく、英語にまつわる話(歴史、哲学、勉強の仕方、海外体験の話、DJの話、働き方の話、人間関係の話、運の話、オススメの本の話、など)様々、お話しさせていただきました。本日僕の授業(話)のよかった点をお聞きしたところ、「話が上手・様々な経験をもとに話してくれる・勉強の仕方・勉強の向き合い方を教えてくれる・勉強をしっかりしてきたなという印象を受ける・先生とDJという一見対極のことをしていて絶妙にバランスが取れている」などのお言葉をいただきました。自分はまだまだすぎる・未熟なのは当然として、引き続き勉強(机の上でも・外の世界でも)していかないとな、と思いました。本日オススメした本をいくつか紹介します。もっとあるのですがちょっと書ききれないですね。。。①光村図書 国語 3(中学校3年生の時の国語の教科書)温かいスープ 今村友信(読むと泣けてしまうくら
0

【無料公開】作文を書くということが大切だと思う人に
作文を書く、とってもめんどくさい小学生の頃、作文を書くのが嫌いだった。だけどいつの間にか、知らぬ間に書く仕事を選んでいた。上手に文章を書いたり、組み立てたりできる人はたくさんいます。長いこと書く仕事に従事していても、そんなにうまくなったとも思えないことばかりです。作文を書く、とてもめんどくさいです。算数の方が頭が活発になって、解けた時は達成感と爽快感があります。理科は物事の道理や仕組みが論理的に理解できた気がして、楽しいです。社会は幾層にも重なった世間の構造を理解すると大人になった気がします。国語は新しい言葉を学ぶたびに、その言葉をやたらと使いたくなります。作文を書く、向き合うのが自分だからなんだかめんどくさいんですよね。つまんないというか。そこからわかることは、自分の内面・内側だからかなぁ。だから作文は楽しいともおもうんだけど。作文を書くってことは、誰かに読んでもらうということでもあるそもそも書くってことは、伝えるってことだと思うんです。伝える、それは文字だけじゃなくて、声や態度、手話もそうですね。その中で伝わりやすいのは、なんだろう。作文のいいところは、文章にしているから、いつでも読めるってことですね。実際はそんな誰かが書いたものを、いつでも読むってことはないんだけど書くってことは、読んでもらうってこととつながっているんです一番の読み手は自分ってことを知る作文って書きながら、読んでます。読みながら、書いてます。自分で作った料理を食べながら作るみたいに、味見しながら完成させる。味見してるから、ついつい太ってしまうみたいに書きながら読むと、読みながら書くと、作文のアタマが太って
0

【無料公開】【塾なし合格ワザ】国語を徹底的に強化する10の勉強法-その2-国語力編‐
漢字の学習は国語学習の基礎になるのか?国語、やってもやっても伸びない。塾に行ったり、通信教育受けててもイマイチパッとしない。そもそも国語って、先天的な力で勝負するもの?つまりいくら勉強してもそれほど伸びない科目なの?
そんな質問良く受けます。
ちょっと整理しましょうか。
ダミーで僕自作の会話を紹介してみますね。
「国語の成績が伸び悩んでいます、どうすればいいですか?」
【何年生で、学校の国語の成績はいかがですか?】
「〇年生で学校の成績はいい方です。塾の模試でいつも偏差値が50を下回って」
【国語は好きですか?嫌いなのですか?お母さんからみてどう思いますか?】
「好きでも嫌いでもなさそうです。ただ国語は週2回塾にも行って基礎・発展も勉強していますし。。。でも成績が下がり気味で。。。」
これって、読んでどう思いますか?深刻さは何となく伝わります。
会話の中に足りないものがあるとしたら
そうです、「具体性が欠けています」
国語とは:
読み書きを通じて相手に自分の考えを伝えたり逆に相手の考えを伝えてもらったり、するために学んでいると思うのです。伝えるためには「具体性」
伝わるためには「具体性」
どちらも具体的でないと伝わりにくい。
具体性って何に支えられていると思いますか?
語彙とその用例だと思います。
ほんとにしょーもない例えですが
「暑い」という言葉しか知らなければ、「ほんのり暑い」みたいに形容しながらでないと伝えられないし、なんか日本語としてヘンです。
「暑い」と「暖かい」という2つの言葉を知っていれば、夏と春で使い分けができますよね。
そういう点で考えると、目的を持てば「漢字
0

【無料公開】【塾なし合格ワザ】国語を徹底的に強化する10の勉強法-その1-国語のカタチ編‐
国語の長文読解対策って、そもそも存在するんですか?
「国語ってどうやって勉強したらいいかわからない?」そんな声がいつも聞こえてきます。
「読書が好きだから、国語力がついて、長文読解もできるでしょう。」
なんて思って塾に入ったら、どうにもこうにも国語だけは伸び悩みなんてことに遭遇していませんか?五年生だと、まぁこれから伸びるでしょう、なんて思っていても
六年生になっても、さして国語が伸びない。。模試でも成績にムラがある。これってなぜでしょうか?個々の原因がわかれば、対策もできるってもんです。
今回の記事はルービックキューブの中にもありそうです。国語の入試問題を分解してみましょう
国語って、一般的には
・【知識】漢字、語彙、ことわざ、慣用句問題(たまに選択式)→とても簡単
・【論理】接続詞問題(選択式)→簡単
・【読解】あてはまる語(抜き出し式)→読めばできる
・【読解】あてはまる言葉(選択式)→慌てずに読めばできる
・【論理・読解】本文の説明と合う・合わないを選ぶ(選択式) →消去法も駆使して・【読解・記述】関連する事柄を説明する問題(記述式)→難しい
・【読解・記述】傍線部の内容を説明する問題(記述式)→難しい
・【読解・記述】理由について説明する問題(記述式)→難しい
・【記述】作文問題(エグイ記述式)→難しいといった具合です。
【知識】【論理】【読解】【論理・読解】【読解・記述】【記述】
というチーム編成になっています。
どうも読書をしていれば読解力が身についていて
塾に行って勉強していれば無条件に国語の成績が伸びる
というわけでもなさそうってことです。
国語は論理的に読解
0

必勝☆合格する小論文の書き方~小論文で失敗する人の特徴~
みなさんこんにちは。ポールです。初めてブログ投稿を行います。今回は、小論文の書き方について、簡単に述べてみたいと思います。□小論文で失敗する人の特徴 4つ①試験開始と同時に書き始める人 小論文の試験で受験者の様子を見ていて感じることですが、チャイム開始と同時にいきなり書き始める人がいますが、このタイプの人は注意してください。私の経験上、このタイプの人で成績や評価が高い人はあまりいませんでした。いきなり書き始めるのではなく、まずは自分の論の方向性や構成を練ってから書き始めるようにしましょう!②論理に一貫性がない人 小論文を書く時に大事なのはゴールを見据えていることです。賛成の立場でスタートした人が、途中で反対の立場がに変わってしまう人がいます。マラソンに喩えると最初順調に走っていた人が、途中で逆走したり、違う道を走ったりしてしまい、失格になってしまうことと一緒です。自分の決めたコースから外れずにゴールまで走り抜けましょう。③字数が9割に満たない人 600字以内、1200字以内で述べなさい。と指示がありますが、9割に満たさないで提出をしてしまう人がいます。これは大きな減点対象になります。最後書くことがなくて困るという人がいます。そのような人にオススメな書き方として、最後字数が余ってしまったときは、「その分野の展望や自分なりの提案」を書きましょう。小論文はそもそもまだ解答が出ていない未解決な問題に対してみなさんに考えを求めています。正解はありませんから、自由にみなさんなりの理想の展望やアイディアについて書いてみてください。④字が小さく汚い人 小論文模試は書かれてある中身で評価をするべ
0

この時期にお話できて良かった
今日は過ごしやすい良いお天気でしたね。洗濯物もよく乾きました。 さて、中学生は中間テストの個票も返ってきて、次の期末テスト、そして中3生は入試に向けて歩き出しています。 先日、ラボ生とテストについて話していた時に、「国語は先生がどう出すかがわかるから、点数がとれる。」と言っていたんですね。 それを聞いて、もしや!?と思い、 私「もしかして、出題するところとかを 教えてくださったり、ワークから出るとか?」 ラボ生「そうです!ワークからしか出ないので。」 「1年生の時はそういう問題じゃなかった ので、全然とれなかったんですけど、今は 大丈夫です。」 私「(心の中で)あちゃ〜><」 「それ、大丈夫じゃないなぁ〜。」 私「早いうちに実力問題にも取り組んだ方が 良いね。」 と話しました。そのラボ生は、なぜラボで国語をとっていなかったので、この時期にお話できて良かったです。まだ対策がとれますからね。 ホントセーフでした^ ^;必ずしも高得点=実力がある=安心ではないので、皆さんもよ〜く確認してみてくださいね。 それでは今日もゆっくりおやすみくださいませ。
0

【YouTube】VOICEVOXで古典を囁く ~竹取物語①~
皆様、ごきげんよう! 「古典を囁く」シリーズ第2弾。『竹取物語』です。草書体フォント・和風BGMと合わせて、雰囲気をお楽しみください!※フォントやBGM等の詳細は、動画概要欄にまとめています。
0

【YouTube】VOICEVOXで古典を囁く ~いろは歌~
皆様、ごきげんよう! 久しぶりのブログ更新です。 ブログは久しぶりですが、YouTubeの動画は結構ちまちまと投稿を続けていました。そのうちの1つを紹介します! VOICEVOXの九州そらさんに「いろは歌」を囁いてもらいました。本文の草書体フォントと和風BGMで、それっぽい雰囲気になっています。古典はまず「雰囲気を楽しむこと」が大事だと私は考えているので!※使用しているBGM等の説明は、YouTube内の動画概要欄にまとめています。
0

受験国語に読書は必要?
今年の担当している受験生の受験、すべて終了いたしました。まだ受験終わっていない方、がんばってください!さて、よく話題になるのが「国語の成績を伸ばすのに読書は有効か」という問題です。結論を言うと「読書は重要」です。これまで私も国語を担当することが多く、そういう相談をたくさん受けてきました。そして教室長が保護者の方に「国語の成績上げたい?だったら読書して」と言っているのを聞いて、「おいおい」と突っ込んでいたこともあります。はっきり言って、「国語の成績を上げる」=「読書をする」ではありません。つまり「読書をした」からと言って「国語の成績が上がる」というわけではありません。その理由としては、読解はテクニックなので読書では身につかないからということがあげられるかもしれません。またよく勘違いされるのが、国語の問題で「作者・筆者の意図」を問われていると思われていますが、実際には「出題者の意図」を問われているということです。読書の世界には「出題者」はいないことが、読書が国語力に直結しない一因でしょう。それでも「読書が重要」である理由はというと、「活字に慣れる」これに尽きます。最近はなんでも解説をする漫画であったり、YouTubeなどの動画、学習アプリなど、様々な活字を使わない学習方法があります。それでも忘れていませんか?残念ながら「テストは活字ベース」です。しかも最近は国語に限らず、他の科目でも「文章で出題」する傾向が大きくなっています。先日の共通テストでも、数学の国語化が話題になってましたね。さらにもっと先まで見据えるとまだまだ「論文は活字ベース」です。「活字に慣れる」ということが目的なので
0

【YouTube】ひらがなの筆順(濁音・半濁音)
皆様、ごきげんよう! 筆順動画を投稿しているので、順番に紹介します! 以前のブログでは「ひらがなの筆順(五十音)」の動画を投稿しましたが、今回は濁音・半濁音の動画です。皆様の学習のお役に立てたら幸いです。
0

【YouTube】国語の文法まとめ ~第1章 3節:動詞(前編)~
皆様、ごきげんよう! 新しい動画を投稿しました! 私のパソコンの都合で、動画として保存完了するまでにかなり時間がかかりました……。 今回から数パート使って「動詞」について学習していきます。前編の動画では、①「動詞」とは②活用の種類前編の補足動画では、①活用の種類の見分け方②五段活用の動詞についてというテーマです!
0

「赤色水夢」
【国語の授業】6歳の時3時間目にプールの授業があった。ヾ(*´∀`*)ノ俺はプールの授業で疲れ切ってしまい何だか眠い。(´ぅω・`)ネムイそして4時間目俺が1番嫌いな国語の授業があり絶対眠ってしまう予感しかない。しかし4時間目が終われば給食を食べて帰りの会をやり帰宅できので少し気合を入れた。そして先生が教室に来て国語の授業をはじめ教科書を開いた。でも教科書には文字がいっぱい書かれててそれを見るだけでももう眠い。こんな状況の中先生が教科書の朗読を始めて永遠読み続ける。〓=〓=〓=〓=〓=〓=〓=〓=〓=〓=〓【朗読】俺は今でも文字や文章や漢字が嫌いでもう既にこの頃から苦手だった。先生が朗読してると案の定朗読について行けずどこを呼んでるか解らなくなる。(*´Д`*)ワカランそんな時は皆が教科書をめくる音を頼りに俺も読めてるふりしてごまかしてた。そんな状態で国語の授業を受けてるからだんだん眠くなってきてウトウトし始めた。この時はもうプールの疲れで眠たくてしょうがなく我慢できない。そして俺は自分の頭が上下に動いてカクカクしてるのが解るくらいウトウトしてしまってた。そんな時先生に肩を叩かれ「は!」となり一瞬目が覚めた!Σ( ̄□ ̄|||)〓=〓=〓=〓=〓=〓=〓=〓=〓=〓=〓【机からの落下】しばらくするとまた頭がカクカクし始めてとうとう座ったまま眠ってしまう。(ノД`)・゜・。そして俺は寝た状態でバランスを崩してしまい横に倒れて机の角に「ごん!」と頭をぶつけて床に落ちてしまった!俺はこの瞬間目が覚めて何が起こったのか解らず当たりを見渡してみた。するとクラスの子達が一斉に笑い出す声が聞こ
0

【YouTube】はねる おん 【「ん」のつく ことば(ひらがな)】
皆様、ごきげんよう! ちまちまと作成していた動画が完成したので、投稿しました! 『国語の文法まとめ』シリーズの合間に、こんな感じの動画をまた投稿していく予定です。※私がパソコン内臓マイクに向かって読み上げた単語について。音質があまり良くないです。予めご了承ください!
0

中秋の名月と仲秋の名月
本日、2021年9月21日は「中秋の名月」で1年で一番お月様が美しいお月見にふさわしい日とされています。ん?1年で一番美しい?ここに私は子どものころ疑問を感じていました。「満月は満月やん」ここで「中秋の名月」について説明します。これは中学受験なんかでも国語、理科に関わってくる内容です。「中秋」というのは旧暦(太陰暦)に基づいています。旧暦では1月~3月が春、4月~6月は夏、7月~9月が秋、10月~12月が冬です。また旧暦は月の周期でこよみを考えるので、基本的に毎月30日までです。つまり、旧暦の秋(7月~9月)のど真ん中にあたるのが旧暦8月15日です。ですから、この日を「中秋」と呼んでいます。ただし、月の満ち欠けの周期は実は30日ではなくおよそ29.5日とされていますので、毎回15日が満月にはならないのがややこしいところです。今年は8年ぶりの「満月の中秋の名月」だそうです。ちなみに、旧暦の昨年12月は17日が満月、今年の1月は16日、その後は17日、16日、15日、16日、15日、15日、15日(←今日)となっています。旧暦でも月の満ち欠けとはこれだけのずれがあります。じゃあ、どうして8月15日が「お月見にふさわしい日」なんでしょうか。これは個人的見解ですが、お月様側の問題ではなく、人間側の問題のように思っています。つまり、旧暦の8月ころになると、かなり涼しく過ごしやすくなっています。今よりも気候が穏やかだったかもしれませんが、それでも扇風機すらない時代。日没とともに昇り始める15日ころの月をみて、着物を着ていても涼しく楽しめるのがこの「中秋」だったのかもしれません。7月(旧暦)
0

【YouTube】撥音・促音・長音を覚えよう! 【Japanese alphabet ‐HIRAGANA & KATAKANA‐】
今回の動画では、〇撥音(はねる音)〇促音(つまる音)〇長音(のばす音)をまとめています。 表記のルールについては、少し難しく感じる部分もあるかと思いますが……。誰かの学習のお役に立てたら幸いです。ぜひ観てください!
0

七夕は旧暦で
今年(2021年)の七夕も雨でした。7月7日の七夕は雨が多いなって感じますよね。まあ梅雨の時期ですから仕方ないですよね。でももともとは旧暦の行事です。旧暦の7月7日と言えば、新暦で言うとだいたい8月中頃2021年で言えば8月14日です。そのころには梅雨も終わっています。そしてもっと重要なのが日付。旧暦は月の動きをもとに作られています。小学校でも5年生あたりで習うところです。旧暦では1日が新月、15日または16日あたりが満月。7日は上弦の月(半月)の少し前。形としては半月よりも少し欠けている感じです。国語でときどき出てくる宮沢賢治の「なめとこ山の熊」に「6日の月」というのが出てきますが、それよりは少し膨らんでいます。しかし大事なのは月の形ではなく、月が見える時刻です。小学校の理科で、なぜ月の形が変わるのか習っています。月の形=太陽との位置関係なので、形によって月の出、月の入り時刻がある程度決まってきます。しかし、中学受験生でも今一それを体感していないため、ピンとこない生徒が多いようです。たとえば「三日月は真夜中には見えない」と言っても、たいてい???という反応です。(もしかしたら大人でもそうかもしれませんが)その後、ジャイアンの話をしたりもします。(その話はまたの機会に)で、話を戻すと旧暦7日の月は、必ず真夜中少し前に沈みます。ちなみに2021年の場合は東京で21時57分ごろ、大阪で22時15分ごろが月の入り時刻です。つまり午後10時前後には月は沈み、空は星を眺めるのに適した明るさになります。月のない空では天の川もきれいに見えるかもしれません。ぜひ今年は旧暦の七夕に星空観察してみ
0

模範解答は絶対的存在ではない
子どもたちの多くは「模範解答は絶対に合っている」と思っています。いや、何なら「模範解答は『神』だ」くらいの感覚の子どもたちもよく見かけます。場合によっては大人である保護者や、ひどい場合には学校の先生でもそれくらいの感覚の方を見受けます。そんなわけありません。「模範解答は人間が作っている」場合によっては問題集の解答などはアルバイトが作っていることもあります。この「模範解答」教とでも言うべきものに入信してしまうとやっかいです。どの科目でも問題集の模範解答が間違えているということは、学年が進むにつれてよくあることです。また、間違えていなくても解答の記述方式が2つ以上あるのに、模範解答が1つしか書いていないということもあります。たとえば算数で、解答方式に指定がなければ小数で答えても分数で答えても問題のないことがよくあります。(有限の小数、既約分数などの条件はありますが)しかし模範解答にどちらか一方しか書かれていなければ、別の方を書いた子供は×だと思い込んでしまいます。国語はもっとやっかいです。自由記述の問題の模範解答は解答例に過ぎないこともよくあります。それでも「模範解答」教の信者の子どもたちは、全く同じ答えが書けない自分のことを責めます。私が子どもたちに何かを教える場面で、模範解答を示す必要があるときは「モハン・カイトーさんの答を見てみよう」と擬人化します。模範解答は「神様」ではなく「頭のいい友だち」くらいの感覚で見た方がいいかなと思います。そしてやっかいなのは、小学校の先生に「模範解答」教の信者が結構いらっしゃることです。保護者の方はちょっと気を付けておいた方がいいポイントかもしれ
0

[国語]主語と述語の悩ましき問題
先日「[国語]成績アップにつながらない声かけ」という記事で書いた「主語・述語」の問題についてご質問があったので、詳しくお話しします。私としては、記述力にもつながる重要な部分だと考えていますが、細かい話になりますので、興味のない方はスルーしてください。「たぶん国語で子どもが混乱する第1位じゃないかなと個人的に思います。」と書きました。まず、お子さんに質問してみて下さい。「主語と述語って、どっちから探す?」「述語から」と答えたかたは大丈夫です。「主語から」と答えたかたは要注意です。中学受験専門塾などに通っている方は、たいてい「述語から」探すように教わっているかと思います。しかし、小学校では「主語から」探すように教えている先生が多いように感じます。これ、日本語の構造を理解していれば、ありえないはずです。たとえば、「太郎くんは、学校に 行った。」くらいの短い文であれば、主語から探してもおそらく正解できるでしょう。主語は「~は」「~が」にあたる部分ですよと言われれば、そりゃまあ「太郎くんは」をたいていの子どもは選ぶでしょう。述語は「どうする、どんなだ、何だ」にあたる部分だと言われれば、「行った」を選ぶでしょう。低学年のうちに、こんな指導法で「〇」をもらって主語・述語を理解していると思っていると、高学年になり、複雑な文が出てきた場合、対応しきれないと思います。なぜか。「日本語の文は文末に述語があり、それに対応する主題または主格を表す言葉が主語だから」さらに複雑な文になると、文の成分としての「主語・述語」とは別に文節と文節の関係において「文の主語・述語」以外の「主語・述語の関係」が存在するこ
0

[国語]成績アップにつながらない声かけ
国語を担当していたり、塾で教室を任されたりしているとよくある相談が「国語の成績をあげるにはどうしたらいいですか?」という質問です。国語ってどうやればできるようになるのか、その方法をあまり考えずに過ごしてしまうということがよくあります。もちろん、それぞれのお子さんによって事情は異なるので、「これだけやれば、大丈夫」なんてものはありません。でも、それなりのメソッドはあります。もし国語の成績が伸び悩んでいるかたは、ぜひご相談ください。そして、今回のブログで紹介するのは、「国語の成績アップ」のための回答で要注意なもの。①「とにかく読書をどんどんすれば、国語の成績あがりますよ」この言葉は、私が国語を担当していた中学受験専門塾の教室長が保護者の方に答えていた言葉なんです。といっても10年以上まえの話ですが。ここ10年ほどで国語の指導法についての本なども、よく目にするようになったので、最近ではこのような回答はあまりないかもしれません。もちろん、読書をして国語の成績を下げることはないと思いますが、中学受験をしようという生徒に、「読書」だけで対応するのはなかなか難しいかと思います。なぜ「読書」だけでは足りないのか、また改めて記事にしたいと思います。②「文章のなかに答えがあるんだから、探せばいいんだよ」これも間違いではありません。もちろん状況によっては、そのように答えることもあります。でも「国語がわからなくて、なんとかしたい」と言っている生徒にこれは言いません。探し方を教えるのが、国語です。③「とりあえず漢字とか語句をがんばれ」これもその通りかもしれません。実際に中学受験の国語では実質5割近くが漢
0

【そっちよりこっち見て! 認知の歪み⑦】
自殺対策支援センターの電話相談員の件、
本日の二次審査では、「身を捨ててこそ
浮かぶ瀬もあれ」とまではいかなかった。
一次審査の時のように、「死の問い」を
しないという致命的なミスはなかったが、
「絶対に大丈夫」だと自信を持てるほど
確り傾聴できた訳でもない。希死念慮が
高く、「話を聴いてほしい」「こういう
自分がいることを誰か一人にでも知って
ほしい」という気持ちを受け止めるのが
精一杯で、「聴いてほしい」という話の
腰を折るまいとひたすら耳を傾けている
うちに時間は経ち、社会との関わり方を
一緒に考えることはできませんか?との
申し出は拒否され、「死にたい」という
気持ちを否定せず受け止めるのみだった。
審査を通過する自信はないが、今の私が
心理カウンセラーとして出来得ることは
成し得たので例え不合格でも悔いはない。
合否連絡は一週間以内にメールであるが、
一週間後の3月19日は自分の誕生日だ。
今まで、高校の合格発表、運転免許取得、
新聞の投稿の掲載連絡、これらのことが
誕生日にはあった。つまり、誕生日には
自分で自分にプレゼントしているように
結構目出度いことが多い。そう考えると、
来週の誕生日に良い知らせがあると思い、
期待して待つくらいが丁度良い気がする。
────────────────────
メンタルヘルス不調の人が悪循環に陥る
ネガティブな思考の癖にアプローチする
認知再構成法とは、過度にネガティブな
気分・感情や不適応的行動と結びついた
認知(自動的な思考やイメージ)を同定
して様々な視点
0

思い出「雨上り・ダイブ」
【雨上がりの散歩】11歳の時夜に大雨が降り夜中音がうるさくて眠れない。 ┐( ̄_ ̄)T;;; 雨でもよく朝起きたら雨がすっかり止んでいて空が晴天になっている。凄く気持ちが良い晴天の中俺は犬の散歩に出かけた。しかし大雨の後で地面が水たまりだらけ。俺の靴が濡れ犬も濡れるのを嫌がって全然散歩してくれない。仕方ないので犬のウンチとおしっこだけさせて散歩を短めにスグ帰って行った。U^ェ^U ワウワウ!俺の靴がずぶぬれになり「足元だけでも濡れると気持ちが悪いのに体中濡れる犬なんて凄く気分悪いだろう」そう感じて可哀そうだった。〓=〓=〓=〓=〓=〓=〓=〓=〓=〓=〓=〓【嫌いな国語】そのあと俺は家に戻り犬の体を拭いて学校の準備をする。この時地面が水溜まりだらけで「今日体育の授業があるけど絶対中止だろうな」と感じてしまう。(ノД`)シクシクそして俺は体育が中止になった時の代替授業の準備をして学校に向かて行った。体育が中止の時の代替授業は俺が大っ嫌いな国語の授業。ヾ(≧Д≦)ノヤダヤダ出来る事ならやりたくないと思い学校に到着すると案の定校庭が水びだし。もう100%国語決定で俺の気持ちがどんより曇った┐(´д`)┌ ウンザリそして空が晴天なのに俺の心は大雨のまま授業が始まった。〓=〓=〓=〓=〓=〓=〓=〓=〓=〓=〓=〓【怪しい行動】体育の授業は4時間目にある予定。お俺もみんなも体育の授業が好きで国語の授業が大っ嫌いだった。そんな思いが皆にあり4時間目までに校庭の水が渇かないかみんな期待していた。1時間目の授業が終わり休み時間になると悪ガキ5人組が教室からいなくなった。そして次の授業まで
0

国語力をのばす3つの力
僕が学生の時に一番苦手だったのが国語です。その主な理由は勉強のやり方がわからなかったことにあります。「主人公の気持ち?知らないよ」「筆者は何がいいたいのでしょう?わからんよ」そもそも答えを求められるけど、答えが1つではない気もしてくる。「あれ?こっちの答えもそれっぽいな」「こうとも言えなくないのでは?」算数や数学のように公式を覚えて計算して答えを導く道筋がわかるなら練習のしようがあるものの、全ての物語の筆者の考えや解釈を覚えるなんてムリだ。せいぜい覚えられるのは漢字くらい。だから国語の勉強=漢字の暗記と捉えていました。そんな風に覚えたものだから、今度は国語を教える立場になった時に困ってしまいました。一体国語をどのように教えたら良いのだろう。文章や物語の解釈はどのように教えたら良いのだろう。文法は教えられるけど、読解力をどのように身につけさせることができるのだろう。困ったときのグーグル先生。調べてみて出会ったのが、福嶋隆史さん著の「国語授業力を鍛える!」という本。めちゃくちゃおもしろかったです。今までモヤモヤしていた国語に対する考え方がガラリと変わりました。腑に落ちる考え方も多かったので、皆さんにもお話したいと思います。【そもそも国語の教科目標って?】文部科学省による中学校学習指導要領によれば国語科の目標はこうあります。"言葉による見方・考え方を働かせ、言語活動を通して、国語で正確に理解し適切に表現する資質・能力を育成することを目指す。"「言葉による見方・考え方を働かせる」とあります。つまり、考える力=思考力を使いましょうってことです。では思考力とはなんなのか。どんな能力で、どう
0

中学受験の明日のために その64 国語の大切さ
以前算数の大切さを述べましたが、今回は国語の大切さを述べようと思います。算数と国語は、多くの学校で理科や社会より配点が高いことが多く、合否に大きく関わってくる科目です。特に算数は、1問あたりの配点が大きいために差がつきやすいです。一方国語は日本語なので、ある程度誰でもできる科目なため、ないがしろにされやすい傾向があります。特に男子は算数ができて国語が苦手という子が多いです。私がまさにそうでした。ここで国語をほとんど勉強せずに算数ばかり勉強すると、後々困ることになります。中学受験は、国語が苦手でも、誰でもある程度はできるためにそこまで差がつかず、算数が飛び抜けてできれば合格する場合があります。大学受験では、国語のいらない学校があり、数学だけが飛び抜けてできると突破できたりします。しかしこれが危ないのです。大学生以降は、文章を読まなければいけない場面が山ほど出てくるからです。大学生から伸びなくなる人は、決まって国語ができない人なのです。国語が苦手でも、逃げずにしっかりと勉強しましょう。国語が苦手な人は、大抵本を読むことが嫌いです。中学生になったら、漫画でも構わないので活字に触れる事が大切です。私は20歳くらいまで、活字だけの本を一冊も読めませんでした。それでも漫画を通して活字に触れていたために、何とか大学入試まで突破する事はできました。ただずっと活字の本を読めていない事がコンプレックスだったために、大学生になってからようやく本を読めるようになりました。これも中学受験の国語で最低限の勉強はしていたことと、中学生以降に漫画を大量に読んでいたからだと思います。社会人になった今では、読書
0

読心術に全集中
噓をついてはなりません。幼い頃から、私たちは大人からそう言われて育ちます。噓も方便などという場合がなくはないですが、だいたい噓は悪と決まっています。ところが、嘘が許される、いや、むしろ上手い噓であればあるほどほめられる世界があるのです。それは「フィクション」の世界。映画、テレビドラマ、漫画、アニメ、ゲーム、芝居など、あげればきりがありません。それらは娯楽、エンターテイメントなどと言われて、人間の楽しみのため存在します。もし、これらのものがなければ、人生はずいぶんつまらないものになるでしょう。そして、国語にもフィクションの分野があります。小説です。教科書にも載っていますし、入試問題にも出ます。事実に基づいて書かれたノンフィクションというものもありますが、小説というのは、たいていの場合は「作り話」です。所詮、「作り話」に過ぎない小説に振り回され、テストの点に一喜一憂するのは、いかにも悔しいではありませんか。
ところで、教科書で習う小説は面白いですか。印象的で心に深く残っている作品はあると思います。でも、面白かった、楽しかった、わくわくした、という経験はあまりないと思うのです。それがない自分はだめなのではないかと思う必要などまるでありません。それが普通です。なぜならば、国語の小説は娯楽のために書かれているわけではないからです。もちろん、娯楽のための小説という世界はありますが、残念ながら教科書にはほとんどないし、入試問題でもほぼ見かけません。
では、娯楽と無縁であるなら、国語系の小説は何のために書かれるのでしょうか。それは人間の心理・心情をいかに細やかに描くか、ということです。人間の心
0

迷宮入りの未解決問題
連載漫画。先が読みたくて、次号を楽しみにする。そういう具合に「続きもの」の作品がある一方で一話完結、読み切りという漫画もある。国語の教科書の文章というはたいがい「読み切り」である。説明的文章の場合は、その中で「テーマ」とされる問題提起というものが解決する、というふうになっている。
入試問題の国語は基本的に「切り取り」である。筆者の一冊の長い本の中から、問題に合う、都合のよい部分のみを「抜き出して」いるのである。出典の書物には他にもまだいろいろなことが書かれているのだが、問題としてのサイズや設問づくりに適切だからこそ、その部分が選ばれたのである。
最も読みやすい論説文というのは文章の比較的初めの方に、問いかけ、問題提示があり(序論)、それについて途中、いろいろ考察することで論が展開され(本論)、最後に筆者の主張が述べられる(結論)というパターンである。自分が作文・小論文を書く側になった場合も、これを基本とすれば良い。難しい問題というのはいくつかのケースがあるが、そのうちの一つが、この型にはまっていない(ように思える)「型破り」な文章である。「定型外」であるために、文章がなかなか頭に入ってこないことがある。こういうときは読み取りにくい。
だが、いくら定型に沿わないこともあるからと言って、次のような文は絶対にない。⓵さんざん持論を述べた挙句、結局のところわかりません、というように問題が未解決のまま終わる。②結論も出ないでまだ本論の途中で文が途切れて終わる。➂問題も解決し、結論も出たが、最後にまたあらたな疑問が提示され、「問いかけ」のまま終了する。以上のような入試問題があれば、非
0

ふみをあむ
私はブログを基本的に「だ」「である」調の文体で書いている。何故ならば、それが普通の文章だからだ。「です」「ます」調のことを敬体というのに対して、これらの「だ」「である」調は常体と呼ばれる。「いつもの、普通の」スタイルという訳である。話すときは私も場面に応じて敬語を使う。特に丁寧語を使って話すと、会話の流れが柔らかくなるし、人当たりもよくなる。だが、話し言葉と書き言葉は別のものである。敬体で書いてある説明文、論説文、評論文、随筆、小説がまるでない訳でもないが、通常、文章は常体で書かれている。この方が断定的で歯切れよく、締った印象を読み手に与える。私の文章も、いかにも「偉そうな感じ」がするかも知れないが、それは常体で書いているからである。
入試における国語の一般入試内の課題作文、推薦入試に課せられる作文・小論文も基本的に常体で書くことをお勧めする。敬体で書くと、「だ」が「です」、「思う」が「思います」になるように、どうしても字数が多くなりがちである。思いつくままにただ書いて良いのであれば別だが、字数制限というものがあるので字数オーバーというわけにはいかない。書く題材が豊富にある場合、字数は節約して書きたいところだ。そのためにも、常体で書く必要がある。
もっとも、内容が的はずれであったり、稚拙なものだったりする場合に常体で書くと、中身が伴わないのに無理している印象になるので、そのときは敬体を勧めている。そのような生徒はだいたい書くのが苦手というケースが多いため、「です」「ます」体の方が字数を稼ぐことにもつながる。
0

【2023年1月12日】音読せんかい、音読千回!
寒い。冬だから。日本の冬ってなんで寒いの?地軸が傾いて自転していることで、日本がある北半球は、冬になると太陽からの光・熱を受ける面積が減るから。説明難しいですね。図が必要だ。で、そんなことよりも、音読ですよ学校の宿題、最大の謎。音読ーONDOKUなんか、呪怨ーJYUON みたいですね。音読やってます?きちんと親サインしてます。めんどくさがらずに、聞いたふりしてください。トンビの子って、書いて覚えないんです。声に出して、読みながら英単語や古語、漢文、数式もろもろ覚えるんです。それでも覚えられなかったことを、書いて覚えているそうです。音にする、声に出すことで、頭に意味が入るつまり、音読の効果はこういうことですよね。黙読って、高度なテクニックで相当読解力がないと読み込めません。音読は、1文字を目で見て2声に出そうと頭が理解して3声に出して4出しながら、意味を理解していく作業です。1から4をショートブロックで繰り返すことで、音とリズムが加わって理解が深まるんですね。その際、字面だけでなく音とリズムが加わって、意味が頭に浸透して読解力が高まるんだと思います。あわせて、記憶していくようになる。小学校の国語の教科書、同じところばかり読んでいるけど小学校に限らずですが、国語って教科書の一つの小説・随筆・論説文をくり返し勉強しますよね。テストもこれだけ読み込んでたら、覚えているから接続詞も漢字も、文意も全部覚えて書けるじゃない。だから国語のテストでどんだけいい点とっても、初見の国語の問題が解ける読解力が身にはつかない!!!と思って、学校の国語を勉強しても、音読してもさほど意味がないと思っている方
0
あなたも記事を書いてみませんか?
多くの人へ情報発信が簡単にできます。
ブログを投稿する
多くの人へ情報発信が簡単にできます。






.png)



.jpg)

































