すべてのカテゴリ
新着有料ブログ
87 件中 1 -
60 件表示

自然界に生まれ変わりはない。あるのは、諸行無常の移り変わりの歴史、それがDNA
■生まれ変わりと移り変わり沢山の鑑定依頼を受ける中で、
亡くなられた方の鑑定をすることも多くあります。
ペットさんの質問で多いケースにはなりますが、
亡くなられた方に対して、
「今どこでどのように過ごしていますか?」
「天国から見守ってくれていますか?」
「たまには会いに来てくれますか?」
「生まれ変わったら、また会いに来てくれますか?」
この様なご質問を受けることは、
クライアント様の十中八九程度の割合であることなのですが、、、
陰陽五行説は自然哲学になり、
自然哲学は自然科学の基になります。
ですので、陰陽五行説は、
基本的には自然科学の立場を支持致します。
自然哲学の方が群は広い訳で、
自然科学の立場で立証できないことを排除する必要はありませんが、
自然科学の中でそれなりに確立している理論と相反する主張が為されている際には、
それ相応の論理性とロジックレベルの高さは求められるものとなります。
ここからお話する内容は、
そんな自然哲学に基づいた陰陽五行説の一つのモノの見方になりまして、
必ずしもこれが正しいとか、
これ支持するとか、
そういうことを考える必要もないものになるかとは思われます。
生まれ変わりや天国や地獄、霊魂とか、
そういうものを考えたりする、
例えば、仏教やキリスト教やその他の宗教等もそうなのかもしれませんが、、、
陰陽五行説では、
“生まれ変わり”は考えないことが多くあります。
その代わりに“移り変わり”というものを考えます。■移り変わりとは?移り変わりとは、
諸行無常のことになりますが、、、
例えば、ペットさんが亡くなって、
土に埋葬したり致しま
0

毎日薬膳~2024年3月1日から2024年3月31日
おうちごはんを極めて健康ライフ!
バランスの取れた食事を目指すには季節の食材で様々な色をそろえるのがポイントです。
3月1日
炒飯
3月2日
ステーキ定食
3月4日
チキンライス(チキン無し)
3月5日
ふろふき大根、すき焼き丼
3月8日
ステーキプレート
3月7日
韓定食
3月9日
鳥パイタン
3月10日
夜食は鳥雑炊
3月10日
メインはかまぼこ
3月11日
フルーツポンチ、チキンライス
3月13日
ライ麦パン。まずい
3月14日
薬膳カレーと温野菜
3月15日
牛丼とヒレカツ
3月16日
冷やし中華
3月16日
トマトと卵の中華炒め、3種イモサラダ、ピラフ
3月17日
一人の休日は体に悪いインスタントラーメンw
イッヒッヒ❗️
3月17日
筑前煮、柏飯、ワカメご飯
3月18日
和定食
3月19日
冷やし中華
3月20日
こんにゃく、鯛の煮付け、キノコ
3月22日
ボロネーゼ
3月24日
朝めし
3月27日
肉定食
3月30日
かやくご飯
0

東洋医学基礎知識~五行説~
五行説とは、地球上様々なものを 木・火・土・金・水 の五つに分類して関係性を考える学説のことで、東洋医学では五行説の考え方を重要視します。みなさん、五臓六腑という言葉、聞いたことありますでしょうか。この五臓とは肝・心・脾・肺・腎のことで、それぞれ木・火・土・金・水のグループに属します。(下図参照)この5つの要素には、相生(そうせい)と相克(そうこく)という関係性があります。・相生木は火を生じ、火は土を生じ、土は金を生じ、金は水を生じ、水は木を生ず上の図の赤矢印の関係のことです。この関係は五臓六腑にも当てはまります。例えば木のグループの肝が弱ってしまうと、火のグループの心も弱ってしまうという考え方です。・相克水は火に勝ち、火は金に勝ち、金は木に勝ち、木は土に勝ち、土は水に勝つ上の図のグレーの矢印の関係のことです。この関係も五臓六腑に当てはまり、例えば肝が弱ってしまうと脾を抑える力が弱くなってしまい、脾が暴走する可能性があります。このように、東洋医学は部分的なところではなく全体のバランスを見ながら不調を考えていきます。咳があっても実はお腹に原因があるなど、関係が無さそうなところに原因があったりするのは、この五行説の考え方があるからだったります。皆様もご興味がありましたら是非調べてみたりしてくださいね。
0

方位の良し悪しのせいにしない
皆さんは吉方位、凶方位というのを気にしますか?今日はそんな方位に絡んだ話をしてみたいと思います。あくまでも個人的な考えですので、素人の戯言と思っていただければありがたいです。吉方位、凶方位の体験談というわけで、吉方位、凶方位という概念について。わりと市民権を得ている分野だと思います。私もそれなりに気にしたことのある一人です。かつて引っ越しの際に参考にしたことがあります。そのうちの一つはいわゆる凶方位ではなく、可もなく不可もなくの方角でした。流派によっては吉方位以外はすべて凶ととらえるようなので、そう言われたら凶だったのだろうということになります。そこはこれまでの引っ越しの中で一番しんどい思いをした家でした。一年たったかどうかぐらいで再度引っ越しをしました。後からその方角は、騒音などの現象が現れるようなことが書いてある記事を見つけ、「ああ、やっぱり」と思ったものです。隣人の生活音ですごく悩まされたのです。その家の防音性能もあまり期待できるタイプではなかったこともあり、正直大失敗だった苦い思い出です。その後今度は吉方位を狙って引っ越しを決め、結果はどうだったかというと普通でした。特別いいことがあったわけでも、悪いことがなかったわけでもなく。しいて言えば、うまくいかないことがあっても割とすんなり解決できた気もします。今はまた別の場所に引っ越して、この時も方位は参考にしましたが、可もなく不可もなくの方角です。結果も同じく至って普通と思います。ここまで体験談を書いてきましたが、正直方位の吉凶ってあるんでしょうか?確かに当たっているような気もしますが、はたして本当にそうなのだろうか?とも思
0

理解すると生きやすくなるー陰と陽のバランスー
昔から陰と陽は対比であり常にバランスの取れたものだと言われています。このことを用いた非常に面白い話も数々聞いてきて自分の中で腑に落ちたり納得するものがいくつもあったので、今回は陰と陽のバランスについてのお話をしたいと思います。【陰と陽は常に同じバランスを保っている】陰と陽と言ってもいまいちピンと来ないですよね。身近で言えば良い事と悪い事は常に同じくらい起こると言われていると思えばわかりやすいと思います。良い事が起きたと同時に悪い事が起きるわけではなく時間をずらして起こるのと同じように、陰陽のバランスも数で同じわけではなく質で同じなのだと考えられています。常にどちらかだけが過多という事ではなく、その人の一生を通して最後には帳尻が合うように全てのことにバランスが保たれています。自分は運が良いとか自分は運が悪いと思っている人は印象に残る部分に目を向けていたり、まだ気づいていないだけで平均するとバランスが保たれてるといえるでしょう。ポジティブな人は悪い事を悪いままにせず自分の中で良い解釈へ変換させることができるので、同じ数や質量の悪い事が起こっても悪いだけで済ませない強い力があり「運の良い人」になってると考えられます。なので「私は運が悪いのに何であの人ばかり良い事が起こるの?」と嘆いている人もいるかもしれませんが、運が良い人もそれなりの良くないこと、陰の部分は経験しており皆平等なのです。バランスが取れていないと感じる人は感じる部分・着眼する部分の違いで思い込んでいるだけですので、視点を変えると見える景色も変わります。【嫌いな人が克服できる】陰陽のバランスと言いましたが実は人間関係でも同
0

風水はバランスを整える相学
風水の定義って難しい。。。占術には『命(運命)』『卜(ボク・偶然と決断)』『相(他に与える影響やバランス)』があり、風水はどこまでを⾔うのかというと、流派によって異なります。今回は風水の中でも『地相』『家相』の相の世界の話をしますので、『相』すなわちモノの配置がどう影響しあうのかを理解していく作業になります。陰陽五⾏説とは陰陽説とは、光と影、太陽と⽉、生と死、男と⼥など万物を陰と陽の2極に分け宇宙の成り⽴ちを説明しようとした思想で、紀元前6世紀の中国にはその概念が存在していたとされています。五⾏説とは、万物を木・⽕・⼟・⾦・水に分類して世界の成り⽴ちを説明しようとする思想で中国最古の経典にその存在がみられます。五⾏には⽊が燃えることにより⽕が生まれ、⽕が消えて⼟が生まれる。⼟から⾦属が産出し、⾦属が冷えると水が生まれる。最後に水を吸って⽊が育つという相生(そうせい)の関係と⽊は⼟の養分を吸い、⼟は水を吸う。水は⽕を消し、⽕は⾦属を溶かす。最後に⾦属は⽊を切るという相剋(そうこく)の関係があります。この2つの思想が古代中国、漢(かん)の時代に結びつき、陰陽五⾏説が生まれ占いから漢方医学、暦、年中⾏事まで⽇常生活に深く根付いています。ちなみ方位にもこの陰陽五⾏説が配属されています。ちなみに⻄は『⾦』で⽩や⾦⾊も『⾦』ですが、単純に⻄に⾦⾊を置けばお⾦持ちというわけではありません。家相全体のバランスを陰陽五⾏説で計っていくことが一番重要なことなのです。地相家相に完璧はない
地相家相には必ず凶がでます。⼈生の節目、世代が変わって家主が変われば今まで吉祥だった家相も凶に変わることが多々あ
0

実践!2024年福を呼ぶ「おせち料理」~九星気学同会法と陰陽五行説の相生・相克の理論に基づく開運方法~
■はじめに
「おせち」は中国から伝わった五節供の行事に食べられる「節目の日のための祝い料理」を示しますが、歳神様に捧げる供物としての正月料理を現在では「おせち」というようになりました。弥生時代に起源をもつようで、奈良時代には朝廷内で祝い料理として振舞われたようです。当時は山盛りになったご飯のみであったようです。おおよそ、現代の正月料理は江戸時代の武家文化に由来し、長寿、無病息災、子孫繁栄をその土地の名産を用いて作られます。おもにめでたさを語呂合わせや陰陽五行説の魔除けなどの思想が由来しているようです。江戸の長屋の住民もどんなに貧しくても祝三種である「黒豆」「数の子」「田作り(関西では「たたきごぼう」)」だけは必ず食べたという事が文献に見られます。
■陰陽五行説について
さて、「おせち」を理解する前に、陰陽五行説について理解を深めましょう。
陰陽説とは、光と影、太陽と月、生と死、男と女など万物を陰と陽の2極に分け宇宙の成り立ちを説明しようとした思想で紀元前6世紀の中国にはその概念が存在していたとされています。
五行説とは、万物を木・火・土・金・水に分類して世界の成り立ちを説明しようとする思想で中国最古の経典にその存在がみられます。五行には木が燃えることにより火が生まれ、火が消えて灰すなわち土が生まれる。土から金属が産出し、金属が冷えると水が生まれる。最後に水を吸って木が育つという相生の関係と木は土の養分を吸い、土は水を吸う。水は火を消し、火は金属を溶かす。最後に金属は木を切るという相剋の関係があります。この2つの思想は古代中国、漢の時代に結びついて陰陽五行説となったとされて
0

関係性
こんばんは。今日は寒い一日でしたね。四柱推命で生まれ日の六十干支(万年暦で生年月日をみると確認できる)を調べてみますと、自身は、50癸丑(みずのとうし)、相方は21甲申(きのえさる)です。癸は、水(−)丑は土(−)、甲は、木(+)申は金(+)で、それぞれ陰同士陽同士の組み合わせとなります。「陰陽五行説」では、森羅万象全てのものは陰と陽に別れ、木火土金水の5つ(五行)から成り立っていると考えられており、さらにそれが陰(−)と陽(+)に別れています。水と木の関係は木に水を与えて育てるので、母親と子供のような関係性ですね。そして、十二支でみると、がんこで動かない丑さん(自身)と興味深々で動き回る申さん(相方さん)、静と動の組み合わせとなりますね。日頃の生活を思い返すと、まさにその通りなのです😌四柱推命は学ぶほど奥深く、そして楽しい側面も兼ね備えた占術だと思っております。
0

五行陰陽の奥深き世界: 生命のエネルギーと調和の探求
中国の古代哲学に根ざす五行陰陽は自然のリズムと人間の存在を解明する魅力的な思想体系です。五行陰陽は、木、火、土、金、水の五つのエレメントと陰と陽の二つのエネルギーから成り立っています。これらの要素とエネルギーは、我々の身体、心、そして運命に影響を与え生命のバランスと調和をもたらします。1. 五行陰陽の基本五行陰陽は、万物がこれら五つのエレメントと二つのエネルギーの交流によって成り立っているという考えに基づいています。各エレメントは他のエレメントとの関係において生み出す、制御する、そして変容する力を持っています。2. 個人の五行エレメント分析五行陰陽占いは、あなたの生年月日に基づいて、どのエレメントが強くどのエレメントが弱いのかを解析します。この分析は、あなたの個性、強み、弱み、そして可能性を明らかにします。3. 五行陰陽と健康五行陰陽は、身体のバランスと健康にも関連しています。各エレメントは特定の臓器や体系と関連しこれらのバランスが健康を保つ鍵となります。4. 五行陰陽と恋愛運恋愛関係においても、五行陰陽は相性を判断する重要な要素です。あなたとパートナーのエレメントが互いにどのように影響し合うのかを理解することで、より調和の取れた関係を築くことができます。5. 五行陰陽とキャリア五行陰陽の知識は、あなたがどのようなキャリアパスを追求すべきかまたどのように仕事で成功を収めるかについての洞察を提供します。6. 五行陰陽と日常生活五行陰陽の原則を日常生活に取り入れることでバランスの取れた生活を送ることができます。食事、運動、睡眠、そしてリラックスの時間を五行陰陽のバランスに基づいて調
0
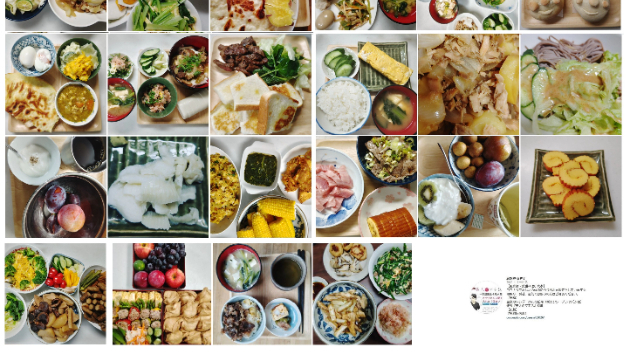
毎日薬膳~2023年9月1日から2023年9月30日
毎日薬膳~2023年9月1日から2023年9月30日
おうちごはんを極めて健康ライフ!
バランスの取れた食事を目指すには季節の食材で様々な色をそろえるのがポイントです。
9月1日
無題
9月2日
伊達巻
9月3日
フルーツいっぱい
珍しい竜眼が手に入った!
9月4日のおかず
9月5日
サラダそば
9月5日
ツナ缶大量消費レシピ
ツナじゃが
9月6日
和食ばんざーい
9月7日
ビリヤニとモロヘイヤスープ
9月7日
エンガワ
9月8日
フルーツヨーグルト
9月8日
ランチプレート
9月4日
美味しんぼより~再会の丼~
9月9日
手作りナンとカレー
9月9日
真夜中のパン工場
子供と例のアンパ○マン密造中
9月10日
おかずクラブ
9月19日
疲れたので、惣菜
9月21日
麻婆豆腐と茄子炒め
9月23日
あら汁 玉子焼、冷奴
9月24日
自家製きつねうどん
9月24日
自家製ローピン
9月24日
収穫祭その1
9月25日
収穫祭その2
9月25日
秋の魚(アジ、カサゴ、タイ)
9月25日
牛丼
9月27日
鯛のあら煮、ニラ玉ほか
9月28日
冷製パスタ
9月29日
一膳飯
9月30日
今日は楽しい運動会♪
0

毎日薬膳~2023年8月1日から2023年8月31日
おうちごはんを極めて健康ライフ!
バランスの取れた食事を目指すには季節の食材で様々な色をそろえるのがポイントです。
8月2日
手作りギョウザ
8月5日
辛味大根モチ
8月9日
ココナッツイエローカレー
8月11日
お煮しめ
8月11日
グリーンカレー
8月12日
キクラゲと小豆とココナッツミルク
たまにはしっかり解説を
夏は多量に汗をかき腎を弱めます。そこで陰陽五行説の腎(水)の属性である黒色の食材で気を高めるのがこのキクラゲと小豆のデザートの目的です。
8月13日
カボチャのスープ(土の属性)とココナッツミルク(金の属性)
8月13日
グリーンカレー(木の属性)
8月14日
鍋
8月15日
朝ごはん
8月16日
鶏カモ雑炊
8月19日
冷やしラーメン、手作りギョウザ
8月22日
シュウマイ
8月23日
カレーと味噌汁
8月25日
カレー豚汁
8月27日
バケット、チキンサラダ
8月28日
シャインマスカットケーキ
8月30日
晩酌
8月31日
スタ丼
0

毎日薬膳~2023年7月4日から2023年7月31日
おうちごはんを極めて健康ライフ!
バランスの取れた食事を目指すには季節の食材で様々な色をそろえるのがポイントです。
7月4日
もつ鍋だぃ
7月6日
アボカドディップほか
7月7日
青菜炒め、牛ごぼう
7月7日
スープストックイン自宅
モロヘイヤスープ
7月8日
ごまだれうどん
7月8日
コムタンスープ
7月9日
油味噌定食
7月9日
チーズタコライス
7月9日
鯛とマグロ
7月9日
フルーツ
7月10日
カレー
7月11日
タコライス
7月12日
マスクメロンで安心です。
7月13日
サラダうどん
7月17日
モーニング☕️😃☀️
7月22日
チーズパンケーキ
7月25日
チャーハン、揚げない油淋鶏
7月26日
トマトパスタ
7月27日
ちゃんこですたい
7月31日
うなぎ、なぜかサルサ
7月30日
おやき
7月30日
味噌汁
7月31日
アンコと緑茶
#薬膳#料理#おうちごはん#陰陽五行説#ココナラ#風水#健康
0

毎日薬膳~2023年4月25日から2023年5月21日
おうちごはんを極めて健康ライフ!
バランスの取れた食事を目指すには季節の食材で様々な色をそろえるのがポイントです。4月25日
刺身定食
4月25日
薬膳カレー
4月29日
精進料理
4月30日
焼肉定食
5月1日
たこ焼きパーティー
5月2日
韓国風料理
5月3日
みとう庵の冷やしやさいそば(再現)
5月4日
マグロ丼
5月10日
カレー
5月9日
スタミナ定食
5月12日
棒々鶏麺
5月14日
タコライス
5月14日
カレーピラフ
5月13日
ちらしずし
5月13日
モロヘイヤスープ
5月16日
オムライスとゆかいなおかずたち
5月18日
ざっかけない惣菜
5月19日
麻婆豆腐、スパゲッティサラダ
5月20日
余ったパスタと野菜ジュースでミネストローネ
5月20日
余った中華麺と麻婆豆腐でなかもと風
5月20日
お惣菜
5月21日
朝食
5月21日
チキンソテー
5月21日
ピザ
0

四柱推命の歴史
ココナラで占いを始めた天籟(てんらい)と申します。よろしくお願いします。ココナラにブログの機能があるのを発見したので、これからちょっとずつ書いてみようかなと思います。まず第一回目は四柱推命について書いてみようと思います。四柱推命は言わずと知れた中国発祥の、生年月日時をもとにして運勢を見てゆく占術です。ちなみに生年月日(時)をもとにして占う占術を、『命術』と言ったりします。命術の代表的なものを挙げると・四柱推命・紫微斗数・算命学・九星・ホロスコープ・数秘術・インド占星術などが挙げられます。その中でも四柱推命は占いの帝王などと呼ばれることもあり、メジャーで王道な命術と言えるでしょう。四柱推命が王道と言う割には、鑑定表を見たことがある人はご存知かもしれませんが、あまり見慣れない漢字が細かく書いてあって、なんだか難しそうな印象もあると思います。ただ、ごちゃっとたくさんの漢字が書かれていても、その中で一番大事なのは、干支(かんし)と呼ばれる、十干・十二支の組み合わせなんです。干支とは、中国に古くから伝わる暦(こよみ)で使われてきた記号です。ご存知かと思いますが、現在私たちが使っている暦はグレゴリオ暦(れき)と呼ばれる、西洋発祥の暦です。別名、西暦とも呼ばれます。西暦は西洋で発明されたもので、日本には明治時代に入ってきましたが、それ以前は日本や中国などの東アジアの国々では、太陰太陽暦と干支暦(かんしれき)という暦を適宜使い分けてたり、同時に使用したりしていました。太陰太陽暦は現在では旧暦とも呼ばれているので、知っている方もいるかもしれません。先ほども言いましたように、四柱推命で使用する暦は
0

毎日薬膳~2023年3月7日から2023年3月25日
おうちごはんを極めて健康ライフ!
バランスの取れた食事を目指すには季節の食材で様々な色をそろえるのがポイントです。
3月26日
白玉ぜんざい
3月27日
惣菜は近くのスーパー
3月28日
すき焼き。割り下を自分で作ったがイマイチ
3月29日
自家製すたどん
4月1日
カレー
4月1日
カレーうどん
4月2日
ノウボラのパスタとナポリタン
4月2日
メメクリームのトライフル
4月2日
なんとなくケーキ作り
4月5日
ローメン
4月8日
お揚げ、ジャージャー麺、ニラ玉
4月9日
オニオコゼづくし
4月12日
大皿盛り
4月13日
いつもの食卓
4月14日
野菜寿司
4月14日
バースデイー
4月18日
ベジ定食
4月19日
冷やし中華、ソーミンチャンプル、フルーツ盛り合わせ
4月20日
マグロ丼
4月21日
焼き肉行くぜ!
https://coconala.com/users/820261
https://coconala.com/services/493270
https://coconala.com/services/1041964
https://coconala.com/services/693695
#薬膳#料理#おうちごはん#陰陽五行説#ココナラ#風水
0

毎日薬膳~2023年2月6日から2023年3月6日
毎日薬膳~2023年2月6日から2023年3月6日
2月7日
しょうが焼き定食
2月7日
お好み焼き
2月8日
餃子
2月9日
青菜と豚肉いため、豚汁
2月11日
合格祝いの手作りピザ
2月12日
オムライス、お麩のからあげ、ジャガイモとさつまいものハッシュド、ポトフ、高野豆腐
2月13日
中華三昧
2月14日
あんかけ焼きそば、チーチク
2月15日
麻婆豆腐
2月16日
ドライカレー
2月17日
海鮮丼
2月19日
彩り定食
2月20日
つけ麺
2月23日
ローストチキン
2月24日
おつまみおつまみ
2月24日
生ハムフルーツ
2月25日
牛丼、肉吸い
2月26日
薬膳粥
2月26日
ぶたすき
3月1日
牛タンカレー
3月2日
おかずクラブ
3月3日
謎のひな祭り
3月3日
中華なイパネマ
3月4日
肉と寿司!
3月4日
ブリの煮付け
3月5日
the和食
3月6日
カレーうどんとちくわ
#薬膳#料理#おうちごはん#陰陽五行説#ココナラ#風水
0

毎日薬膳~2023年1月15日から2023年2月5日
毎日薬膳~2023年1月15日から2023年2月5日
1月15日
ショートケーキ子供が作ったので見た目はご愛嬌!!
1月15日
ヤーコンアカダイコンサラダ
1月15日
白菜と豚コマの中華炒め
1月17日
あんかけ焼きそば
1月18日
健康定食
1月19日
筑前煮、おきゅうと、チャーハン、味噌汁
1月20日
つけ麺
1月20日
手巻き寿司
1月21日
ハムサンドとコーヒー
1月21日
カレー
1月22日
暗殺者のポテト、和風タルタルソース
1月22日
朝食
1月23日
ほっこり定食
1月23日
暗殺者のポテト2
大根煮物
1月24日
ボルシチとサラダ
1月25日
パスタとサラダ
1月26日
しっぽくうどん
1月26日
古漬け再利用おやき
1月28日
和食外伝
1月30日
和食外伝2
1月31日
和食外伝3
1月31日
ソースカツ丼、定食
2月1日
タマゴカレー
2月1日
フルーツサラダ
2月1日
海鮮丼
2月2日
カレーうどん
2月3日
パンケーキと肉まんの飲茶
2月4日
和風ガパオライス
隠し味にしょっつる☆
https://coconala.com/users/820261
https://coconala.com/services/493270
https://coconala.com/services/1041964
https://coconala.com/services/693695
#薬膳#料理#おうちごはん#陰陽五行説#ココナラ#風水
0

毎日薬膳~2022年12月12日から2023年1月14日
12月12日
和風ビビンパ
12月16日
粕漬定食(キンメダイ、牛タン、鶏肉、豚肩)
12月18日
鳥うどん好き
12月21日
野菜炒め
12月21日
お好み焼き
12月21日
つけ麺の麺
12月22日
おつまみ3種
12月23日
冬至っぽい
12月24日
メリークリスマス!!
12月26日
夕飯あまりものでなんとかする系
12月27日
ラララ入船江戸の味♪
お正月の前に伊達巻の予行練習
12月28日
あまりもの定食
12月30日
晩酌😊
12月31日
実践!2023年福を呼ぶ「おせち料理」その1
~九星気学同会法と陰陽五行説の相生・相克の理論に基づく開運方法~
※かまぼこ以外全部作るという謎のプライド
1月1日
「おせち料理」その2
かまぼこ以外全部作るという謎のプライド
1月1日
「おせち料理」その3
※かまぼこ以外全部作るという謎のプライド
1月3日
睨み鯛の鯛飯
1月6日
洋風ディナープレート
1月7日
カレーだよ!
1月8日
お好み定食
1月9日
揚げ物★
1月13日
ネギトロ巻きと穴キュウ巻き
1月13日
ナポリタン
1月14日
カルボナーラ
1月14日
黒豆と栗鹿の子
0

実践!2023年福を呼ぶ「おせち料理」~九星気学同会法と陰陽五行説の相生・相克の理論に基づく開運方法~
■はじめに
「おせち」は中国から伝わった五節供の行事に食べられる「節目の日のための祝い料理」を示しますが、歳神様に捧げる供物としての正月料理を現在では「おせち」というようになりました。弥生時代に起源をもつようで、奈良時代には朝廷内で祝い料理として振舞われたようです。当時は山盛りになったご飯のみであったようです。おおよそ、現代の正月料理は江戸時代の武家文化に由来し、長寿、無病息災、子孫繁栄をその土地の名産を用いて作られます。おもにめでたさを語呂合わせや陰陽五行説の魔除けなどの思想が由来しているようです。江戸の長屋の住民もどんなに貧しくても祝三種である「黒豆」「数の子」「田作り(関西では「たたきごぼう」)」だけは必ず食べたという事が文献に見られます。■陰陽五行説について
さて、「おせち」を理解する前に、陰陽五行説について理解を深めましょう。
陰陽説とは、光と影、太陽と月、生と死、男と女など万物を陰と陽の2極に分け宇宙の成り立ちを説明しようとした思想で紀元前6世紀の中国にはその概念が存在していたとされています。
五行説とは、万物を木・火・土・金・水に分類して世界の成り立ちを説明しようとする思想で中国最古の経典にその存在がみられます。五行には木が燃えることにより火が生まれ、火が消えて灰すなわち土が生まれる。土から金属が産出し、金属が冷えると水が生まれる。最後に水を吸って木が育つという相生の関係と木は土の養分を吸い、土は水を吸う。水は火を消し、火は金属を溶かす。最後に金属は木を切るという相剋の関係があります。この2つの思想は古代中国、漢の時代に結びついて陰陽五行説となったとされてい
0

毎日薬膳~2022年11月17日から2022年12月8日
11月20日
えのきと牛肉の佃煮
追加購入→えのき、牛肉
11月20日
鶏鍋
追加購入→鶏肉、白菜、ネギ、えのき、人参
11月20日
筋の通ったフキ
追加購入→フキ
11月23日
和食三昧
11月24日
つけ麺
11月28日
中華丼
11月29日
田作り、もやし炒め、ゆず大根、フルーツ盛合せ
11月29日
刺し身切り落とし
11月30日
ツナサンド、フルーツ
追加購入→柿、パン、イチゴ、バナナ、みかん
11月29日
中華丼
11月30日
あんかけラーメン
追加購入→ラーメン
12月1日
おかずクラブ
12月1日
ピクルス作り
12月2日
カレーライス
12月5日
いぶりがっこクリームチーズ
12月7日
クジラ肉、チャーハン
12月8日
カボチャサラダ、スモークチーズ、自家製ピクルス
#薬膳#料理#おうちごはん#陰陽五行説#ココナラ#風水
0

毎日薬膳~2022年11月2日から2022年11月16日
11月2日
彩り惣菜
追加購入→かぼちゃ、鶏肉、牛肉、ごぼう、オクラ、大根、ニンジン、蓮
11月2日
みかんの季節
11月3日
冬至まで待てない!!小豆ぜんざい
11月4日
誕生日!
追加購入→スポンジケーキ、生クリーム、イチゴ、レタス、ベビーリーフ、パプリカ、鶏肉
11月5日
ベジ丼
秋の雑草たち
11月8日
ユッケ(レアステーキ)
追加購入→アンガスビーフ、ネギ
11月7日
豚の味噌漬け定食とシメジご飯
追加購入→豚肉、シメジ、ミックスサラダ
11月8日
ステーキとクラブハウスサンド
追加購入→バケット
11月11日
三平汁
11月13日
鳥肉のジャムソース添、ツナクレープ
追加購入→鳥肉、ベビーリーフ
11月14日
モツ煮
11月15日
酒の肴
11月16日
朝ごはんとデスクワーク
11月16日
鍋の季節、鶏鍋
#薬膳#料理#おうちごはん#陰陽五行説#ココナラ#風水
0

毎日薬膳~2022年10月9日から2022年10月22日
10月9日
蕪と柿の酢の物
追加購入→柿、蕪
10月10日
マカロニグラタン
追加購入→牛肉、チーズ、鶏肉、バター、マカロニ、ブロッコリー、玉ねぎ
10月11日
おつまみ百珍
ホタテ刺身、温野菜、イカ、串かつ
追加購入→ホタテ、串かつ、イカ、オクラ、ブロッコリー、パプリカ、レンコン
10月11日
包んだぜ!餃子150個
追加購入→餃子の皮、豚挽き肉、ニラ、生姜、キャベツ
10月12日
チラシ寿司、しめ鯖、野沢菜、味噌汁
追加購入→油揚げ、伊達巻、おおば、アスパラしめ鯖、豆腐
10月13日
納豆、卵、焼き鳥、カツとじ
10月14日
ネギトロ巻、柿と生ハムのカナッペ、赤ワイン
追加購入→ネギトロ巻、生ハム、チーズ、リッツ、赤ワイン
10月15日
筍若狭煮、ごぼうと牛肉のしぐれ煮
追加購入→ワカメ、筍、牛肉、ごぼう
10月15日
おでんうどん
追加購入→大根、練り物、豆腐、こんにゃく、冷凍うどん
10月17日
いさぎのよいメニュー、焼肉
追加購入→豚肉、焼肉のたれ
10月17日
野菜炒め(ラーメンスープ)
追加購入→カット野菜、ラーメンスープのもと
10月18日
レンコンのきんぴら、ふかし芋
追加購入→レンコン、さつまいも
10月19日
ステーキ、モロヘイヤスープ
追加購入→牛肉、スプラウト、モロヘイヤ
10月21日
カレーライス
追加購入→じゃがいも、ニンジン、カレールー、牛肉、豚肉、ピーマン、ナス
10月21日
すき焼きと微アルのジン
おいおい、S撃のGルメみたいなステマじゃないよ!
追加購入→牛肉、卵、ビアルジン
10月21日
カレーうどん、マグロ
追加購入→三つ葉、びんちょう
0

毎日薬膳~2022年9月23日から2022年10月9日
9月26日
野菜炒めと小物たち
追加購入→野菜パック、牛肉、豚肉、オカヒジキ
9月27日
あんかけラーメン
追加購入→中華麺
9月28日
和定食
追加購入→ごま豆腐、鰹節、小松菜、豚肉
9月29日
秋の味
追加購入→ナシ、プラム、さつまいも
9月30日
インドカレーとナンとパンと
追加購入→パン、ナン
10月1日
秋ごはん
追加購入→りんご、豆腐、水菜、かぼちゃ、鶏胸肉、納豆、ネギ、しめじ、ニンジン、油揚げ
10月2日
たぬきつねラーメン
追加購入→油揚げ、揚げ玉、中華麺、ネギ
10月4日
カレー、蕪と柿のサラダ
追加購入→カレールー、豚こま、柿、蕪
10月5日
白和え、棒々鶏、メンチカツとじ
追加購入→豆腐、柿、蕪、鶏肉、ネギ、卵、メンチカツ
10月6日
うどんすき焼き
追加購入→うどん、牛肉、春菊
10月7日
惣菜で済ませよう。
追加購入→揚げ物、セリ、鶏肉
#薬膳#料理#おうちごはん#陰陽五行説#ココナラ#風水
0

毎日薬膳~2022年8月22日から2022年9月2日
9月4日カレー、天津飯、きくらげの錦松梅風、プルーン、納豆
追加購入→牛すじ、豚肉、卵、きくらげ、じゃがいも、ニンジン、ブロッコリー、納豆、ネギ
9月6日
ローストビーフ、ベビーリーフ、栗、天ぷら、鶏唐揚げ
追加購入→牛肉、ベビーリーフ
9月13日
土佐田舎寿司
追加購入→ミョウガ、柚子酢、リュウキュウ、こんにゃく、油揚げ、卵
9月15日
ケールと牛肉とラム肉のサラダ
追加購入→ケール、牛肉、ラム肉
9月15日
うま煮ラーメン、酢の物、きんぴら、豚肉の佃煮
追加購入→野菜カット、中華麺、豚肉、きゅうり、ちくわ、ごぼう、人参
9月20日
敬老の祝重
追加購入→アワビ、キンメダイ、エビ、ぶり他
9月20日
焼肉丼
追加購入→牛肉、ケール
9月21日
麻婆丼
追加購入→挽き肉、豆腐、ネギ、豆板醤、甜麺醤
9月22日
冷しゃぶ、キャベツのカレー風味炒め、フルーツ盛り合わせ
追加購入→牛肉、レタス、キャベツ、ぶどう、プラム
#薬膳#料理#おうちごはん#陰陽五行説#ココナラ#風水
0

毎日薬膳~2022年8月22日から2022年9月2日
8月23日
油揚げ?いえいえ、フレンチトーストです。
追加購入→パン、牛乳、卵
8月24日
肉もやし炒め
追加購入→もやし、ニラ、豚肉
8月25日
クッパ、ネギぬた、カサゴの煮付け、りんご、梨、海老の鬼殻焼き
追加購入→ネギ、カサゴ、りんご、梨、海老
8月26日
ステーキ、サラダ
追加購入→ルッコラ、ベビーリーフ、牛肉、ソース
8月27日
野菜の黒酢炒め、枝豆
追加購入→枝豆、レンコン、じゃがいも、さつまいも、ピーマン、玉ねぎ
8月28日
イサキ、カンパチ、タイ
追加購入→イサキ、カンパチ、タイ
8月28日
BBQでハム作り
追加購入→豚肉、鶏もも
8月29日
豚汁
追加購入→豚肉、ニラ、大根、味噌、人参、レンコン、豆腐
8月30日
ハンバーグ定食
追加購入→挽き肉、高野豆腐、椎茸、パプリカ、パン
9月2日
おつまみ百景
追加購入→じゃがいも、玉ねぎ、ニンジン、もやし、イカ、枝豆、さつまいも
9月3日
スモークサーモンとカマンベールチーズクラッカー、ステーキサラダ
追加購入→牛肉、ベビーリーフ、ルッコラhttps://coconala.com/users/820261
https://coconala.com/services/493270
https://coconala.com/services/1041964
https://coconala.com/services/693695
#薬膳#料理#おうちごはん#陰陽五行説#ココナラ
0

毎日薬膳~2022年8月1日から2022年8月21日
8月4日
骨汁定食
追加購入→パイコー、小松菜、さつまいも、カボチャ、オクラ、枝豆、茄子
8月6日
冬瓜と挽き肉のあんかけ
精米したての新潟コシヒカリおにぎり
追加購入→冬瓜、挽き肉
8月7日
マーボー丼、グリーンサラダ、ポテトサラダ、カボチャサラダ、オクラの唐揚げ
追加購入→豆腐、挽き肉、オクラ、カボチャ、ベビーリーフ、じゃがいも
8月8日
サラダラーメン、麻婆麺、トマトの卵とじ、冬瓜スープ
追加購入→中華麺、トマト
8月9日
マグロ小松菜餃子もやしナムル
追加購入→マグロ、小松菜、もやし、挽き肉、餃子の皮、ニラ、キャベツ
8月10日
ステーキ、イカリング、野菜スープ
追加購入→アンガスビーフ、イカ
8月11日
天下一品こってり再現
追加購入→じゃがいも、にんじん、ねぎ、挽き肉、中華麺
8月15日
たら汁、きんぴら、肉3種、ナス味噌、小松菜、エリンギのマヨあえ
8月17日
手巻き寿司セット
追加購入→サバ、枝豆、鶏肉、椎茸、卵
8月18日
やきとり丼と夏おでん
追加購入→魚河岸あげ、さつま揚げ、ごぼう、人参、しらたき、油揚げ、切り干し大根、小松菜、豆腐
8月19日
実はカレー
追加購入→鶏胸肉
8月20日
魚尽くし
追加購入→アジ、イカ
8月21日
ニラ豚炒め、和風オムレツ、ガーリックシュリンプ、イカのぽっぽ焼き
追加購入→ニラ、豚肉、エビ
https://coconala.com/users/820261
https://coconala.com/services/493270
https://coconala.com/services/1041964
https://co
0

毎日薬膳~2022年7月1日から2022年7月10日
7月1日
茶色最強定食
カジキの煮付け、甘酢からあげ、タチウオ揚げ、小松菜おひたし、ご飯
追加購入→カジキ、タチウオ、鶏肉、、小松菜
7月2日
パパさんのパーンはこだま酵母
追加購入→小麦粉、こだま酵母、レーズン、くるみ
7月3日
鯛百景
鯛めし、ムニエル、煮付け
追加購入→鯛、ねぎ、オクラ、エリンギ
7月4日
タンドリーチキン
追加購入→鶏肉
7月5日
おつまみオールスター
イワシの甘露、骨せんべい、きゅうりの浅漬、マグロぶつ、きんぴらごぼう
追加購入→イワシの甘露、骨せんべい、きゅうり、マグロ、ごぼう、人参
7月6日
サラダ丼
追加購入→豚こま、牛肉、ベビーリーフ、パプリカ、ドレッシング
7月6日
親子丼、オクラとアスパラの茹で野菜
追加購入→鶏肉、卵、玉ねぎ、ねぎ、オクラ、アスパラ
7月7日
七夕素麺、野菜の寒天寄せ、何故かピーマンの肉詰め
追加購入→オクラ、ピーマン、人参、アスパラ、ひき肉、玉ねぎ
7月8日
カナッペ、生ハムメロン、アンチョビパスタ
追加購入→バケット、クリームチーズ、生ハム、メロン、サーモン、アンチョビ
#薬膳#料理#おうちごはん#陰陽五行説
0

毎日薬膳~2022年6月20日から2022年6月30日
6月22日
豆ご飯、タンドリービーフ、小松菜炒め、和風麻婆、鯖の一夜干し
追加購入→枝豆、小松菜、ひき肉、牛肉、鯖、豆腐
6月24日
鶏胸肉からあげ、モロヘイヤスープ
追加購入→鶏胸、モロヘイヤ、エリンギ
6月27日
真夏の冷やし中華&鶏モモ定食
追加購入→鶏モモ、小松菜、レタス、みょうが、冷やし中華、練り物、ごぼうにんじんとうもろこし高野豆腐
6月28日
余り物カレーとフルーツサラダ
追加購入→カレールー、もつ、レタス、グループフルーツ
6月29日
サラダ、豚の生姜焼き
追加購入→豚肉
6月29日
豚丼&カレー
追加購入→なし
6月30日
深夜の焼きそば定食
追加購入→焼きそば、豚肉、ベビーリーフ、ブロッコリースプラウト
#薬膳#料理#おうちごはん#陰陽五行説
0

毎日薬膳~2022年5月29日から2022年5月9日
5月29日
ビビンバ、メロン
追加購入→きのこ、豚肉、鶏肉、もやし、オクラ、きゅうり、小松菜、メロン
5月30日
実はカレー
追加購入→鶏肉、キャベツ、玉ねぎ
6月1日
フルーツ盛り合わせ、餃子、おきゅうと、豚しゃぶ
追加購入→豚肉、えご、メロン、パイナップル、ねぎ
6月4日
釣ってきたイワシを魚河岸揚げにして『おでん』にまで持ってくる!!
調理時間2時間
追加購入→しょうが、豆腐
6月5日
マクロビ風定食
追加購入→トマト、きゅうり、大葉、玉ねぎ、アスパラ、鶏肉、ピーナッツ、小松菜、ちくわぶ油揚げ
6月7日
梅雨イワシ
追加購入→イワシ、大葉、おから、油揚げ、こんにゃく、小松菜、鶏肉、ちくわ
6月9日
惣菜もたまにはいい。
追加購入→牛肉、ベビーリーフ、春巻き、コロッケ
6月9日
麻婆茄子風
追加購入→牛肉
6月10日
バケット
追加購入→バケット、ベビーリーフ、ベーコン、クリームチーズ
6月10日
クリームチーズクラッカーあんずジャムを添えて
追加購入→クリームチーズ、クラッカー
6月11日
伊達巻、ポテトサラダ、野菜炒め丼
追加購入→伊達巻、じゃがいも、サツマイモ、にんじん、白菜、にら、もやし、豚肉
6月11日
青梅のシロップ漬け
追加購入→青梅、氷砂糖
6月12日
誕生日!!
ピザ、サラダ、ケーキ
追加購入→コーン、トマト、レタス、ウインナー、ピーマン、いちご、桃缶、生クリーム、スポンジケーキ
6月13日
手巻き寿司
追加購入→マグロ、サーモン、アボカド、肉
6月18日
アボカドとじゃがいものチヂミ
追加購入→じゃがいも、アボカド、ねぎ
6月19日
カレーうどんとサラダ
0

初夏のさっぱりしたメニューと「五色健康法」
*上の画像は、昔勉強に使ったメモ書きを載せております。「ヘタウマ」(人に言われました)ですが……テーマに合っていたので(>ლ)天候が安定せず、あまり調子の上がらない日々です。そんななかでも食べやすいかなぁと思う食事を、先日つくってみました。・締めさば・冷やしニラの酢みそ・ひじきと大豆の煮もの・もずく黒酢です。締めさばは冷凍されたパックのものを冷蔵庫で半解凍にして、包丁で切るだけなので簡単です。もずくも小さなカップのまま、手軽に。ニラはさっとゆがいて冷水につけ、4センチほどに切りそろえ、酢みそに少量しょうゆを合わせたものをかけます。ここまですべて「酢」を使った味つけですが、同じくして「砂糖」も使っているので酸っぱいだけにならず、食べやすいです。ひじきの煮ものは缶詰のドライ大豆と、にんじん、湯抜きした油揚げを入れたほっこりとした一品ですね。さて、タイトルの「五色健康法」とはですが5つの色(赤・黄・緑・白・黒)の食品を取り入れることで、自然とバランスのとれた食事になるという考え方のことで、古代中国に始まった「五行説」が元となっているそうです。上の画像の文字をわかりやすく起こしますと、赤…鮭・カツオ・マグロ・鶏肉・豚肉・牛肉・ ニンジン・トマト・ハム・ウインナーなど黄…卵・味噌・油揚げ・ショウガ・タケノコ・ トウモロコシ・レモンなど緑…ホウレンソウ・ニラ・シソ・ブロッコリー・ きゅうり・ピーマンなど白…米・めん類・豆腐・はんぺん・白身の魚・ ハクサイ・ダイコンなど黒…のり・わかめ・ひじき・こんにゃく・ 黒ごま・シイタケなどとなっています。今回のメニューでは、さばとにんじん…赤、ニ
0

毎日薬膳~2022年5月10日から2022年5月29日
5月10日
ハッシュドビーフ、フルーツサラダ
追加購入→牛肉、ビーフシチュー缶、トマト、きゅうり、パイナップル、メロン
5月11日
炊き込みご飯と味噌汁
追加購入→なし
5月11日
つけ麺
追加購入→中華麺、スープ
5月12日
余り物定食
追加購入→なし
5月13日
オニカラ定食
追加購入→からあげ、しそ、ダイコン、油揚げ
5月14日
焼肉丼、付け合せ
追加購入→豚肉、スプラウト、かいわれ大根、ヤーコン、魚河岸あげ
5月17日
根菜定食
追加購入→人参、青梗菜、卵、豚肉
5月18日
冷やし中華はじめまして
追加購入→豆腐、中華麺、レタス、鶏肉、きのこ
5月19日
ステーキ
追加購入→バケット、牛肉
5月21日
カレー、ポテトサラダ、とうもろこし
追加購入→カレールー、じゃがいも、きのこ、とうもろこし、鶏肉、玉ねぎ
5月25日
パプリカの甘酢漬け、豚肉と鶏肉とニラの炒めもの、イワシの素揚げ、小松菜豆腐味噌汁
追加購入→パプリカ、豚肉、鶏肉、豆腐、小松菜、にら
5月24日
焼きそば弁当
追加購入→焼きそば、パプリカ、トマト、卵、小松菜、グレープフルーツ
5月27日
冷やし中華ともつ煮、隠れているけどハイボールもあるで(オヤジか!)
追加購入→卵 中華麺、みょうが、小松菜、もつ煮
5月28日
梅雨鰯
釣れた釣れた43匹
5月29日
手作り餃子
追加購入→餃子の皮、キャベツ、にら、ひき肉
#薬膳#料理#おうちごはん#陰陽五行説
0

ISD個性心理学を生活に取り入れると笑顔が増える 世界平和に繋がる事を確信しました。
『キヨくん、人(相手)は変わらないんだよ』代表に言われたシンプルながら深い一言でした。・わかっているようでわかっていない自分を知り・自分と相手は違うという事を受け入れよう人は違う事が学べました。あなたの善かれが、相手がい善いと捉えるかは違ってきます。AIも学習をしていくからどんどんと進化をしています。そんなAIにも出来ない事があり、人にしか出来ない事があります。・創造力を必要とする仕事・コミュニケーションを必要とする仕事これからの仕事や生活でも必要になってきます。オンライン化も進んでいて、オンラインになればなるほど、人との繋がりが、リアルで当たり前の事が、当たり前でなくなってくる。人とのコミュニケーションがいかに大切か、これから必要になってくると思います。ISD個性心理学は世界平和に繋がると確信しました。ISD個性心理学を通じて世界平和を志します。またまた、大きなこと言ってますね。自分も初めはそう感じていました。ですが、・もっと自分に向き合う・比較を止める自分を知れるから、相手との違いを受け入れる事ができます。これだと思います。勿論、自分だけが良ければはダメです。自分の変化できる可能性を知り、人のことばっかり気にせず、まずは自分に目を向けよう。助けになるのがこの学問です。伝えた事と伝わった事は違う事が多いです。戦争も、些細な言い争いも、デカいか小さいかで変わらないと思います。・自分以外が気になってしまう・周りに変わって欲しいななどに、エネルギーを使わずに、自分のいい才能個性を伸ばすために何をしようともっと全力でエネルギーを使ってほしいです。皆平等に違う才能個性を持っています。周
0

毎日薬膳~2022年5月1日から2022年5月9日
5月1日
柏餅風パン
追加購入→小麦粉
5月4日
鶏粥、高野豆腐の唐揚げ
追加購入→なし
5月5日こどもの日
中華ちまき風おこわ、うなぎもどき、紅白なます、柏餅
追加購入→豚肉、人参、もち米
5月6日
カレーライスとグリーンサラダ
追加購入→カレールー、豚肉、サニーレタス、玉ねぎ
5月7日
オボベジタリアンの日
レタスチャーハン、紅白なます、えのき茸の甘煮、ゴボウのマヨあえ、きんぴら、ウドの新芽あえ、サツマイモ
追加購入→ウド、サツマイモ
5月9日
困ったときのカレーライス、日の丸弁当、銀鱈の煮付
追加購入→じゃがいも、人参、ルー、豚肉、玉ねぎ、銀鱈
#薬膳#料理#おうちごはん#陰陽五行説
0

毎日薬膳~2022年3月27日から2022年4月9日
3月28日
春は苦味のサラダうどん(手抜き)
追加購入→冷凍うどん、カット野菜、豚肉
3月29日
八百屋の見切り品定食
追加購入→トマト、アボカド、卵、グリンピース、さやえんどう、鶏肉、じゃがいも、玉ねぎ、サツマイモ3月31日冷やし中華はじめまして☆
→小松菜、もやし、中華麺、豚肉、焼肉のたれ、冷やし中華のたれ
4月5日
ラムと豚肉のキーマカレー
追加購入→ラム、豚ひき肉、蓮、カラーピーマン、マッシュルーム、スナップエンドウ
4月6日
豚肉百景
きくらげの炒めもの、回鍋肉、青菜炒め
追加購入→豚肉
4月7日
疲れたのでチャーハン
追加購入→なし
4月8日
子供のリクエスト!入学祝いはフルーツポンチ
追加購入→いちごカットフルーツ
4月9日
ローストビーフ寿司
追加購入→アンガス牛
#薬膳#料理#おうちごはん#陰陽五行説
0

毎日薬膳~2022年3月13日から2022年3月19日
3月13日
卒園式のお祝いは野菜チラシ寿司
追加購入→菊の花、蓮、いんげん、マッシュルーム、ベビーコーン、ブロッコリー、油揚げ、三つ葉、トマト、スプラウト、カイワレ大根、伊達巻
3月14日
ガパオライスのライス抜き
追加購入→鶏肉、パクチー、ねぎ、しょっつる、しょうが
3月15日
ほうれん草のグラタン、ラタトゥイユ、バケット
追加購入→バケット、ほうれん草、チーズ、ホワイトソース、牛乳、ナス、牛肉、ピーマン
3月16日
或日の夕食
追加購入→ブロッコリー、蓮、ごぼう、豚肉、きゅうり、人参
3月18日
水の属性のスムージー
追加購入→ブルーベリー、レモン、トマト、セロリ
3月19日
子供の卒業お祝い善
追加購入→ブロッコリー、じゃがいも、いちご、ウド、パイナップル、バナナ、玉ねぎ
https://coconala.com/users/820261
https://coconala.com/services/493270
https://coconala.com/services/1041964
https://coconala.com/services/693695
#薬膳#料理#おうちごはん#陰陽五行説
0

毎日薬膳~2022年2月28から2022年3月5日
2月28日
特番もやしでかさ増しつけ麺
追加購入→豚こま、もやし、ニラ、中華麺、醤油タレ
3月2日
肉じゃが。じゃがいもと肉類は『土』の属性
追加購入→じゃがいも、人参、豚肉
3月3日
お好み焼きと焼きそば
追加購入→キャベツ、豚肉
3月4日
子供が作ったフルーツサンド
追加購入→食パン、いちご、生クリーム
3月5日
野菜カレー、野菜スープ、ポテトサラダ
追加購入→ナス、ブロッコリー、玉ねぎ、鶏肉、小松菜、ニンニクじゃがいも、サツマイモ、マヨネーズ、にんじん
https://coconala.com/users/820261
https://coconala.com/services/493270
https://coconala.com/services/1041964
https://coconala.com/services/693695
#薬膳#料理#おうちごはん#陰陽五行説
0

気とは何か?【現代風水論】
元気、勇気、磁気、気候。『気』の付く言葉はいっぱいあります。しかし、『気』を説明できる人はそうそういません。ある説明では『人体が発するエネルギー』。またある説明では『一般的に気は不可視であり、流動的で運動し、作用をおこすとされている。しかし、気は凝固して可視的な物質体となり、万物を構成する要素と定義する解釈もある。宇宙生成論や存在論でも論じられた。』と言われています。なるほど、水も鉄も個体に熱エネルギーを加えると蒸発して気体になります。その逆を考えるなら気体は凝固して液体になるので、これは強ち間違いではありません。 物質が持っているエネルギー(ブラウン運動、ファンデルワールス力。や未だ解明できない重力など)が気の正体の根本なのかもしれません。 風水では、気の流れを重視します。(その『気』の正体が問題なのですが)各流派を総合すると①北の定義は太陽真北や北斗七星の北ではなく磁北を用いることから「磁力を重視」する。②山から発生する気流や水脈の流れを評価する。③気や水は滞留せず適度に流れているのがよい。④(特に陰と陽の)バランスを重視する。という事は共通して言えるようです。 特に地球のチカラの源である磁力を重視するという点は特筆すべきでしょう。この地球の磁力は私たちにどのような影響を与えているのでしょうか?詳しい仕組みは省きますが、立命館大学 古気候学研究センターの論文では「磁力が弱まると寒冷化が起こる」との記載があります。ちなみに今まで11 回の地磁気逆転が起こり、気候へ大きな変動を起こしているんだそうです。地球の地磁気の強弱には太陽活動「黒点推移」が関係しているという事で、【太陽
0

毎日薬膳~2022年2月20から2022年2月27日
2月20日
しいたけハンバーグ、ピーマンの肉詰め
追加購入→しいたけ、牛豚ひき肉、パン、ピーマン
2月21日
びんちょうまぐろとアボカドの海苔巻き、豚肉のサニーレタス巻、澄まし汁、ポテトサラダ追加購入→びんちょうまぐろ、アボカド、サラダレタス、豚バラ、じゃがいも、にんじん、さつまいも、マヨネーズ、玉ねぎ、ソース、にんにく
2月22日
ポテトサラダその2、鶏肉ソテー、パスタ
追加購入→鶏肉、じゃがいも、サツマイモ、レッドオニオン、ベビーリーフ、トマト
2月23日
目覚めよ!インカ!
追加購入→じゃがいも(インカのめざめ)、銀鱈、牛肉、豚ひき肉、豆腐
2月24日
スーパーデジタルハイブリッドジェネリック油そば
鶏がらスープのもととゴマ油でなんとかする☆
追加購入→中華麺、もやし、豚こま、ニンニク
2月25日
甘味噌もやし炒め
追加購入→もやし
2月26日
ほうれん草のおひたし、むきニンニク(下ごしらえ)、親戚にもらったおやき、ポテトサラダ。そんな休日
追加購入→じゃがいも、ほうれん草、小松菜、サツマイモ、ニンニク、玉ねぎ
#薬膳#料理#おうちごはん#陰陽五行説
0

毎日薬膳~2022年2月13から2022年2月19日
2月13日
フルーツサンドリベンジ!
もはやサンドしないというコペルニクス的転回、パイナップルは『金』
追加購入→パン、生クリーム、いちご、フルーツ缶、キウイフルーツ、パイナップル、レモン
2月14日
まあ〜るく治めるたこ焼き
たこ焼きを発明した関西人に感謝!
追加購入→小麦粉、キャベツ、揚げ玉、ねぎ、タコの代わりのホルモン
2月15日鶏すき焼き
追加購入→鶏もも、白菜、ねぎ、豆腐、えのき、椎茸
2月16日唐揚げチャレンジ!!2kgのモモと胸肉を揚げまくる。鶏が絶滅したらうちの子の食欲のせいだ。。
追加購入→鶏胸、鶏モモ、片栗粉レモン
2月17日
チャーハン唐揚げ定食
追加購入→小松菜、エリンギ
2月18日
キムチ、チャーハン、麻婆茄子
キムチは辛
追加購入→キムチ、なす、豚肉
2月19日
栗おはぎ、栗おこわと豚汁
小豆は黒。薬膳では「腎(水)」を補強する。甘すぎは厳禁×
追加購入→あんこ、栗甘露煮、ニンジン、小松菜、豚肉、ゴボウ
https://coconala.com/users/820261
https://coconala.com/services/493270
https://coconala.com/services/1041964
https://coconala.com/services/693695
#薬膳#料理#おうちごはん#陰陽五行説
0

毎日薬膳~2022年1月29から2022年2月4日
1月29日ファミレスに行きたい次男。でも今は感染防止のためガマンなのだ。ということで、今日は、ファミレス風
ラタトゥイユの赤(火)、パスタの黄色(土)、鶏肉の黄色(土)、小松菜の青(木)
追加購入→鶏肉(胸、もも)、小松菜、ピーマン、なす、玉ねぎ
1月30日
皇帝レタス(山クラゲ)の中華風冷菜
甘酢とゴマ油でさっぱりと
酸味『木』、山クラゲ『木』
追加購入→山クラゲ
1月31日
明日は受験、今夜はカツ!!
豚肉『土』
追加購入→豚ヒレ、パン、キャベツ
2月1日
今日は『金』の麻婆豆腐。市販のソースは嫌いなのでスパイス調味料を組み合わせて作ってます!
2月2日
今日はカレー『金』をリクエスト。レタスの『木』を添えて
追加購入→カレールー、にんじん、玉ねぎ、豚肉、レタス
2月3日節分
さようなら丑!こんにちは寅年。
追加購入→牛肉、きゅうり
2月4日
和風ジャージャー麺
レタスときゅうりの『木』多め
追加購入→豚ひき肉、きゅうり、中華麺#薬膳#料理#おうちごはん#陰陽五行説
0

毎日薬膳~2022年1月22から2022年1月28日
1月23日辛いぜ『金』の豚ブロック肉のスパイス焼き
追加購入→豚ブロック肉
1月24日
なーんにもないけどケーキを作る。
デコは6歳の子供のセンス
酸っぱい系なので「木」の属
追加購入→生クリーム、シフォンケーキ、いちご、はっさく
1月25日
ネギと超高級和牛のぬた和えとごぼうと牛肉の佃煮。
ネギは『肺(金)』、ごぼうは『脾(土)』
追加購入→ごぼう、ネギ
1月26日
さぁ見よ!息子よ!この高校生の部活帰りの様なメシを!カレー『辛味の金』に焼肉『赤色の火』トッピング。しかもカレーはスパイスからきちんと作ったのだよ!ちなみに小松菜『緑の木』のすまし汁もあるのだ!ちなみに母は食べる前にお腹いっぱい。
追加購入→小松菜、牛肉、ジャガイモ、にんじん、たまねぎ
1月27日
手作りドラ焼き『小豆命』
黒色の小豆。実は優秀な薬膳『腎』を補強する『水』の属
追加購入→あんこ、卵
1月27日
舌平目のムニエルタルタルソースを添えて、白身は金の補強!
追加購入→舌平目
1月28日
豚丼の上に巨大卵焼き&ワンタンスープ
豚と卵『土』、椎茸『水』、小松菜『木』
追加購入→豚、卵、椎茸
#薬膳#料理#おうちごはん
0

実践!2022年福を呼ぶ「おせち料理」~九星気学同会法と陰陽五行説の相生・相克の理論に基づく開運方法~
はじめに
「おせち」は中国から伝わった五節供の行事に食べられる「節目の日のための祝い料理」を示しますが、歳神様に捧げる供物としての正月料理を現在では「おせち」というようになりました。
弥生時代に起源をもつようで、奈良時代には朝廷内で祝い料理として振舞われたようです。当時は山盛りになったご飯のみであったようです。
おおよそ、現代の正月料理は江戸時代の武家文化に由来し、長寿、無病息災、子孫繁栄をその土地の名産を用いて作られます。おもにめでたさを語呂合わせや陰陽五行説の魔除けなどの思想が由来しているようです。江戸の長屋の住民もどんなに貧しくても祝三種である「黒豆」「数の子」「田作り(関西では「たたきごぼう」)」だけは必ず食べたという事が文献に見られます。
陰陽五行説について
さて、「おせち」を理解する前に、陰陽五行説について理解を深めましょう。陰陽説とは、光と影、太陽と月、生と死、男と女など万物を陰と陽の2極に分け宇宙の成り立ちを説明しようとした思想で紀元前6世紀の中国にはその概念が存在していたとされています。五行説とは、万物を木・火・土・金・水に分類して世界の成り立ちを説明しようとする思想で中国最古の経典にその存在がみられます。五行には木が燃えることにより火が生まれ、火が消えて灰すなわち土が生まれる。土から金属が産出し、金属が冷えると水が生まれる。最後に水を吸って木が育つという相生の関係と木は土の養分を吸い、土は水を吸う。水は火を消し、火は金属を溶かす。最後に金属は木を切るという相剋の関係があります。この2つの思想は古代中国、漢の時代に結びついて陰陽五行説となったとされています
0

金運を下げるトイレ【現代風水論】
意外とやってしまう事で、金運を下げてしまっていることって結構あるんですよね。今回は金運を下げるトイレをご紹介します。■トイレに本棚 これはあるあるです。風水で「紙」は「吸う」ものとして扱われます。お札(ふだ)もそういう意味で霊気を宿させているものですし、同じ漢字でお札(さつ)も権力者の権威を宿しています。ただの紙がなぜ1万円札になるのかと言えば、それは紙に権威を吸わせているからです。たかが紙切れですが、権威を持った瞬間、人の命すら奪うのがお金のチカラですね。 数多の疫病のもとであったトイレは風水でも重要視されます。無処理のトイレ→肥溜め方式→ケンタッキー式便槽→浄化槽処理→水洗トイレと現代社会の歴史はトイレの処理の歴史といっても過言ではありません。住宅のどこにトイレを置くのか、為政者は都市のどこにトイレを置くのかがとても重要なのです。 さて、本(雑誌・新聞も)は言わずもがな紙です。このトイレの邪気を吸う紙です。本を置いて良いわけがありません。余計な紙も持ち込むべきではありません。 陰陽五行説的に見れば神は植物由来の『木』になり、金運の『金』を消耗させる存在になります。■トイレに観葉植物 これもよくみられます。。。人間が見ているときはイイのですが、想像してみてください。普段は暗い空間に生きている植物を置いているわけでして、かわいそうではありませんか??結構強い植物でもトイレに置くと枯れるんですよ。。。 環境工学的に見れば、本来家の中にあるものではありません。植物特に土壌を必要にするモノは湿気と各種の胞子を持っていますので家の環境に良い影響を与えません。 陰陽五行説的に見れば観葉
0

陰陽の理を知れば恋愛運が良くなる
世の中のすべての存在と現象を陰陽と規定することができるが、男女とも例外ではない。
人間関係に問題がある理由は、皆自分の基準で考えて判断するからだが、その関係の中で恋愛は特に難しい。
男性と女性はその本質が違うからだ。男性は陽で、女性は陰であるため、その間隙は文字通り天と地の違いだ。
(性別そのものの気質で見るのだ。個人の命式によって細かい違いはある)
男性は陽だ。陽は本質が優先だ。
そのため、男性は物を買ったり、人と会う時、そのもののスペックを重要だと考えている。主観的な考えや駄々をこねるのを嫌がる。
女性がボーイフレンドの前で最も多くするミスが、前後の状況を捨てて、自分の主観だけを言う行動だ。
男性はひたすら数値とファクトで接近するのが好きだ。そのように相手を信頼する。それは女性でも例外ではない。
「男性の言葉は額面通りに解釈しなければならない」
陽は単純だから!
このような男性を陰の基準(女性の視線)で判断してしまうため、男性との関係が難しくなる。
女性は陰だ。陰は関係が優先だ。
そのため、女性は物を買ったり、人に会うとき、周りの評判を重要に考える。商品レビューに敏感だ。
男性がガールフレンドの前で最も多くするミスは、ラインやメールが届けばすぐには返信しない行動だ。
女性は当然不安に思う。不安な状況を持続させるなら、むしろ確定した失敗を選ぶ。
それで、女性は捨てられたと感じられたら、先に捨てようとする。どんなにつまらない話だとしても、すぐ返事をもらってこそ安心する。
男性が 「重要な内容でもないのに、少し遅く返事すればいいよ!」
こう考えた瞬間、女性との関係は壊れる。
陰陽
0

四柱推命とは?
こんにちは。
今日は、私が鑑定で用いている”四柱推命”ってどんな占い?というのを簡単にご紹介させていただきます。
四柱推命は、生まれた年、月、日にち、(時刻←わかる場合。時刻は分からなくても鑑定できます。)をもとにして、その人の性格た運勢を表す占術です。
この四柱推命は歴史が長く、もともとは古代中国が発祥で日本には江戸時代に入ってきたと言われているそうです。当時江戸では、四柱推命によって占ってもらうのに、家を一軒建てられるほどのお金を出した人がいたとか・・・
四柱推命を学んで思ったのですが、思ってたよりも複雑で難しいんです(^^;
ただ、的中率は数多くある占いの中でも高いと言われています。
ここからは、四柱推命の2つの思想をご紹介したいと思います。
【陰陽思想】・・・自然界のあらゆるものは、”陰”と”陽”の相反するものから成り立っている。例えば、太陽と月、明と暗、静と動、表と裏などお互いに補い合うことで成立しているのです。
この思想を初めて知った時に、人も同じで、合わない人がいたとしても、自分と考えが合う同じような人ばかりでは、世の中成立しないということと同じだなと思いました。
また、人生もなんでも上手くいく時期、上手くいかない時期があるのも、ある意味普通のように感じるようになりました。
続いてもう一つの思想は、
【五行説】・・・目に見えるもの見えないものに関わらず、自然界のすべてのものは「木・火・土・金・水」に分類されるという考え方です。これらの要素も、互いに助け合ったり、時には害し合ったりして成り立っているのです。
四柱推命では、占う際にすべての方がこの「木・火・土・金・水
0

【妊娠しづらい体質】四柱推命と陰陽の調和
最近は結婚を遅くする場合が多いので、子どもの出産が自然に遅くなる。遅く子どもを生産しているため、子どもの数は格段に少なくならざるを得ない。
したがって、少子化問題が国家的キーワードであることは誰もが知っていることだ。
先日、結婚して5年も経った夫婦が出産の問題で相談を依頼した。これまで、子供がおらず、悩んでいるという。
「命式に子どもがいなければ、諦めて他の方法を探してみる」と言って、心配のこもった相談を始めた。
命式を鑑定してみると夫婦共に相当な問題があることがわかった。
つまり、夫婦共に命式が片方に偏っていた。このような命式を、われわれは陰陽の調和が合わない「偏枯(へんこ)」 (陰陽のどちらか一方に傾いたものを指す)命式と呼ぶ。
命式の構成は男女ともに午月の火の日柱で、周辺の構成要素ともに水の気運がないか、または非常に不足した熱い熱気に満ちていた。
そのため、このような命式の構成では妊娠しづらい体質なので、自分の体をある程度管理してもだめなら、医学の力を借りて人工受精法を選ぶように勧めた。
我々は四柱推命学をよく占う手段としてのみ知っている場合が多い。
しかし、それは偏見だ。もちろん占術で活用されている現実なので、そのように考えるのも無理はない。
しかし、占術に劣らず重要なのが医学だ。
四柱推命命式とは、その天気を地に降ろす時期と質量を年月日時と五行別に分けて詳しく記録した天気の明細書である。
そのため、四柱推命命式を見ると、その主人公の人体を構成した五行(五臓六腑)の質量と
0

フライングスター風水について(その2)
占術には『命』『卜』『相』がありそれぞれ役割が異なります。『命』は運命、『卜』は決断のタイミング、『相』はバランス・守りのようなものです。地相家相は『相』にあたり、いわば守りの環境学と言えます。守りが固い城も陥落することがあります。『相』よりも強い『命』の時は『相』だけでは人生を開くことはできません。また、古くからの言い伝えが工学的評価を得て、技術基準、やがては法令の規制にまで評価されたものが多々あります。シックハウスの24時間換気、採光、構造の吹き抜け等。よって、今でも科学的エビデンスを得ていない事柄でもゆくゆくは評価される可能背があるかもしれない。風水の教えを守るという事はそういう事になります。よって、家相なのどの『相』で金運が向上するのではなく、全体のバランス、対人関係、仕事でお金を稼ぐ、そして、家に帰ってその日の悪運を落とす。生きるためのバックグラウンドの整備になります。個々から運命と戦って道を切り開くのはご自身の努力になります。 西に黄色置いて黙っていれば大儲けという事ではないという事を勘違いしている方が多くいる現実は私たちの啓蒙不足だと言えます。
さて、フライングスターですが、これは欧米的思想で主に都市計画をする際の風水。通常の流派と違う点は、時間軸がある点です。広告宣伝のおかげで『即効性』などと扇動されていますが、本質的には陰陽五行説のバランスを取るということに変わりはありません。日本に伝わる際に規模感が都市から住宅へと変化したようです。ですので、『世界地図』でハイキングに行くようなちぐはぐなことが起こっています。私の流派はもっと『陰陽(五行)体質』を知り
0

現代語訳『家相秘伝集(上巻)(天保11年)』著:松浦琴鶴 訳:左人統紳
まえがき
鬼門に玄関を作らない。裏鬼門に台所を・・・と現代でも多数の人が家相を気にして間取りを考えている。ある調査によれば日本では鬼門裏鬼門を気にする人が7割いるといわれ、大半のハウスメーカーも間取り作成の際は簡易な方位盤を図示できるように対応しているという。この鬼門裏鬼門は古の中国の陰陽五行説を起源としているが、その原産地の中国では日本ほど重視しているわけではない。ちなみ陰陽五行説では、中心、鬼門である北東と裏鬼門である南西『土』に属されている。『土』は季節で言えば、土用(旧暦では季節の合間、1年に4回ある季節)で、この土用は、農耕や土工事など土に触る行為を忌避している。日本の様に四季がはっきりとしている農耕社会では、土の神「土公神」が重視され結果として、『土』の属性である、中心、鬼門、裏鬼門が家相で重視されるように発展していったのではないかと訳者は考えている。本書も中心、鬼門、裏鬼門を特に重視して書かれており、現代の日本の家相の礎や源流を知る重要な資料であると考える。本書の著者 松浦琴鶴 について
松浦琴鶴(マツウラキンカク)は徳川中期の易占家。大阪の人。父の名は東雞で同じ易学者。名前は純逸、号は琴鶴、観濤閣。家学を父に受け、観相をもつてその名大いに著はる。天保頃の人。(大阪人物誌より)北九州一帯で古代から勢力を保っていた松浦一族を源流に持ち、現代でも琴鶴を初代とした松浦長生館という鑑定所は存在している。
著書では『琹鶴』と『琴鶴』の名が混在しており明治21年出版の『家相秘伝書』では、上巻の著書は松浦琹鶴、下巻では松浦琴鶴と名乗られている。下巻の内容も主語が別人のような言い
0
2,000円

まじめに風水☆あなたの体質に合う風水処方します。鑑定実例
実例鑑定が見たいというお客様が多いため鑑定の実例をご紹介します。
鑑定のご依頼について迷っている方はこちらをご購入いただきご検討ください☆ご購入後ご依頼いただいた際は、サービス料金からブログ購入分をお値引きさせていただきます。(例:5000円サービスでブログが500円の場合は、4500円でご提供)≪はじめに≫
完璧な地相や家相はありません。たとえ現状で非の打ちどころのない地相・家相であっても、状況が変化し、ある日突然、凶相へと変化することもあります。大切なことは、常に地相・家相・体質の陰陽のバランスを常にとりながら、弱点を補っていくことです。
進学・結婚・出産・体調の変化に応じて見直し、継続的に改善を続けていくことをおすすめします。
≪思想と流派について≫
東洋医学の思想に基づく体質チェックをおこない、地家相は主に陰陽思想をもとに建築工学的な観点から合理的説明ができるもので構成されています。(方位(鬼門)や古典風水は、工学的合理性に欠くため本流派では積極的には採用しておりませんが、参考補足的に採用しています。)
上記を踏まえたうえで、建築士資格保有者として良識のある回答をいたします。
≪免責事項≫
1、各種法令を順守します。特に建築士法第23条の業に当たる行為、薬機法等の効果効能を謳う行為はいたしません。
2、紛争の解決に本鑑定書を使用することはできません。また、この鑑定により起因する紛争や諸問題について責任を負いかねます。
3、法令の制限に関する判断は行いません。不動産の購入等につきましては、最終的にはご自身の判断で行ってください。
4、許可なく本鑑定
0
500円
.jpg)
周易と六爻占術の特徴
周易は「周の易」という意味だ。すなわち、中国の周の占う本だ。
周易は陰陽思想に基づいて陰爻、陽爻、中庸思想を中心とする基本哲学が流れているが、これから推測すると少なくとも春秋戦国時代の陰陽五行家が登場し、陰陽論的世界観が成立してから(鄒衍の陰陽五行説、紀元前3世紀頃、孔子の死後200年余り)中庸が成立したと見るのが妥当である。孟子にも周易に関する話が一言も登場しないことを考えれば、周易は少なくとも孔子はもちろん、孟子以降の戦国時代末期から漢初期に成立したと見るのが妥当である。
周易は ☰(乾) · ☱(兌) · ☲(離) · ☳(震) · ☴(巽) · ☵(坎) · ☶(艮) · ☷(坤)という8卦で構成されるが、これら8卦を重畳させて8x8=64卦、386卦に卦辞と爻辞をそれぞれ付けてその意味をもって未来を占う。周易の卦辞や爻辞は非常に抽象的な言語に並んでいるため、これらの言語は幅広い解釈の可能性を残している。したがって、周易はその抽象的な卦辞と爻辞に関する多様な解釈を基本とするので、非常に遠い未来である数百年後も推論することができる。代わりに、その抽象性によって、高度に専門化、練習されなければ、とんでもない解釈をしやすいという点だ。
例えば、周易一番目の卦である重天乾卦5爻に飛龍在·天利見大人(龍が空を飛んでいるので大人を見ると有利だ)、六爻に亢龍有悔(頂上に上った龍には後悔がある)となっているが、これは非常に広範囲な解釈の余地を持つ。また周易には利涉大川(大きな川を渡れば利になる)という爻辞もよく出てくるが、これら爻辞はすべてその抽象性
0
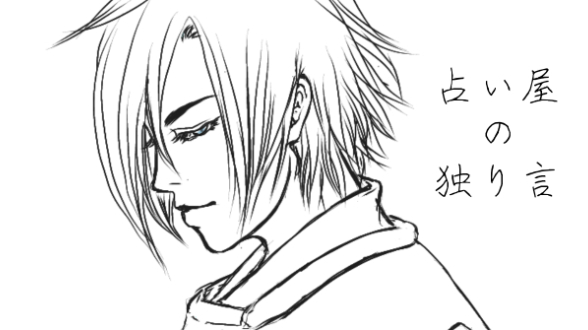
生活に息づく陰陽五行①
東洋占術を扱っていると、漢字ばかりで堅苦しいと思われる事が多いもので、どうにか面白さをお伝え出来ないものかと思いまして。多くの東洋占術においてその根底にある思想に「陰陽五行説」というものがあります。正確には「陰陽説」と「五行説」を合わせたものなので元は別の思想なのですけれどね。「陰陽五行」と書いてはみましたが、なんと読むかご存じですか?「いんようごぎょう」と読む方が多いかもしれませんが、「おんようごぎょう」と読む方が研究者や専門家ウケは良いです笑陰陽と書いても小説やコミック、映画などの陰陽師のイメージが強いですが、実際の陰陽師は陰陽五行説と関係しているから陰陽師と言われたわけでもないのをご存じですか?「陰陽」と書いて「うら」と読み、陰陽(うらおもて)によって吉凶を「占う」ため陰陽師とされていたのですね。陰陽師とは早い話が、国家公務員占い師です。私が各所で、現代に陰陽師は存在しないと口酸っぱく言っている理由は、現在、国家公務員の役職として占いを専門に行う部署がないため、そこで働く人も居ないので陰陽師は存在しないからです。ちなみに。陰陽師は占いを専門にする人達ですので、お祓いなんてものは基本的に神職や僧侶の役目でした。陰陽師にその役目が回ってきた時には、密教や神道、修験道など他の宗教などの祓いを元に構成していて、祓うというよりも災厄に対して「これをお供えするから、頼むから出ていってくれ」「どうかこの辺で勘弁してください、お願いですから静まってください」という方法を取っていたので、現代で多くの方がイメージする安倍晴明のイリュージョン的なお祓いや結界の張り方はフィクションです。もちろん
0

陰は悪い? 陽は良い?
「陰って悪そう。 陽は良さそう。」字のイメージでそう思われる方もいらっしゃいます。陰は悪ではなく陽は善ではありません。生と死、表と裏、明と暗のようにどんな事象にも必ず陰と陽が存在するのです。太極図は白い部分にも黒い点があり大きな陽の中にも必ず陰が存在し「陽が盛んである」と表しています。同様に黒い部分にも白い点があり大きな陰の中にも必ず陽が存在し「陰が盛んである」と表しています。一方が存在することでもう一方が成り立つ。それによって自然の秩序が保たれているのです。
0

陰陽五行説
陰陽五行説(いんようごぎょうせつ)算命学をはじめ中国で生まれた占いは陰陽五行説が根本にあります。𓂃 𓈒𓏸「陰陽」についてこの世界には生と死、表と裏、明と暗のように互いに対立する性質を持った2つの気が存在します。古代東洋思想では自然界の法則を理解するためにこの2つの気を「陰」と「陽」で表しました。どちらかが多すぎたり少なすぎたりするとバランスを失い正常な状態を保てません。幸せになるためにはお互いを尊重し補い合っていくことが大切です。【性質の陰陽】●陰… 冷やす、鎮める、堅固、湿潤、閉じる○陽… 温める、動かす、柔軟、乾燥、開く【自然界の陰陽】●陰… 秋冬、北、夜、月、水○陽… 春夏、南、昼、太陽、火【人体の陰陽】●陰… 下半身、体幹、腹、臓、血○陽… 上半身、四肢、背、腑、気𓂃 𓈒𓏸「太極図」一度は目にしたことがあるかと思います。「陰と陽のバランス」を表した図です。白色が「陽」黒色が「陰」を表しており天地万物あらゆるものは陰と陽のバランスによって成り立つことを示しています。陰と陽のバランスは人それぞれ違います。理想的な生き方を過ごすためにご自身のバランスを知ることが大切です。
0

毎日薬膳~2024年2月1日から2024年2月29日
おうちごはんを極めて健康ライフ!
バランスの取れた食事を目指すには季節の食材で様々な色をそろえるのがポイントです。
2月5日
しょうが焼き定食
2月10日
焼肉定食
2月12日
タマゴいっぱい
2月12日
ギョウザ
2月12日
サバ定食
2月13日
三色丼
2月14日
ちらし
2月17日
朝食☕️🍞🌄ロサンゼルス
2月21日
うどん、レモネード
2月22日
ちゃんこうどん
2月25日
牛タン定食
2月26日
焼肉定食
2月29日
二日酔いに煮込み
0

毎日薬膳~2023年12月1日から2023年12月30日
おうちごはんを極めて健康ライフ!バランスの取れた食事を目指すには季節の食材で様々な色をそろえるのがポイントです。
1月2日
けんちん汁
1月3日
鳥なべ
1月3日
ブリ刺し
1月7日
ふぐ刺し
1月7日
魚と馬刺
1月8日
白菜炒め
1月10日
大根と鶏肉の薬膳カレー
1月11日
ステーキ丼
1月16日
タマゴカレー
1月17日
ギョウザとスープ
1月18日
焼肉定食
1月21日
チキンソテーとオニオンスープ
1月21日
カレーライス
1月22日
お惣菜
1月24日
ビーフシチュー
1月26日
もつ鍋
0

1月21日 五行バランスで「火」と「水」
1月21日日曜日 仏滅甲申初大師・初弘法、料理番組、ライバルが手を結ぶ、ユニベアシチィ、Spartyのパーソナライズ、三十路、瞳の黄金比率の日です。1866年慶応2年。薩摩と長州との薩長同盟が結ばれた日。陰陽五行説で、火と水はお互いけん制し合う、妨げ合うというのが有名。まさに薩長同盟の前の薩摩と長州。呉越同舟。ただ、呉越同舟のように、いざ船が沈みかかった時はお互い敵同士でも助け合います。火と水も同様。お互いそれぞれのエネルギーを妨げますが、煮るのは火の上に水が必要。そして火の勢いをコントロールするのにも水が必要です。普段は敵対していても、必要な時は必要に応じて調節するのが五行の面白い所。今日はグレー🤍がラッキーカラー。今日も良い日に💞
0

毎日薬膳~2023年12月1日から2023年12月30日
毎日薬膳~2023年12月1日から2023年12月30日
おうちごはんを極めて健康ライフ!
バランスの取れた食事を目指すには季節の食材で様々な色をそろえるのがポイントです。
12月1日
炊き込み御飯、煮込み
12月2日
煮込みうどん
12月3日
ベイクドポテト、オニオンスープ
12月3日
連子鯛と太刀魚
12月4日
鴨鍋
12月5日
手作り餃子
12月11日
あら
12月12日
ビビンパ
12月20日
ホルモン煮込み
12月22日
冬至のホウトウ
12月24日
クリスマスディナー
12月26日
惣菜
0

毎日薬膳~2023年10月3日から2023年10月26日
おうちごはんを極めて健康ライフ!
バランスの取れた食事を目指すには季節の食材で様々な色をそろえるのがポイントです。
10月3日
タコとキュウリの酢の物、おかひじき
10月4日
スモークサーモン
10月4日冷やしうどん
10月5日
お惣菜
10月6日
ちゃんこ鍋
10月7日
手巻き寿司
10月8日
なすのばら肉巻き
10月8日
朝ごはん
10月9日
鰺刺
10月9日
オクラの寒天よせ
10月10日
カオガンマオ
10月15日
雨の日の昼
10月16日
鳥鍋
10月20日
作り置きのおかず
10月23日
カオガンマオ
10月23日
カオガンマオ定食
10月24日
チャーハン
10月25日
カンパチのエスニックカルパッチョ
10月26日
ステーキ丼
0

現代風水論【丁字路玄関対処編】
自分の家の前が道路の突き当りになっているという事はありませんか?風水では一律に凶という事ではなく交通量や私道などの条件によっては凶が少ない場合もあります。もし、ある程度凶が小さい場合は対処も可能です。華僑風水では↓のような対処法があります。 ですが、私はあまりアイテムに頼るのではなくもう少し物理的に対処する方法をとります。具体的には色々あり誤解を与えて独り歩きしないためにも記載しませんが。。。特に殺気が起こす事例は方位により様々です。おおむね喧嘩が起こる。散在する。変な人がかかわる。などです。心当たりのある方はぜひご相談を。。。こちらの記事も参考に
0
あなたも記事を書いてみませんか?
多くの人へ情報発信が簡単にできます。
ブログを投稿する
多くの人へ情報発信が簡単にできます。


















.jpeg)
















